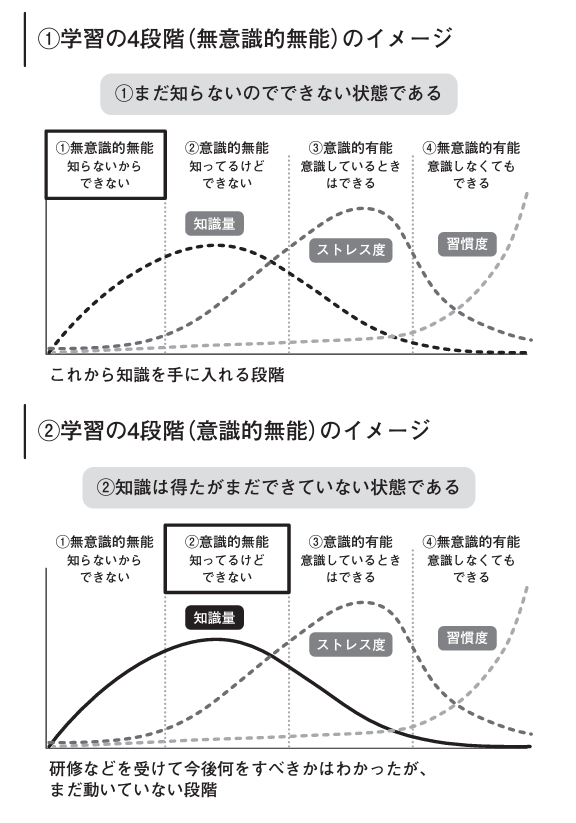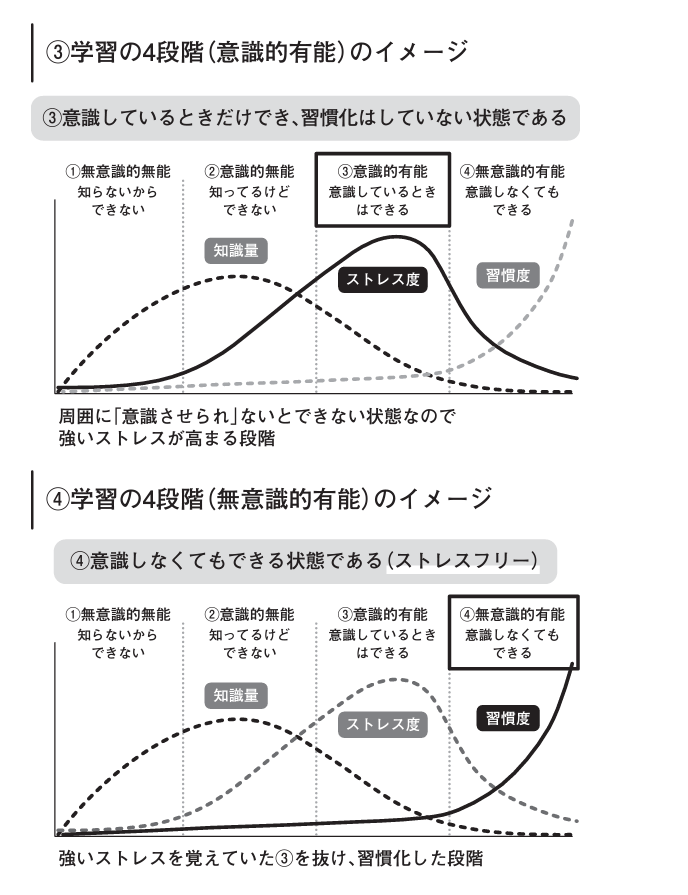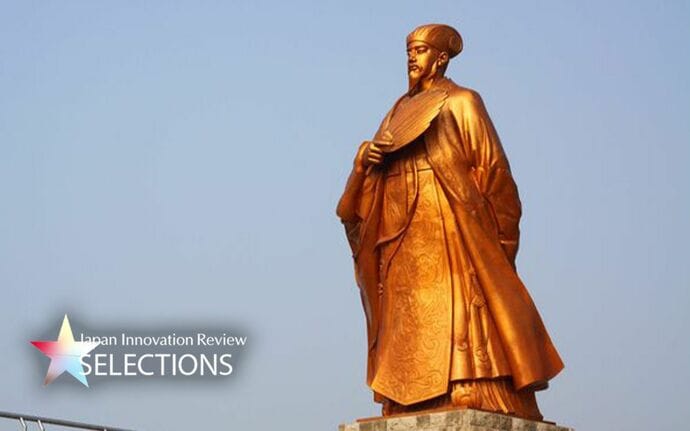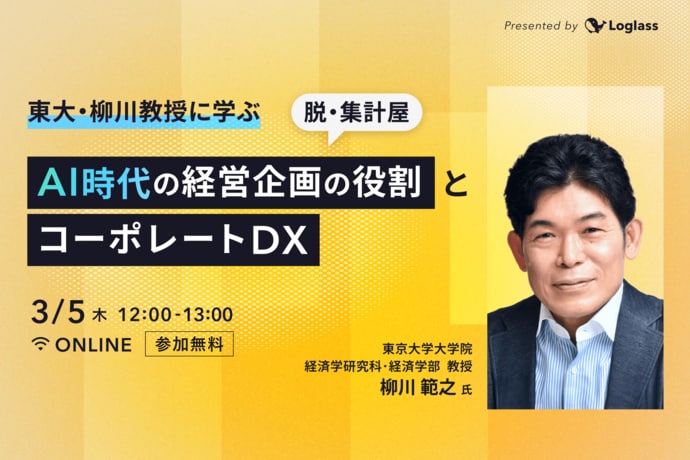maroke – stock.adobe.com
maroke – stock.adobe.com
「ホワイト過ぎる職場に、成長の機会を奪われると感じて辞めてしまう」――若者の退職を招く新たな問題に、「厳しくしても優しくしてもダメなら、いったいどうすればいいんだ!」と頭を抱える担当者は多い。本連載は、今どきの若者とどう関わるのが正解か、20年近く企業の組織改革に携わってきた経営コンサルタントが、11の具体的シーンで解説した『若者に辞められると困るので、強く言えません――マネジャーの心の負担を減らす11のルール』(横山信弘著/東洋経済新報社)から内容の一部を抜粋、編集。
第4回目は、部下が学習し、成長していく4つの過程を紹介。それぞれの段階で上司に必要とされる対応方法を解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 ゆるくてもダメ、Z世代を劇的に変える「ちょうどいい」マネジメントとは?
■第2回 部下を褒めるよりも100倍大事な「アクノリッジメント」とは何か?
■第3回 「スピード」と「完成度」、どちらを部下に優先させるべきか
■第4回 「無意識的無能」から「無意識的有能」へ、部下を成長させる「学習の4段階」とは?(本稿)
■第5回 なぜ知識や能力が足りない人ほど「馬鹿の山」に登りたがるのか(6月17日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
「学習の4段階」とは何か?
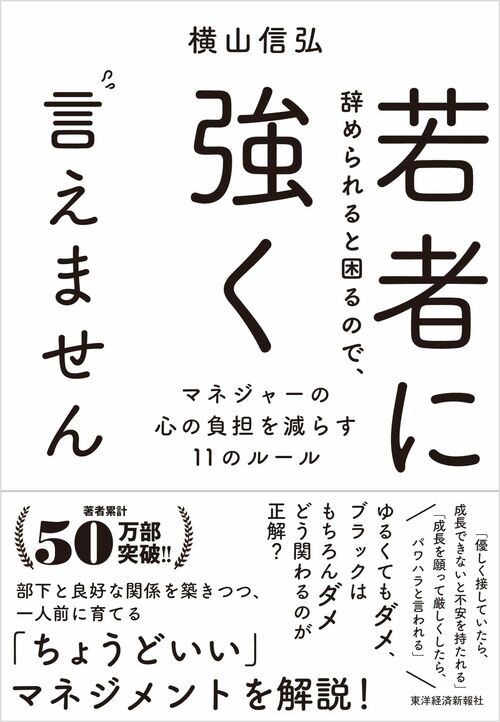 『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)
『若者に辞められると困るので、強く言えません』(東洋経済新報社)
有名な「学習の4段階」を用いて部下の成長を考えると、以下のように分類できる。
(1)無意識的無能(知らないからできない)
(2)意識的無能(わかってるけどできない)
(3)意識的有能(意識するときだけできる)
(4)無意識的有能(意識しなくてもできる)
1つ1つ解説していこう。
1つ目は「無意識的無能」、「知らないからできない」という状態である。車の運転にたとえると、運転方法を知らないから運転できない、ということだ。
2つ目の「意識的無能」は、「知っているのにできない」という状態である。車の運転にたとえると、運転方法は学んだけれども実際の運転はできない状態のことだ。
3つ目の「意識的有能」とは、「意識しているときはできる」という状態を指す。トレーニングを繰り返し、身体に覚え込ませている最中である。教習所で何度も運転の練習をすると、意識すればなんとか運転できる状態になるだろう。
ただし「意識的有能」状態のときは肩に力が入り、常に緊張する。まだ慣れていないから、それなりのストレスがかかるものだ。この状態のときが一番大切で、しっかりと状態を見える化し、マネジメント対象とする。
4つ目が「無意識的有能」だ。これは無意識でも、できてしまう状態のことだ。「できる」のではなく、「できてしまう」状態だ。
ストレスは一切なし。モチベーションなどまったく関係がなくできる。なぜなら、それをすることが「当たり前」になっているからだ。いわゆる「習慣化」した状態のことである。
この状態になれば、頑張らなくてもよくなる。なので、マネジメント対象から外す。無理をさせないようにする、ということだ。
車の運転で表現すればわかりやすいだろう。運転に慣れている人であれば、頑張らなくても運転できる。運転の細かい所作を意識しなくても、運転して目的地に到着することができる。もう頑張る必要はない。力を抜いて運転すべきだ。
このように部下を成長させる際、真っ先に考えなければならないのが、どんな行動を「無意識的有能」の状態にするか、である。
これさえハッキリさせれば、部下を成長させるマネジメントは、もう理解したようなものだ。