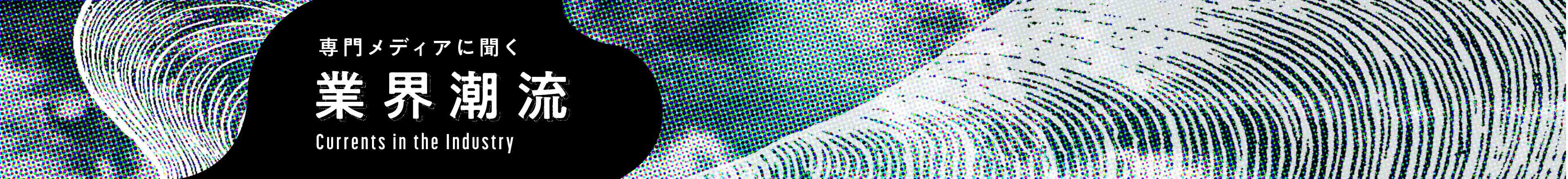写真提供:新華社、日刊工業新聞/共同通信イメージズ
写真提供:新華社、日刊工業新聞/共同通信イメージズ
世界の化学業界では今も、規模を求めて合従連衡が加速している。こうした中、日本の化学業界が持つ強みは何か、海外に対する競争優位性は維持できるのか。化学工業および周辺産業の動きをカバーする日刊専門紙「化学工業日報」の取締役編集本部長編集局長・渡邉康広氏に聞いた。
規模で海外企業に圧倒される日本の化学メーカー
――化学業界はグローバル競争が激しい分野だと思います。世界の中で日本の化学会社はどのようなポジションに置かれているのでしょうか。
 【化学工業日報】
【化学工業日報】1936年に設立され、間もなく90周年を迎える日刊専門紙。化学会社を中心に商社、プラント、物流などの周辺事業者、さらには化学品を部材として製品を製造している自動車メーカーや家電メーカーなども含め、13万人の読者を擁し、海外支局も含め総勢60人の記者が日々100本以上の記事を新聞、電子媒体などで発信している。
拡大画像表示
渡邉康広氏(以下・敬称略) 2022年のC&EN(Chemical&Engineering News、米国化学会が発行するニュース媒体)による調査結果では、世界の化学会社を売上高でランキングすると、1位はドイツのBASF、2位は中国のシノペック、3位が米国のダウと海外企業が並び、日本企業はかつてのように10位以内に入る会社はなく、売上規模では海外勢に大きく後れを取っています。
欧米の化学会社の売上規模が巨大化しているのは、自らの強みを最大限に引き出すために合従連衡を推進しているからです。イノベーションを生み出す研究開発は規模が大きい方がより多く捻出しやすく、また一国を代表するような規模の会社に進化すれば政府への発言力が増し、業界もとりまとめやすいはずです。
例えばドイツのBASFは、「総合化学メーカー」という看板を掲げてありとあらゆる化学製品を製造していますし、アメリカのダウは基礎化学品(エチレンやプロピレン、トルエン、ベンゼンなど、合成樹脂や洗剤、肥料などさまざまな製品の原料になるもの)に特化しています。規模の拡大と得意分野の深掘りを同時に進めているのですね。
日本はどうかと言いますと、広義の化学会社は上場企業で200社以上、未上場も含めるとおよそ2万社に達しており、業界再編を進めないことには、少なくとも規模で海外勢に立ち向かうのは難しいでしょう。
――それでは、日本の化学会社の特徴、強みは何でしょうか。
渡邉 スペシャリティケミカルに特化する傾向が強まっています。少品種大量生産される汎用化学品に対し、スペシャリティケミカルは多品種少量生産されるもので、医薬品、農薬、化粧品、塗料、添加剤、接着剤などさまざまな化学品があり、半導体、フラットパネルディスプレー、タッチパネル、燃料電池といった先端分野における製品群に用いられています。
現状、汎用化学品は主に中国や中東など、石油資源を持つ国が価格競争力を強めており、日本の化学会社は価格面で太刀打ちできなくなってきています。この30年ほど、日本の化学会社は付加価値の高いスペシャリティケミカルの分野で、コツコツと実績を積み上げてきましたが、ここにきてスピードを加速させています。
例えば半導体材料の世界大手であるJSRは、半導体の製造に不可欠なフォトレジストという製品で世界トップメーカーの一角を占めています。フォトレジストは樹脂や溶剤、感光材、添加剤といった多種多様の薬剤を投入し、調製、ろ過といったプロセスを、クリーンルーム内に設定された設備を使って、厳密な管理の下に製造されています。こうした微に入り細をうがつ製品製造は、日本企業の得意とする分野の一つです。
そしてもう1点、これも日本の化学会社の強みだと思うのですが、信越化学工業の塩ビ(塩化ビニル樹脂)事業に見られるように、世界の塩ビ需要に応えられるだけの、安定した供給体制を確立していることです。同社が1973年に米国で創業したシンテック社は、塩ビという汎用品の世界において、創業時は米国13位だったのが、現在は世界1位になりました。