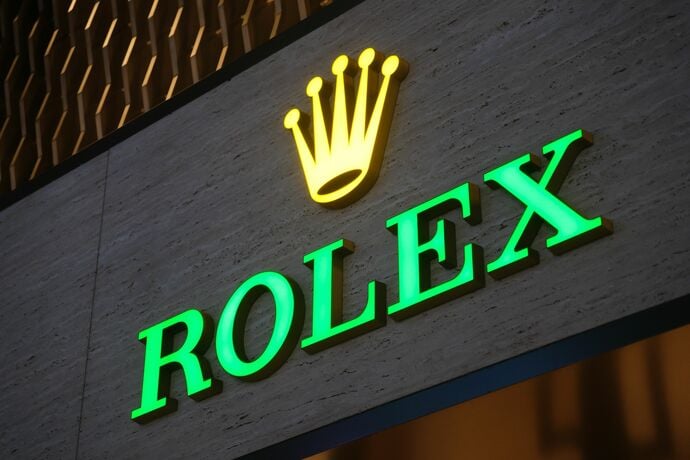獨協大学経済学部経営学科 教授の黒川文子氏(撮影:川口絋)(日産 サクラ写真:共同通信社)
獨協大学経済学部経営学科 教授の黒川文子氏(撮影:川口絋)(日産 サクラ写真:共同通信社)
世界で急速に進むEVシフト。その中で、日本の自動車メーカーは出遅れが指摘されている。また、消費者の動向においても、日本国内のEV普及は他国に大きく遅れている。長年にわたり自動車業界の経営戦略を研究してきた、獨協大学経済学部経営学科の黒川文子教授にこの状況と、日本が逆転するために取るべき策について聞いた。
日本のEVが出遅れた理由はどこにあるのか
――EV販売において、日本の自動車メーカーの出遅れが指摘されています。どうしてでしょうか。
 黒川 文子/獨協大学 経済学部経営学科教授 経営学博士
黒川 文子/獨協大学 経済学部経営学科教授 経営学博士獨協大学経済学部経営学科教授。日仏経営学会元会長。企業の製品開発や自動車産業の経営戦略を専門としている。主な著書に『自動車産業のESG戦略』(中央経済社)、『21世紀の自動車産業戦略』(税務経理協会)、『製品開発の組織能力』(中央経済社)などがある。
黒川文子氏(以下・敬称略) 日本の自動車メーカーは、EVの取り組みで最初から遅れていたわけではありません。例えば、世界初の量産型EVは日産の「リーフ」でした。
しかしその後、各国がEVの製造販売を後押しする法律を施行し、EV市場が立ち上がってくる中、日本ではそうした法律ができませんでした。結果、日本の自動車メーカーはEVの販売比率を増やす必要がなく、遅れが生じている状況です。
だからといって、世界全体で日本の自動車メーカーの販売戦略に陰りが見えているわけではありません。状況は地域ごとに異なります。まず、EV化を国策として強力に進めている中国市場では、EV普及率が29%と高くなっており、その中で日本メーカーの存在感は薄れています。
一方、欧州ではEV化の目的を燃費規制、つまりCO2排出量の削減に置いており、日本のハイブリッド車がその規制をクリアできる性能を持っていました。日本車のCO2排出量は、2001年と2019年を比較するとマイナス23%と大きな削減に成功しており、ハイブリッド化によって世界でダントツの環境性能を誇っています。そのため、EVでなくても当面は販売を続けることができています。
なお、欧州メーカーのハイブリッドは、マイルドハイブリッドと呼ばれており、CO2削減効果は限定的でした。そのため、法規制をクリアするには、一気にEV化に進むしかなかったのです。
もう1つの巨大市場である米国はどうかというと、米国全土のEV普及率は7%程度に留まっています。主要国の中で最も低い日本で約3%ですから、米国の普及が進んでいるとは言えません。EVのトップメーカーであるテスラは高級車であり、大衆の手には届きません。徐々に安いEVも登場していますが、国土が広く航続距離の長さが求められるため、バッテリー容量の関係でどうしても車両価格が高くなるのです。カリフォルニア州のZEV規制法では、販売台数の一定比率をCO2排出ゼロの無排出車(ZEV)、すなわちEVにしなければ罰金を科すなど、厳しい規制を設けている地域も一部ありますが、米国全体では普及していないと言えます。
現状のシェアを見ると、日本の自動車メーカーはEV化で出遅れたように感じますが、実際は各地域の事情をにらみながら、既存のエンジン車、ハイブリッド車を販売の中心に置いていると捉えています。
とはいえ、世界では日本を含めた123カ国・1地域が2050年までにカーボンニュートラルの実現を宣言しており、長期的に見て市場がEV化に進むことは間違いありません。2031年には、全世界の新車販売でEVがガソリンエンジン車を上回ると予想されており、日本の自動車メーカーも今後EVに注力していく方針を打ち出しています。