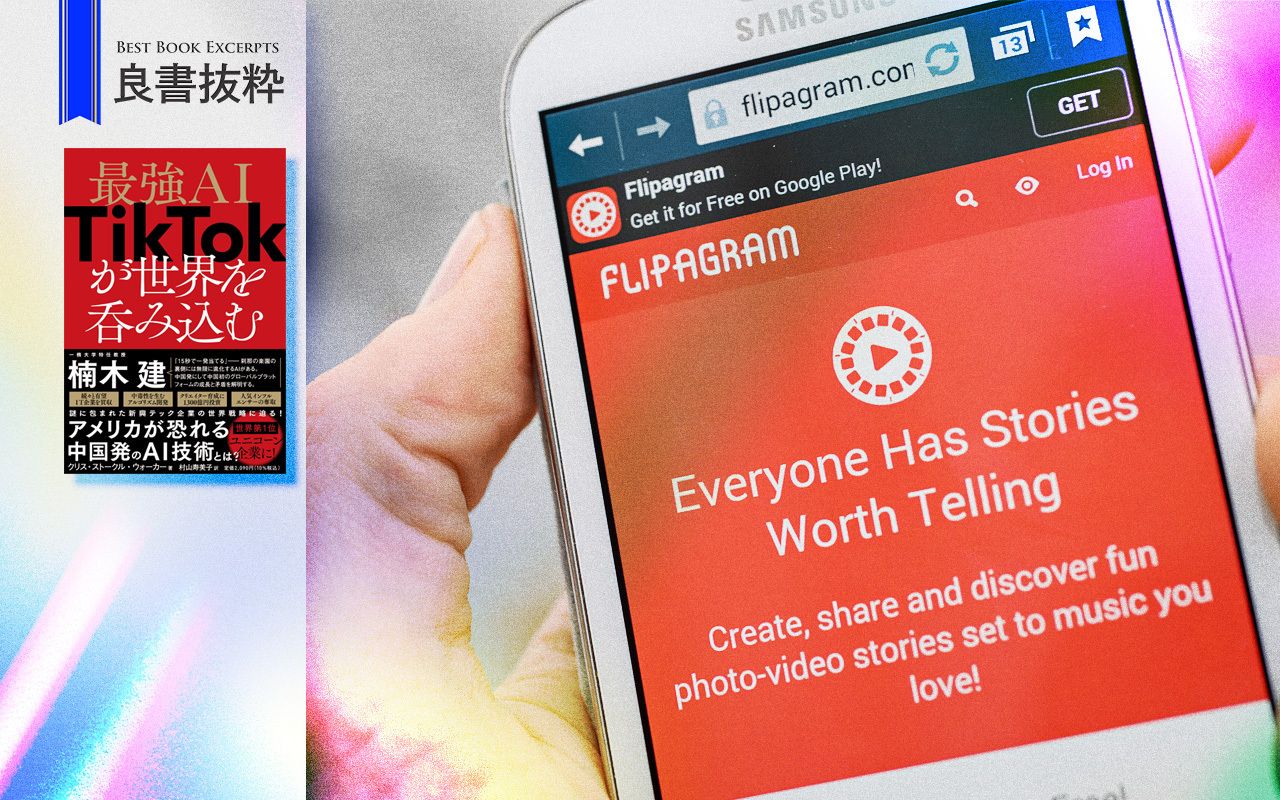 Roman Pyshchyk/Shutterstock.com
Roman Pyshchyk/Shutterstock.com
ショート動画の作成・投稿・シェアが手軽にできるSNS「TikTok」。その人気はユーチューブやインスタグラムといった先行世代のSNSを圧倒し、マーケティングツールとして注目する企業も多い。運営母体のバイトダンスが中国のテック企業であることも耳目を集める理由の1つだ。本連載では、同社の戦略やTikTokの開発、急成長の背景を探った『最強AI TikTokが世界を呑み込む』(クリス・ストークル・ウォーカー著/村山寿美子訳/小学館集英社プロダクション)から、内容の一部を抜粋・再編集。
第2回は、欧米では無名のバイトダンスが台頭する契機となった、AI企業買収劇にスポットを当てる。
<連載ラインアップ>
■第1回 前身アプリ「ミュージカリー」から継承したTikTokの「成長モデル」とは?
■第2回 無名だった中国企業バイトダンスは、なぜ動画アプリ「フリッパグラム」を買収したのか?(本稿)
■第3回 群雄割拠のショート動画市場、中国版TikTok「ドウイン」を生んだ差別化戦略とは?
■第4回 人の注意力持続時間は8秒…それでも見続けてしまうTikTokの巧妙な仕掛けとは?
■第5回 TikTokの「おすすめ動画」はなぜクオリティが高く、ユーザーの関心にマッチするのか?
■第6回 競合SNSのインフルエンサーに100万ドルを提供、TikTokの強気のスカウト戦略とは?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
AI企業を続々と買収する
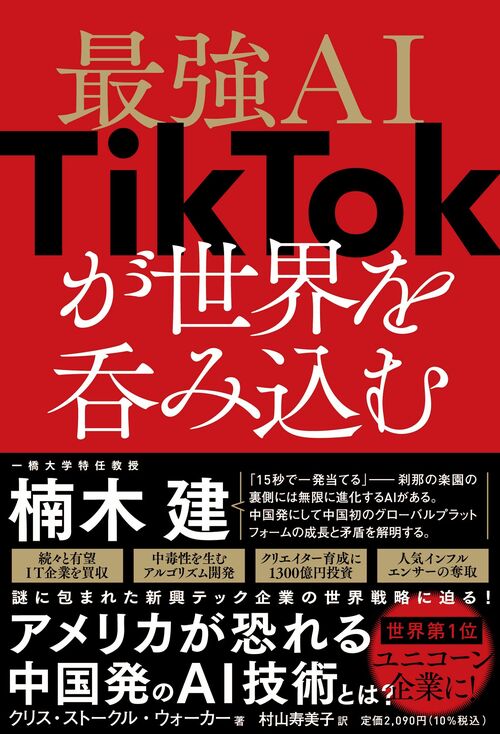 『最強AI TikTokが世界を呑み込む』(小学館集英社プロダクション)
『最強AI TikTokが世界を呑み込む』(小学館集英社プロダクション)
バイトダンスの物語を端的に表すと、発明の才とリソースの巧みな配置、一連のアプリで必要とされるスキルやソフトウェアの獲得と集約される。
ミームやニュースのヘッドライン、あるいは気軽に楽しめるショート動画を提供するのが中国であろうが、ほかの地域であろうが関係ない。だが、ティックトックの台頭について語るなかで、人々が往々にして見落としがちなのは、その成長を勢いづけたのは買収だったということだ。
バイトダンスはその存在期間に少なくとも17の買収を行った。そのうちかなりの数がAI企業の買収だ。
たとえばジュークデック(Jukeddeck)というロンドンに本社を置くコンピューター作曲サービスは、2019年に買収されバイトダンスに組み込まれた。バイトダンスの社内チームと合体し、ティックトックの背後にいる企業のテクノロジーがこうした買収によって拡張され、その結果、世界中で急速な発展を遂げるに至った。
買収の一つに関わっていたのがジョン・ボルトンだ。当時、彼は気持ちをくじかれていた。2020年の夏の朝、私たちはスマホで軽いおしゃべりをしていた。背後で車が音を立てて行き来し、子供が遊んでくれとねだる声が聞こえるなか、この家族思いの男はその事実を素直に認めた。
その3年前の2017年、ボルトンは頭を掻いていた。2014年4月、彼はフリッパグラムという企業に加わった5番目の男となり、この会社の派手な造りのロサンゼルスオフィスで、ショート動画をトップチャートの音楽に載せて記録できるアプリ、ブーム(Boom)を見ていた。
その後3年も経たないうちに、このアプリは3億回――膨大な回数――もダウンロードされ、2014年のほんの数週間のうちに大流行を果たした。同時にそれは世界の180か国でダウンロード回数ナンバーワンのアプリになった。
フリッパグラムは投資家から7000万ドルを集め、2010年代後半に最も世間を賑わせたソーシャルメディアの一つだった。買収を申し出る者が次々と現れたが、そのうちの1社は創設者たちの注目を集めるのに十分な業績を上げていた。社員たちはグーグルやフェイスブックやアップルに社員ごと引き受けてもらえるのではという期待で色めき立った。
当時、ボルトンと同僚たちがフリッパグラムにリンクされた名前を見て、困惑したのも無理はない。「バイトダンス」と言われてもピンとこなかった。グーグルで新しい上司について調べても、事態は変わらなかった。「がっかりしたよ」とボルトンは素直に認めた。「バイトダンスなんて聞いたこともなかったし、中国のテクノロジー企業が中国以外で成功したことなんてあっただろうか?」








