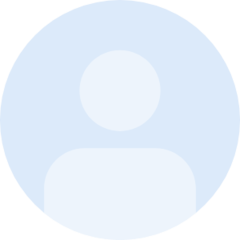写真提供:©Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ 「ZUMA Press」
写真提供:©Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Press Wire/共同通信イメージズ 「ZUMA Press」
デジタイゼーション、デジタライゼーションを経てデジタル化の最終目標となるデジタルトランスフォーメーション(DX)。多くの企業にとって、そこへ到達するためのルート、各プロセスで求められる施策を把握できれば、より戦略的に、そして着実に変革を推し進められるはずだ。
本連載では、『世界のDXはどこまで進んでいるか』(新潮新書)の著者・雨宮寛二氏が、国内の先進企業の事例を中心に、時に海外の事例も交えながら、ビジネスのデジタル化とDXの最前線について解説する。第12回は、世界のIT企業が相次いで参入する「AIエージェント」開発の現在地をお伝えする。
社名を冠した「OpenAI o1」にかける意気込み
ChatGPTを開発して生成AIの火付け役となったオープンAIが、生成AIの最新モデルとして、「OpenAI o1(オーワン)」(以下、o1)を2024年9月に発表した。ChatGPTとは違う名前を付け、あえて社名を冠した背景には、オープンAIの意気込みが感じられる。
o1の基となる訓練データは、ChatGPTの最新版である「ChatGPT-4o(フォーオー)」(以下、4o)と同様、2023年10月までのものとされているが、その最大の特徴は、AIの“考える力”を強化した点にある。
ChatGPTでは回答できなかった数学の問題に加え、クロスワードパズルや暗号などをo1は解くことが可能となった。 この考える力は、AIが問題を解決する際に必要な推論の力を強化学習することで生み出されたもので、そのレベルはすでに人間の博士号並みの能力を獲得するに至っている。
このように、生成AIが進化するスピードはすさまじく、隔世の感があるが、4oであれo1であれ、性能を飛躍的に向上させる一方でコストを下げ、従来はトレードオフの関係にあるとされていた差別化とコストリーダシップが両立できている点にオープンAIの強みが感じられる。
実際、2023年3月に登場した「ChatGPT 4」と後続モデルとをパフォーマンスとコストの両面で比較してみると、2023年11月にリリースされた「ChatGPT 4 Turbo」では、パフォーマンスが2倍に向上する一方で、コストは6分の1に削減されている。
さらに2024年5月の最新モデル4oでは、パフォーマンスが6倍に向上するとともに、コストは12分の1に削減されていることから、パフォーマンスとコスト効率の最適化を高いレベルで達成していることが分かる。