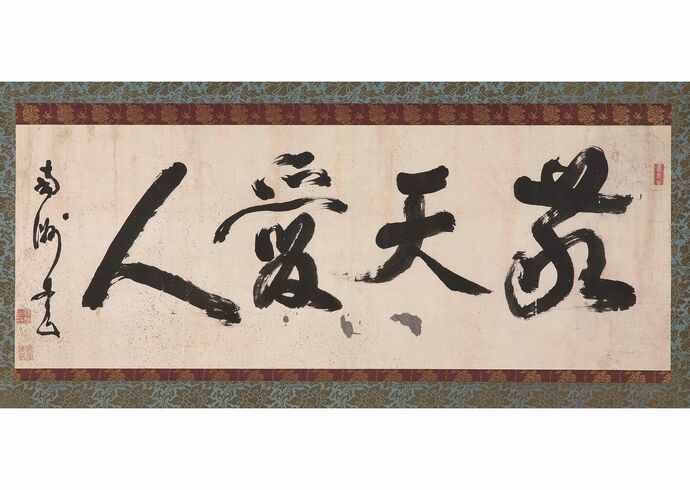元日本取引所グループCEO斉藤惇氏(2014年撮影)
元日本取引所グループCEO斉藤惇氏(2014年撮影)写真提供:共同通信社
「日本再興戦略」の一環として、2015年に適用が始まった「コーポレートガバナンス・コード」。その狙いは企業の持続的な価値向上にあるが、相次ぐ企業不祥事や不正により、「守り」の側面ばかりが議論されてきた。本来の「攻めのガバナンス」を効かせるうえで、日本企業に欠けているものは何か。本連載では、13人の論客による多様な議論を収めた『組織ガバナンスのインテリジェンス ガバナンス立国を目指して』(八田進二編著/同文舘出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。コーポレートガバナンスのあるべき姿を考察する。
第2回は、日本独特の形態である「監査役会設置会社」「指名委員会等設置会社」「監査等委員会設置会社」の特徴と課題を浮き彫りにする。
■「グリード」(強欲)同士のぶつかり合いで企業は強くなる
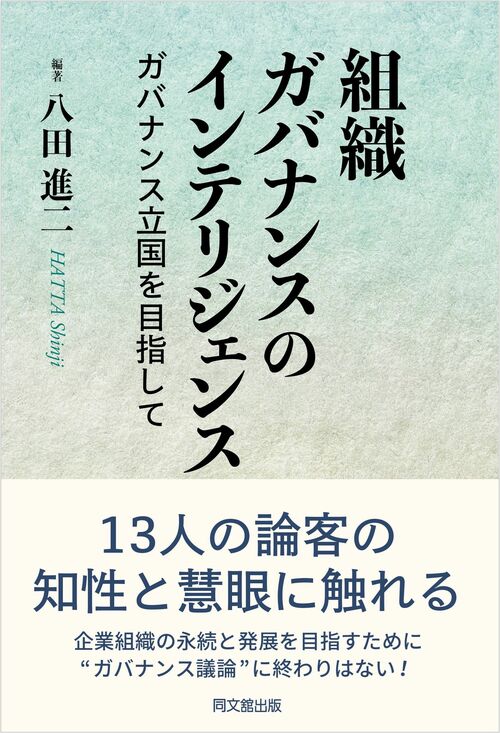 『組織ガバナンスのインテリジェンス 』(同文舘出版)
『組織ガバナンスのインテリジェンス 』(同文舘出版)
斉藤 私は法による縛りよりは、人間の“欲”に訴えたほうが有効なんじゃないかと思っているんですよ。
株主は株価が上がって欲しい、配当もたくさん欲しい。だから、社長はしっかりしてくれ、と。この製品は時代遅れだ、その経営には無駄がある…、“倫理の力”よりも“欲の力”ははるかに強いと思うのです。もっとも、こういうことを言うと、上村先生には品がないって言われてしまうのですが(笑)。
とはいえ、私企業の株式に価値がないと国家は富まない。富まないと税収が減り、雇用も生み出せずに国際競争に負ける。企業が強くなるということは、いわば「国防」と言っていいと私は思っているんです。だから、企業を強くしないといけない。そのためには誰かが見ていないとダメ。
その「誰か」が捜査当局だけでは、実は迫力がない。法を犯しているかどうかではなくて、お金になるかならないか――。そんなグリード(強欲)な目で見られるほうが、はるかに経営者にとってプレッシャーになると思うし、米国のコーポレートガバナンスのあり方はまさに、これなのです。
八田 アメリカ社会は相当グリードですもんね。