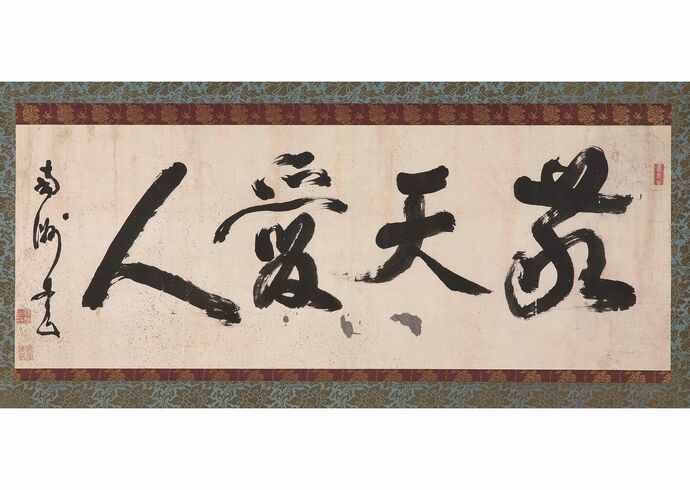元日本取引所グループCEO斉藤惇氏(2013年撮影)
元日本取引所グループCEO斉藤惇氏(2013年撮影)写真提供:共同通信社
「日本再興戦略」の一環として、2015年に適用が始まった「コーポレートガバナンス・コード」。その狙いは企業の持続的な価値向上にあるが、相次ぐ企業不祥事や不正により、「守り」の側面ばかりが議論されてきた。本来の「攻めのガバナンス」を効かせるうえで、日本企業に欠けているものは何か。本連載では、13人の論客による多様な議論を収めた『組織ガバナンスのインテリジェンス ガバナンス立国を目指して』(八田進二編著/同文舘出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。コーポレートガバナンスのあるべき姿を考察する。
第1回は、元日本取引所グループCEO斉藤惇氏が、日本における「コーポレートガバナンス・コード」導入に至る経緯を振り返る。
■ 企業価値を「キャッシュフロー」で見られない日本企業
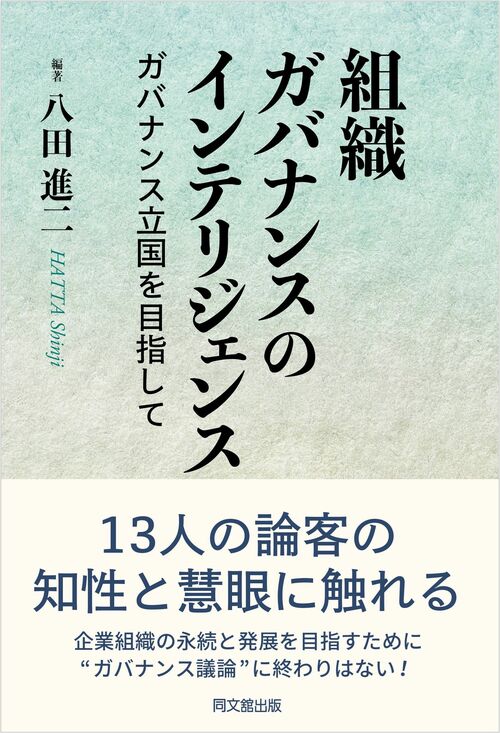 『組織ガバナンスのインテリジェンス 』(同文舘出版)
『組織ガバナンスのインテリジェンス 』(同文舘出版)
斉藤 2002年に住友ライフ・インベストメントを辞めて、家で庭いじりをしながらプラプラとしていたら、旧大蔵省(現財務省)から金融庁に転じ、当時、産業再生機構設立準備室次長を務めていた小手川大助さん(元IMF=国際通貨基金理事)が「機構の社長をやらないか?」と言って来たんです。誰も引き受け手がいなかったようですね。
八田 それでも社長を引き受けられたわけですが、カネボウ、ダイエーといった大型案件も手掛けられた。大変なご苦労をされたでしょう?
斉藤 産業再生機構で一緒に仕事をした仲間たちは非常に優秀で、そして、「国を立て直さなければ」という使命感に燃えていた。ただ、彼ら彼女らとは価値観を共有できましたが、再生対象になった企業や銀行とはなかなか嚙み合わなくて苦労しました。
まず「エンタープライズバリュー」(企業価値、EV)という言葉が通じない。EVについては、ダイエー創業者の中内功さんも、とうとう最後まで理解してくださらなかったですね(笑)。
私は野村アメリカ時代に不動産の証券化も手掛けましたので、バリュエーションをキャッシュフローで見るのは常識だと思っていました。でも、これが再生対象企業には通じない。不動産に投下した金額でモノを言うのです。銀行も土地を担保にカネを貸す。近隣の土地の売買事例がいくらだからこの金額だとか、路線価の2.5倍だからその金額だとか…。
その不動産が稼ぎ出すキャッシュフローで価値が決まるという発想がまったくない。産業再生機構の仕事は不良債権の処理だから、銀行がどういうバリュエーションでカネを貸したのか検証してみると、みな、類似比較なんです。100億円かけて作った建物でも、収益を生まなかったらタダのコンクリートの塊なんですけどね。