 写真提供:NurPhoto/共同通信イメージズ
写真提供:NurPhoto/共同通信イメージズRokas Tenys/Shutterstock.com
イノベーション創出の重要性が叫ばれて久しいが、言葉が独り歩きしている感も否めない。イノベーションの本質とは何なのか。本連載では、『イノベーション全史』(木谷哲夫著/BOW&PARTNERS発行)の一部を抜粋、再編集。京都大学でアントレプレナーシップ教育に当たる木谷哲夫氏が、前史に当たる18世紀、「超」イノベーションが社会を大きく変容させた19世紀後半からの100年、その後の停滞、AIやIoTが劇的な進化を遂げた現在までを振り返り、今後を展望、社会、科学技術、ビジネスの変遷をひもときながらイノベーションの全容に迫る。
第1回は、イノベーションの概念を再確認し、その本質を明らかにする。
<連載ラインアップ>
■第1回 なぜグーグルやヤフーは成功し、インフォシークやエキサイトは敗れ去ったのか?(本稿)
■第2回 日本経済低迷の背景にある「資本投入量の減少」は、なぜ起きたのか?
■第3回 ハーバード大学はなぜ、知財ライセンスをスタートアップに与えるのか?
■第4回 インテル、アップル、TSMC・・・勝ち組に共通する「たった一人の天才」の破壊力とは?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
イノベーションは科学技術と何が違うのか
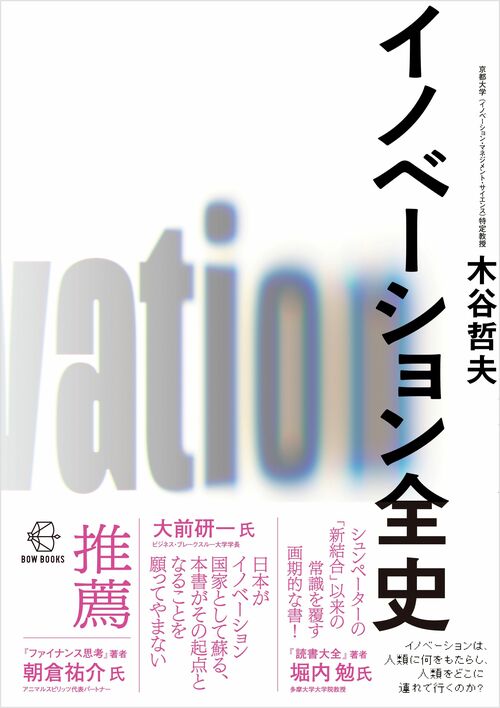 『イノベーション全史』(BOW BOOKS)
『イノベーション全史』(BOW BOOKS)
日本でも実は、イノベーションという言葉が使われるようになったのは、ごく最近のことです。
技術革新、科学技術、新技術などと称されていたものが、ごく最近、イノベーションというように言い換えられるようになりました。
たとえば我が国の「科学技術基本法」が「科学技術・イノベーション基本法」に変更されたのは、ごく最近です(令和3年4月施行)。
この法律ではこれまで科学技術という言葉だけだったのが、科学技術とイノベーションの2種類の言葉を両方並べて書くことで、イノベーションは科学技術とは異なるものである、という認識の変化を示しています。
それでは「イノベーション」と「科学技術」の違いは何でしょうか?
イノベーションと技術革新がどう異なるかについては、さまざまな人がそれぞれの言葉で説明してきました。
「アイデアは実験室で確認されたときに誕生するが、意味ある規模で複製できるほどにコストが下がった段階で初めてイノベーションとなる」
「イノベーションとは何か新しいものを創造する以上のことを意味している。イノベーションとは顧客に付加価値をもたらす新製品による便益の創出を含んだ概念である」
という具合です。
共通しているのは、イノベーションには「普及」の側面があるということが、科学技術と異なっているということです。科学的な発見や新技術の発明だけではイノベーションになりません。普及し世の中に対するインパクトがあること、人々の生活を変えること、経済的な価値を生み出すことで、初めてイノベーションとなるのです。
イノベーションは科学技術と異なり「新しさ」「発見」だけではなく、世の中に普及することによる「経済的価値」の実現が重要だということです。
つまり、「科学技術・イノベーション基本法」という新しい名称により、国がこの法律で推進したいのは、科学的発見や新技術の研究だけではなく、それを世の中に普及し経済的な結果をもたらすことである、ということが明示されたわけです。
以上に書いたことを定式化すると、
イノベーション=新しさ×経済的価値
ということになります。
そして、さらに一歩進めると、実は「新しさ」は何も自分で発見、発明したものである必要もありません。このため、実際には次のように定式化できます。
イノベーション=エミュレーション(模倣)×ディフュージョン(普及)
アメリカにおけるイノベーションの黄金時代には、もともとはヨーロッパ発の発明や発見をエミュレーション(模倣)し、それを大量生産でディフュージョン(普及)させるということが、繰り返し大規模な形で起こりました。








