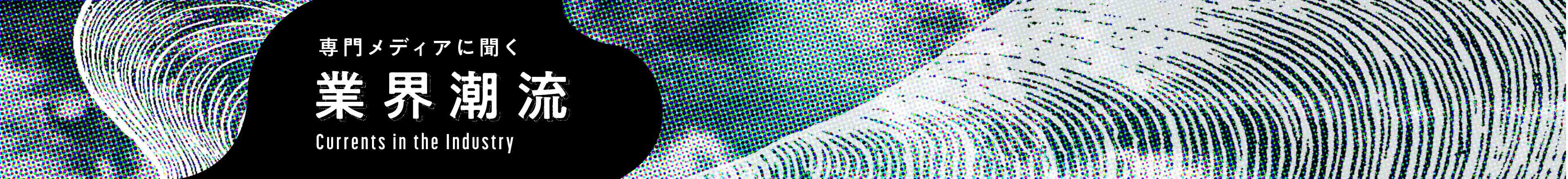tonton/Shutterstock.com
tonton/Shutterstock.com
2016年の電力自由化、2017年のガス自由化によって、地域独占色の強かったそれぞれの業界に、異業種からの参入が加速した。同時に、電力会社はガス事業に、ガス会社は電力事業に参入するなど、エネルギー業界は大きな転換点を迎えている。
クリーンエネルギーへの関心が高まる中、今後ガス業界が目指す方向とは? ガスエネルギー新聞常務取締役編集長の大坪信剛氏に話を聞いた。
災害に強いガスの熱電供給で自治体との連携を強める
――ガスは電気と並び、国民にエネルギーを供給する二大業界です。最近はクリーンエネルギーへの関心が高まっていますが、業界としてどのような動きをしているのでしょうか。
 【ガスエネルギー新聞】
【ガスエネルギー新聞】都市ガス会社の今を報道する業界唯一の新聞。天然ガス、LNG、燃料電池などガス業界の技術や製品情報、企業ニュースの他、周辺業界や行政の動きなども幅広く報道する。2023年7月から新メディア「ガスエネWeb」を公開中。
拡大画像表示
大坪信剛氏(以下・敬称略) 今年4月に日本ガス協会会長に就任した内田高史東京ガス会長は、ガス業界の現状を「明治期にガス灯がともった創業期」と「(石炭ガスから)LNG(液化天然ガス)への転換」に続く「第3の創業期」と表現しています。
2020年10月に政府が打ち出した「カーボンニュートラル」宣言を受け、脱炭素・低炭素をどう進めるかが、ガス業界にとって喫緊の課題となっています。
この件に関連して印象的だったのは、政府の方針を受けて「ゼロカーボンシティ」宣言を出した地方自治体の多くが、相談相手として都市ガス会社を選ぶ事例が増えていることです。
――なぜ都市ガス会社が選ばれたのでしょうか。
大坪 電力会社は東京電力、関西電力、東北電力など、大手と呼ばれる10社で全国をカバーしているのですが、都市ガス会社は全国に190社以上あり、地元自治体と身近な関係を築いてきました。そのため、電力会社に比べて相談する際に敷居が低いという印象があるのだと思います。エネルギーの安定供給と脱炭素の両立のため、自治体が公営の体育館や駐車場に太陽光パネルを設置したいという時、地元のガス会社と連携するケースが多いという話を聞きます。
また、防災拠点の電力供給に必要な太陽光パネルや蓄電池、あるいは停電時に備えたガスによる熱電供給システムの提供などに、都市ガス各社が深く関わっています。
実は、これには理由があります。2019年9月に房総半島を襲った台風15号では、千葉県内で最大64万戸余りが停電しましたが、都市ガスによる発電・給湯システムを備えていた地域だけが停電を免れ、温水シャワーを提供できたという事実がありました。
2018年9月に北海道胆振東部を襲った最大震度7の大地震では、日本で初めて、エリア全域に及ぶ大規模停電である「ブラックアウト」が起きました。ここでも、都市ガスによる熱電供給システムを有していた施設には、煌々(こうこう)と明かりがつき、温水が利用できました。
これらの経験から、「都市ガスは災害に強い」という評価が広まり、自治体との連携が一段と強まったと考えられます。