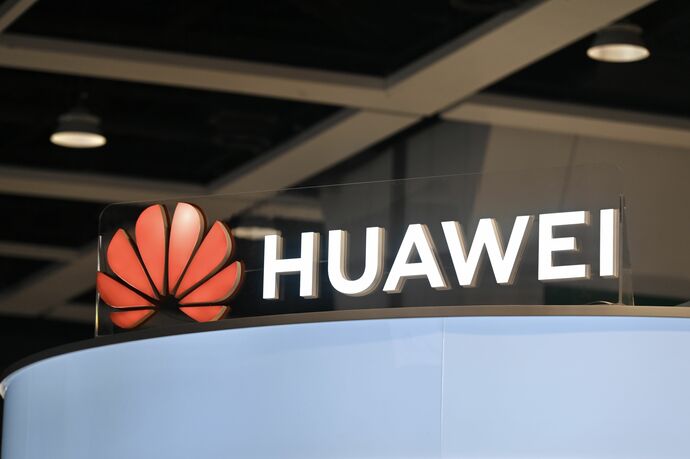デロイト トーマツ コンサルティング チーフ・ストラテジー・アンド・イノベーション・オフィサー、テクノロジー・メディア・通信インダストリーアジアパシフィックリーダーの首藤佑樹氏(撮影:宮崎訓幸)
デロイト トーマツ コンサルティング チーフ・ストラテジー・アンド・イノベーション・オフィサー、テクノロジー・メディア・通信インダストリーアジアパシフィックリーダーの首藤佑樹氏(撮影:宮崎訓幸)
複雑化する企業の課題、AIをはじめ日々進化するテクノロジーのスピードに、日本企業の対応は後れが目立つ。変革を支援するDXパートナーも変わらなければいけない。デロイト トーマツ コンサルティングの首藤佑樹氏は、自社のビジネスモデルを、AIを軸にしたものへと大きくシフトさせ、コンサルタントの能力を生かすことで企業の成長をサポートすると語る。同社の取り組みを聞いた。
全ての経営者はテクノロジーへの理解が必要
――日本企業のDXは後れているという指摘があります。どう感じていますか。
 首藤 佑樹/デロイト トーマツ コンサルティング チーフ・ストラテジー・アンド・イノベーション・オフィサー、テクノロジー・メディア・通信インダストリーアジアパシフィックリーダー
首藤 佑樹/デロイト トーマツ コンサルティング チーフ・ストラテジー・アンド・イノベーション・オフィサー、テクノロジー・メディア・通信インダストリーアジアパシフィックリーダーメディア、半導体・電子部品、SI、ソフトウエア、総合電機などの業界を幅広く担当し、事業戦略策定、組織改革、DX支援など実績豊富。2014年から4年間米国赴任し、米国から日本企業の支援を行った。
首藤佑樹氏(以下敬称略) DXの概念は非常に広く、顧客接点の改善もあれば、AIやRPAを活用して社内プロセスを自動化する取り組み、データ基盤の整備やクラウドシフトなど、さまざまです。また、取り組みの規模も、ツールを導入して小規模な生産性の改善をするものから、データ基盤を作って全社のデータを収集し、経営の意思決定に活用する大規模な改革までと多様です。DXの中身は何を狙うかによって異なるため、成否をひとくくりで判断することはできません。
ただ、変革に向けた投資判断のスピードは、総じて米国と比べて遅いと言わざるをえません。私は過去に米国駐在の経験がありますが、米国企業を見ていると、技術に投資してビジネスモデルやサービスを変えていこうという意欲が非常に高いと感じました。それに対して日本企業は、石橋をたたいて渡る慎重さ、様子見を好むカルチャーが顔をのぞかせ、スピードダウンしている印象を強く持ちました。
昨年大きな話題となった生成AIも、米国企業の動きは速く、米国のデロイトが支援するプロジェクトの数は日本と比べて圧倒的に多く、投資額も桁違いに大きくなっています。
さらに、日本の労働人口の減少とリスキリングの後れによるデジタル人材の不足が、DXの進みにブレーキをかけています。この点は海外の同僚と話しても、「なぜそれが国家の課題なのか」と言われて今ひとつ理解してもらえないところがあります。他の国ではまだ深刻な状況とはなっていない高齢化社会とリスキリングの後れが、今の日本企業にとってボトルネックになっていることは確かです。
――DXの投資額が低い理由に、投資対効果を意識しすぎることがあるのでしょうか。
首藤 それはどの国でも同じで、ROI向上に対する要求は強くなっています。ただし、日本は投資の失敗に対する責任追及が強すぎるという問題があります。DXは新しい技術を使う挑戦で、どれだけ入念に計画しても、正直やってみないとわからない部分があります。そのため、やり始めてうまくいかなければピボットして修正を繰り返すことが必要なのですが、日本企業は失敗に対する受容性が低く、失敗後の再挑戦を許さない傾向があります。
もう1点、経営者のテクノロジーに対する理解が乏しいことが原因で、DXがうまくいかないという問題があります。技術への理解が足りないため、目に見える結果だけを追いかけてしまい、「効果がない」と決めつけてプロジェクトを中止する企業を何度も見てきました。
ERP(統合基幹業務システム)の導入を例にすると、日本企業では業務プロセスを支える基幹システムとして見ているケースがほとんどです。そのため、ERPを確実に導入することが目的化してしまいます。しかし海外の企業は、ERPによって整流化されたデータを使って、ビジネスにどういう付加価値を生み出すか、ということを考えています。同様に生成AIについても、単なる生産性向上のツールとして見るか、他の技術と組み合わせて新しい価値を生み出そうという目線を持てるかで、結果は大きく変わります。
――経営者が技術部門の出身か、そうでないかによる違いがあるのでしょうか。
首藤 そこは必ずしも関係ありません。どんなキャリアを積んできていても、テクノロジーに触れる機会はあります。例えば製造業ではハードウエアからソフトウエアによる付加価値をどう上げるべきか、またはカスタマーサポートをソフトウエア化して顧客のライフサイクルを支援するサービスを構築するなど、あらゆる部門でテクノロジーへの理解が不可欠な時代です。それを貪欲に取り込んで経営に生かしていく姿勢があれば、理解を深めていくことが可能だと思います。
もちろん、私が長年担当してきたTMT(テクノロジー・メディア・通信)業界では、先端テクノロジーへの理解や、部下が新しい技術にチャレンジする際の受容性も高いと思います。ただ、投資判断の点では、先ほど話した文化的な問題でスピードが落ちる傾向があるのは残念なところです。