 キリンホールディングス デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長の皆巳祐一氏(撮影:宮崎訓幸)
キリンホールディングス デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長の皆巳祐一氏(撮影:宮崎訓幸)
DXの専門部署を立ち上げてから約3年、キリンの施策が実を結んでいる。2021年にはグループ全体のデジタルリテラシーとスキル向上を目的とする社内プログラム「DX道場」を開講。翌2022年には経済産業省から、特に企業価値貢献部分において、注目されるべき取り組みを実施している「DX注目企業2022」に選定された。中でもDX道場の受講者数は好調に推移しており、2021年では白帯(初級)約700人、黒帯(中級)約200人だったのが、2022年は白帯約1200人、黒帯約600人、師範(上級)約50人、そして2023年上期時点で白帯約1500人、黒帯約750人、師範約150人と、開講時に予定していた2024年の受講者目標を既に達成している。
Japan Innovation Reviewでは2022年3月に、キリンがDX道場を立ち上げた狙いについて記事化したが、社内のDXが進んだ秘訣と新たに見えてきた課題について、キリンホールディングスのDX戦略推進室の皆巳祐一室長に話を聞いた。
ビジネスの課題をデジタルで解決する人材を育てる
──2021年にグループ全体のDXリテラシー向上を目的としたレベル別プログラム「DX道場」を立ち上げてから約2年、当初予定よりDX人材育成が好調です。好調の要因は何だと思いますか?
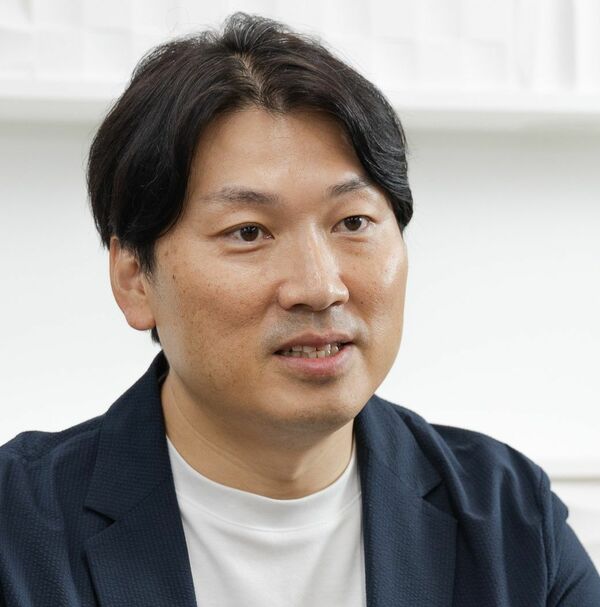 皆巳 祐一/キリンホールディングス デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長
皆巳 祐一/キリンホールディングス デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長食品メーカーにて営業、マーケティングに従事した後、デジタル化の重要性を感じて2017年キリンホールディングスのデジタルマーケティング部へキャリア入社。SNS、オウンドメディア運営を担当後、2020年経営企画部DX戦略推進室の立ち上げメンバーとして参画。2023年より現職。
------
座右の銘:「成功の反対は失敗ではなく、挑戦しないこと」
尊敬するビジネスパーソン:森岡毅氏(株式会社刀 代表取締役CEO)
座右の書:『ストーリーとしての競争戦略―優れた戦略の条件』(楠木建著)
皆巳祐一氏(以下・敬称略) まずDX道場を立ち上げた背景として、キリンでは、DXを進めるうえで「本社だけでではなく、事業・部門も一緒に取り組む」ことを大切にしているということがあります。いくら本社側が意欲的でも、現場の人たちが自主的に取り組もうと思わなければDXは成功しません。従業員のモチベーションに火を付け、一緒にやっていくという姿勢が大切だと考えています。
その狙いが従業員の意識と合致したということなのではないでしょうか。つまり、DX道場に対する関心の高さには、従業員一人一人の危機意識が表れているのだと思います。競合他社の状況やニュースを見て危機感を覚える、業務でデジタル化の重要性を痛感するなど、キリンには日頃から変化に敏感な従業員が数多くいます。最初は「外部セミナーを受講するにはお金も時間もかかるけれど、社内でやっているなら受けてみるか」という腕試し感覚で受講する人が多かったのですが、いざ受けてみると、予想以上にDX道場で求められるレベルは高く、内容も実務に即している。カリキュラムの質やデジタル化の重要性を体感し、より上のレベルを目指すようになった受講者が、DX道場について口コミし、社内にその良さが広まったことも道場に関心が集まるようになった一因ではないかと思います。
──DX道場は、全てがキリン独自のカリキュラムです。講座の内容はどのように決めているのですか。
皆巳 DX道場では、事業の課題解決策をデジタル活用によって考えられる「ビジネスアーキテクト」を育成することが目的です。単に知識を付けるだけではなくキリングループの課題をデジタルで解決できる人材を育てたいので、課題で社内事例を用いるなど、パートナー企業と協議しながら明日からすぐ使えるような実践的な内容にしています。
カリキュラムの見直しは、市況や受講生アンケートを基に2~3年単位で行っていく計画です。デジタルICT技術の進歩や市場環境の変化、社内の育成状況に合わせて、講義内容を随時見直しています。現在は応募者が多いことから講座の開催回数を増やすなど、運営しながら都度見直しを行っています。
──白帯、黒帯、師範という3つのレベルを設定していますが、それぞれどのようなことを学ぶのでしょうか。
皆巳 白帯は初級者対象なので、基本的なところから解説し、デジタルアレルギーを取り除くことを目的にしています。「なぜキリンがDXに取り組む必要があるのか?」などそもそもDXを行う背景や、専門用語の解説が中心です。
黒帯以上ではツールを実際に触ってもらうことを重視しているので、ダッシュボードをはじめとするBI(ビジネスインテリジェンス)ツールやAI・機械学習の活用講座を通じて、ライセンスを受講者に付与することで実際のデータを基に学べるようにしています。白帯・黒帯共に、課題を一定基準までクリアできることが認定条件です。
師範は、事業レベルのDX推進を先導できるような人財の育成を目的に実践的な設計としており、実務における課題を持ち込んで受講される方も多いです。DX企画立案・案件推進コース、データ利活用コース、新規ビジネスコースなど複数ありますが、「散在するデータをTableau(タブロー)で一元化して分析する」「新しいECの立ち上げを構想する」など、受講者の実務に即した内容に約数カ月間かけて取り組みます。コースによっては講師による1on1ミーティングや上司同席での発表会など説明能力が求められるところも特徴で、現場で実践可能なレベルが求められます。








