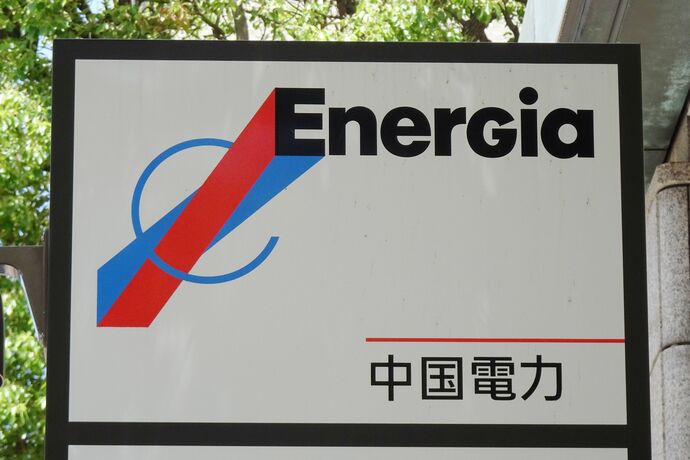日本製鉄株式会社 執行役員 デジタル改革推進部長,情報システム部長の星野毅夫氏(撮影:川口紘)
日本製鉄株式会社 執行役員 デジタル改革推進部長,情報システム部長の星野毅夫氏(撮影:川口紘)
国内最大手の鉄鋼メーカー、日本製鉄。かつて「産業の米」とも呼ばれた鉄鋼業をリードし続ける同社は、1960年代からICT活用に力を入れてきた。それほど早くから取り組んだ理由は、広大な敷地と複雑な生産プロセスを有する製鉄所において、デジタルの導入は「なくてはならないもの」だったからだ。
さらにその積み重ねを活かし、近年は全社的な業務プロセス・生産プロセス改革の一環としてDXを推進している。このDXには、コンセプトとなる2つの柱がある。蓄積された膨大なデータを横断的に結合する「つなげる力」と、データを課題解決や意思決定に活用して競争力を強化する「あやつる力」だ。一体どのように進めているのだろうか。同社のDXをリードする情報システム部長兼任 執行役員の星野毅夫氏に聞いた。
日本製鉄がいち早くIT化を推進してきた理由
――日本製鉄では、60年代からICTを積極的に導入してきたそうですが、何か動機や理由があったのでしょうか。
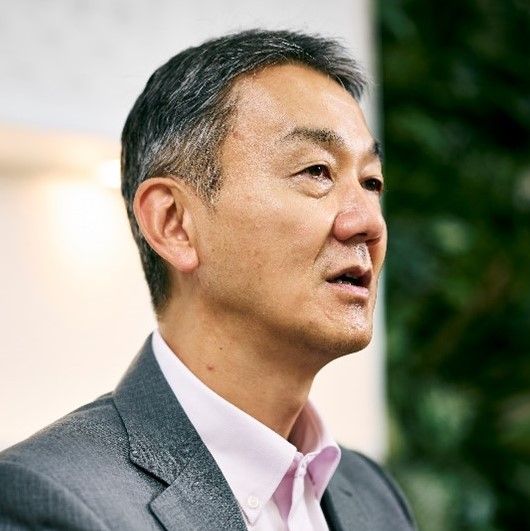 星野 毅夫/日本製鉄 執行役員 デジタル改革推進部長,情報システム部長
星野 毅夫/日本製鉄 執行役員 デジタル改革推進部長,情報システム部長1991年4月新日本製鐵(当時)入社、設備技術センターにて電気制御設備の設計開発に従事。2005年、ローコードでの制御システム開発基盤(ROBOC.OP)を開発。プロセス研究開発マネジメント業務も担当しながら、制御システム設計に従事。2017年から室蘭製鉄所設備部長、2020年よりデジタル改革推進部にて生産プロセス改革に従事。2023年4月より、情報システム部長を兼任し、日本製鉄における戦略的デジタルトランスフォーメーション施策を推し進める。
星野毅夫氏(以下敬称略) ICTを早くから取り入れたのは、必要に迫られてという表現が適切かと思います。なぜなら製鉄所は、人の手だけでは回しきれないほど大規模かつ複雑な製造プロセスを持っているからです。
具体例を挙げると、当社の東日本製鉄所(君津地区)は1228万平方メートルと千代田区より広い面積があります。全長は新宿駅と東京駅を結ぶ距離とほぼ同じで、JR山手線の中に横たわるほどの大きさがあります。
それだけの広大な敷地の中で、鉄鉱石を溶かして固め、粗鋼をつくる「鉄源工程」、粗鋼を高温下で成形する「熱間圧延」、さらに常温下で鋼管、厚板、建材といった製品に成形する「冷間圧延」などの多様な生産プロセスが行われており、製品の種類も薄板だけで約7万種類におよびます。
このように大規模かつ複雑な製造プロセスですから、必然的にデジタルの活用が検討に上がりますし、そもそも現場のデータがないと生産計画も立てられません。そのため、1960年代にIBM製メインフレーム(大型汎用コンピュータ)を使ってコンピューターによる制御で稼働する製鉄所を作り、70年代には君津製鉄所でオンライン・リアルタイム生産管理システムを構築。以降も分散系、WEB系、さらにクラウドと、その時代に合わせたシステムを取り入れながら、一貫して最新のICT技術によるデータ活用に取り組んできました。
――製造現場が広大なうえに、機械の数も膨大な中で、無線IoTセンサなどを整備するのは大変な作業ですね。
星野 早い時期からICTやデータ活用に取り組んできた歴史があるので、新しいテクノロジーのシーズが登場した際には「まず試してみよう」という気概が社内にはあります。これは、当社にかぎらず鉄鋼業界全体に共通しているかもしれません。
私たち本部のシステム部門が「こういう技術があるよ」と声をかけると、「うちの現場で使ってみたい」などと手が挙がり、PoCで導入してみる動きが起きます。それでうまくいったら横展開する、というプロセスを昔から繰り返し積み重ねてきました。