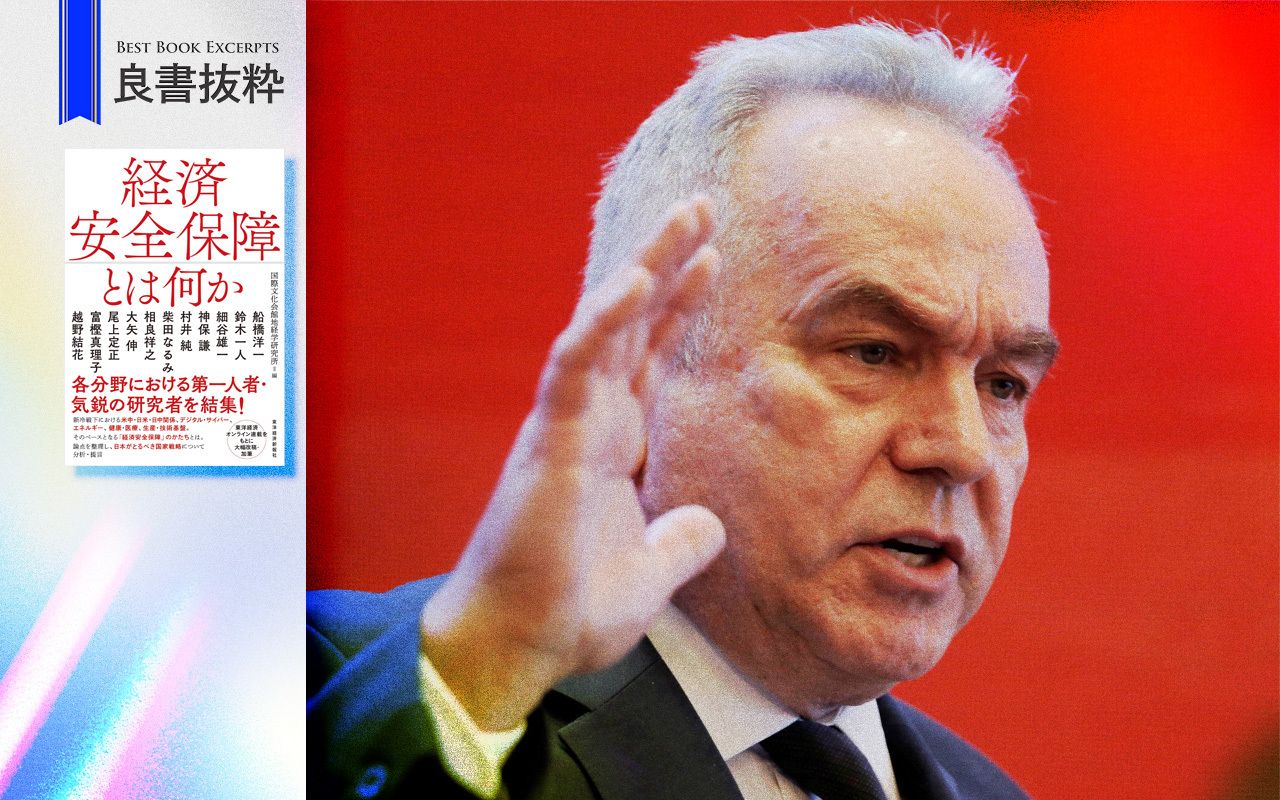 米バイデン政権で2021年、国家安全保障会議(NSC)のインド太平洋調整官に任命されたカート・キャンベル氏
米バイデン政権で2021年、国家安全保障会議(NSC)のインド太平洋調整官に任命されたカート・キャンベル氏写真提供:ロイター/共同通信イメージズ
近年、新聞やニュースでも多く取り上げられるようになった「経済安全保障」。グローバル化する「経済」は、国家の安全保障という文脈にどのように関連するのだろうか。本連載では『経済安全保障とは何か』(国際文化会館地経学研究所編/東洋経済新報社)から、内容の一部を抜粋・再編集。米中・日米・日中関係をはじめ、デジタル・サイバー、エネルギー、健康・医療、生産・技術基盤の領域において、これからの日本はどのような国家戦略をとるべきなのか、各分野の第一人者が分析・提言する。
第3回は、地政学的視点から経済安全保障の現在地を分析。中国との競争姿勢を鮮明にした米国の戦略認識と、その背景にある安全保障上のパワーバランスを考察する。
<連載ラインアップ>
■第1回 日本が経済安全保障戦略で「黒字国」から「赤字国」に転落した3つの構造的理由
■第2回 経済社会秩序を守る「経済安全保障」政策の展開は、なぜ政府にとって困難を伴うのか?
■第3回 「中国は戦略的競争の相手国」米国が対中強硬路線を鮮明にした経済安全保障上の理由とは?(本稿)
■第4回 コロナ禍やウクライナ侵攻で浮き彫りとなった、サイバー空間における経済安全保障の課題とは?
■第5回 国家安全保障の要と言えるエネルギー産業、日本の供給体制はなぜ脆弱なのか
■第6回 英国はなぜ国家間のコロナワクチン争奪戦に勝利し、世界初の接種を実現できたのか
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
戦略的競争としての経済安全保障
 『経済安全保障とは何か』(東洋経済新報社)
『経済安全保障とは何か』(東洋経済新報社)
日米関係において経済安全保障が重視されるようになった背景には、米国の対外政策における戦略的競争(Strategic Competition)の概念が経済分野を射程に入れたことに起因する。
米バイデン政権で国家安全保障会議(NSC)のインド太平洋調整官に任命されたカート・キャンベル(Kurt M.Campbell)は、スタンフォード大学で開催された会議において、米国の対中政策に関して「関与政策と幅広く表現されていた時代は終わった」と宣言し、今後の「主要なパラダイムは競争ということになる」と言及した。
米国の対中政策にはオバマ政権後期からトランプ政権にかけて、構造的とも言える変化が生じている。トランプ政権は2017年12月に発表した「国家安全保障戦略(NSS)」において、中国を「現状打破国家」とみなし、2018年1月に要旨が公表された「国家防衛戦略(NDS)」では、中国が「長期的な戦略的競争」の相手国と位置付けられた。また2018年10月のペンス副大統領の演説は、中国の軍事、経済、政治体制、社会に対する包括的な警戒を先鋭化させた内容となった。
こうした対中政策の包括的な競争路線は、とりわけトランプ政権後期の対中経済政策によって鮮明になっていった。トランプ大統領は中国との貿易に包括的な制裁関税を課し、貿易戦争は熾烈化していった。
また、中国企業を主たる念頭に置く対内投資規制と審査の強化、先端技術の輸出規制、政府調達分野における中国製品の規制など、中国との経済的取引を制限する措置を矢継ぎ早に展開していった。そして、さらに人権分野でも香港における民主化デモ弾圧や、新疆ウイグル自治区問題をめぐり、米政府は中国に対する批判と圧力を強めていった。
この時期に注目すべきは、米国内においてトランプ政権及び共和党保守派のみならず、民主党議員やシンクタンク、米産業界などが軒並み中国に対する姿勢を硬化させたことである。2018年の中間選挙では米下院で民主党が地滑り的勝利を収め、主要な政治課題で共和党政権との対立を深めていた。
しかしこと中国関連法案に関しては、台湾旅行法、アジア再保証推進法、台北法、香港人権・民主主義法、ウイグル人権法、外国企業説明責任法、香港自治法などの数多くの法案で、ほぼ全会一致で可決している。
これらから得られる重要な示唆は、米国の対中政策で「戦略的競争」を追求する路線は超党派的に共有されており、また「関与とヘッジ」を揺れ動く振り子構造としての対中政策の理解は、ほぼその基盤を失ったということである。
バイデン民主党政権が発足したのちにも、トランプ前政権が追求した対中強硬路線が継承され、そしてさらに競争が激化しようとしていることはその証左である。それが、冒頭のキャンベル発言における「関与政策と幅広く表現されていた時代は終わった」という認識に結びつく。








