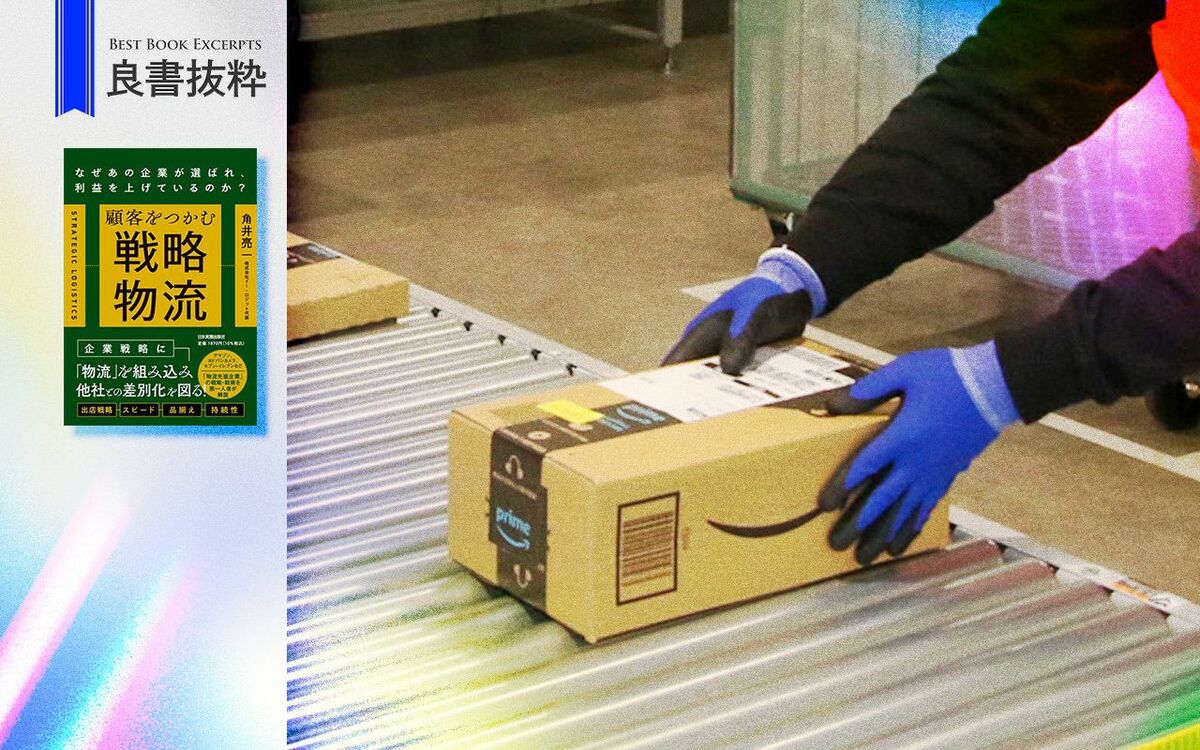 写真提供:山陽新聞/共同通信イメージズ
写真提供:山陽新聞/共同通信イメージズ
EC市場の拡大によって物流の重要性が増す中、物流をコストと見なす企業は多い。一方で、物流を「利益を生む機能・部門」として企業戦略に取り込み、成長の足掛かりにしている企業が存在する。物流をプロフィットセンター化するには、どんな戦略が考えられるのか。本連載では、『顧客をつかむ戦略物流 なぜあの企業が選ばれ、利益を上げているのか?』(角井亮一著/日本実業出版社)から、内容の一部を抜粋、再編集。物流によって競合との差別化に成功している企業4社の戦略と取り組みを紹介する。
第4回は、配送スピードや利便性の向上を狙ったアマゾンジャパンの物流ネットワークについて解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 業界1位の座を支えるドミナント戦略、セブン-イレブン独自の「高密度集中出店方式」とは?
■第2回 セブン-イレブンはなぜ、全国展開や大都市圏への出店を急がなかったのか?
■第3回 西海岸の地下倉庫で創業したアマゾンは、いかに全米物流ネットワークを築いたか?
■第4回 コロナ禍で利用率が急増、アマゾンの「宅配部隊」が躍進した背景とは?(本稿)
■第5回 全品配送料無料の「ヨドバシエクストリーム」は、なぜ最短2時間半で配達できるのか?
■第6回 新着は毎日2600点超、年間6000万点を出荷するZOZOの物流拡張計画とは?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
段階的に機能に差をつけて物流拠点を展開
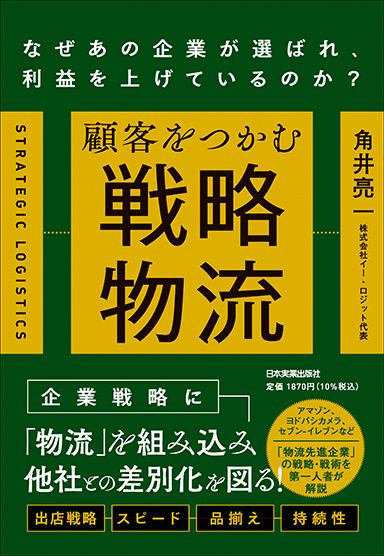 『顧客をつかむ戦略物流』(日本実業出版社)
『顧客をつかむ戦略物流』(日本実業出版社)
日本の国土は、全米の25分の1のスケールしかありませんが、日本のアマゾンでも米国同様、段階的に機能に差をつけたFC、DS、ネットスーパーの拠点展開を図っています。
アマゾンジャパンが、この3年ほどの間に拠点数を一気に増やしているのがDSです。2023年には11か所に新設され、現在は50か所以上で展開されています。
このDSではどのような作業が行なわれているのか。
2022年8月に、沖縄県内初のDSが設置されました。公開された同所での作業の流れを見ていくと、次のような流れになっています。
県外の物流拠点から届いた荷物の荷下ろしから始まり、荷物の登録、仕分け、ドライバーによる荷積み作業が行なわれます。
仕分けでは商品の配送地域ごとに分ける作業が行なわれる際に、作業スタッフは指先に小型のスキャナーをつけており、スキャナーで商品のバーコードを読み込むと、対象商品の入る箱が点灯するようになっています。
また、ドライバーによる荷積み作業は、スマートフォンのアプリによる指示に沿って行ないます。以前は、指定された棚に置かれた商品をドライバーが1個ずつ積み込んでいましたが、最新のDSでは専用の配送バッグに商品が入った状態で置かれるようになり、ドライバーはそのバッグごとトラックに積み込めばすぐに配送に出かけられます。この仕組みは2019年の後半ごろ、米国で始まったとされていますが、アマゾンの場合、こうした効率化のための工夫は、日々、随所で進められています。
沖縄県の場合、FCを設けても採算には乗らないといわれますが、このDSの機能をうまく活用すると、都内FCからの飛行機便経由により、沖縄県内でもプライム会員向けの当日配送を実現できるのではないかと考えられます。








