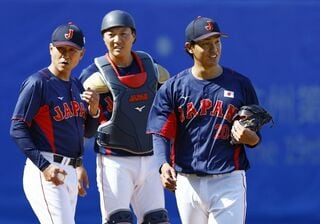◎六大学野球の舞台である神宮球場(写真:望月仁/アフロ)
◎六大学野球の舞台である神宮球場(写真:望月仁/アフロ)東大野球部のエース松岡由機の野球人生を綴るノンフィクションの最終話。4年生になった松岡は、東大野球部という独特なチームの中で、どんな思いを持って神宮球場のマウンドに上がっていたのか。そして松岡にとって、また、東大野球部にとっての「1勝」の意味とは?(矢崎 良一:フリージャーナリスト)
【第1話】六大学野球でも名を馳せたMAX146kmの東大エースが野球をやめる理由
【第2話】なぜ東大野球部は強くなっているのか、考えながら量をこなすという思考
【第3話】体格に恵まれていない松岡は、なぜ150km近い球速を出せるようになったのか?
ちょうど1年前に本格的にスタートした新チーム。松岡由機は自ら望み副将というポジションに就く。
その前年、一期上のチームは選手個々の能力が高く、戦力的な期待値は高かったが、チームバランスを欠き、本来の力を発揮できずに終わった一面がある。4年生の部員たちに方向性の相違があり、チームはスタートから最後までギクシャクした雰囲気が続いていた。
強いリーダーシップを持つ主将の松岡泰希(現・明治安田生命)が、勝つために妥協のないスタンスでチームを引っ張ろうとしたが、それは野球強豪校の出身がほとんどいない東大野球部では馴染めない厳しさでもあった。
それに反発する部員たちも多く、当初は仲介役としての働きを期待されて副将になった西山慧が、いつの間にか松岡主将と対立する立ち位置になり、存在感を増していた。
チームを引き上げようとした松岡主将と、チームのバランスを取ろうとした西山副将。「僕は西山さんを支持していました」と松岡は言う。
「普段から距離が近かったというのもあるし、投手陣は投手陣で練習するので、西山さんの話をずっと聞いていました。チームのために末端にまで目を配り動かれている姿を見てすごいなと思っていましたし、西山さんの考えに納得させられる部分がすごくあったので、当時は西山さんの考えに賛同していましたね」
だから「西山さんのような働きが自分にもできたらいいな」という思いで副将に立候補した。
「でも僕らの学年が一番上になって、一期上のチームのことを振り返ったら、(松岡)泰希さん、西山さん、どちらの言っていることにも正しさはあるんだなと思いました」
私も当時の東大を何度も取材し、彼らの考えを細かく聞いてきた。ひよるわけではないが、どちらの言うことも正論だと感じていた。
根っこにあるのは、東大というチームの持つ特殊性。いわゆる強豪校であれば、選手たちには「優勝」「甲子園」「日本一」といった共通の目的があり、それはノルマでもある。だからプロセスであれこれ軋轢があっても、最後はその目的の下で歩調を合わせることができる。
だが、東大の選手たちの多くは、そういうメンタリティで野球をしてきていない。松岡もこう話している。
「そういう対立は常に存在していて、それがたまたま主張の強い2人がいたことで顕在化したというだけで、東大ってもともとそういう文化なんです。それをどうやって折衷していくのがいいのか、毎年頭を悩ますわけで」
そういう意味では、松岡も東大ではマイノリティーだった。西山のようになろうと思ってそのポジションに就いたが、いざリーグ戦が始まって、「勝ちたい」という感情が前面に出て来た時に、前年の松岡主将のようになっている自分に気付いた。