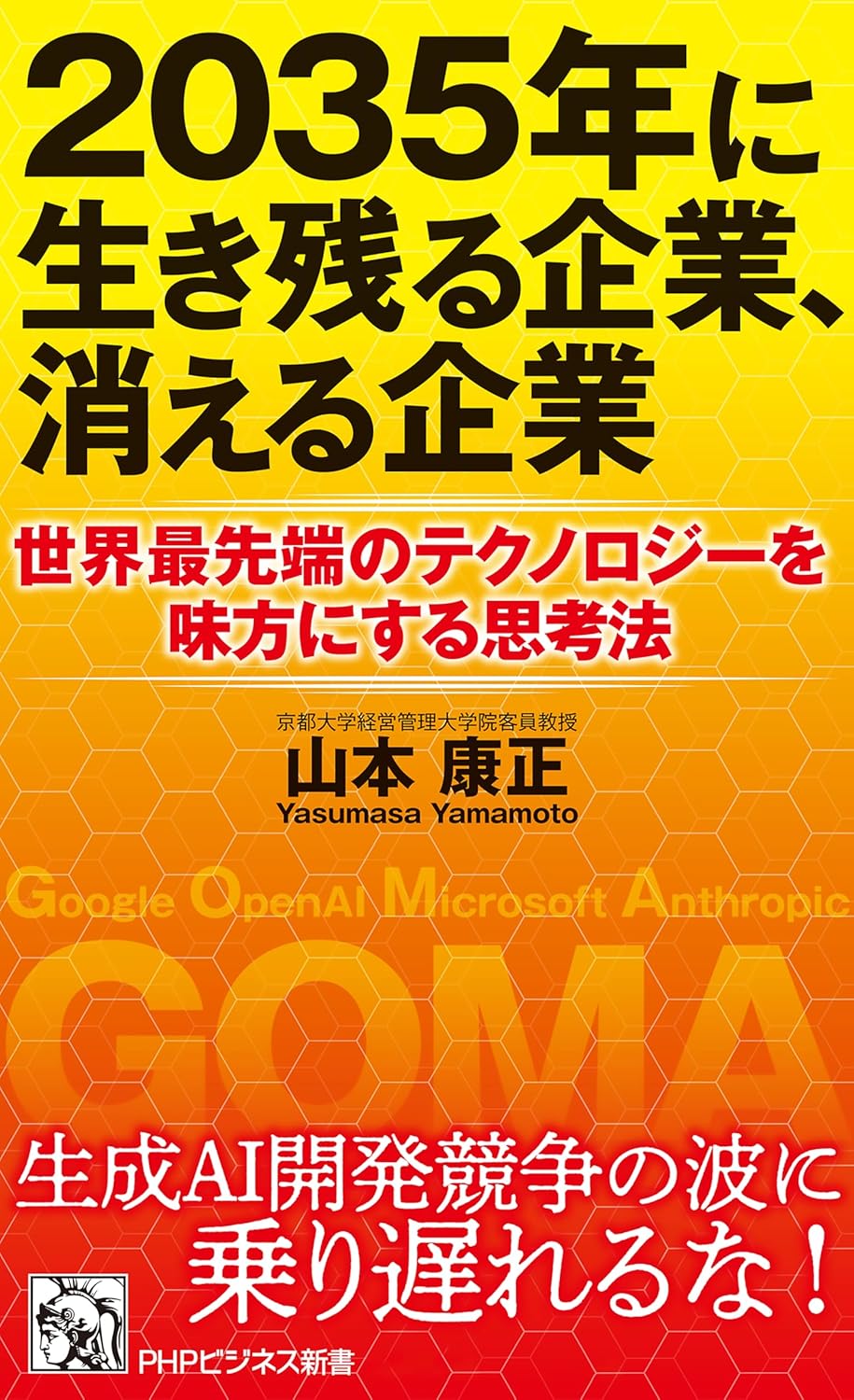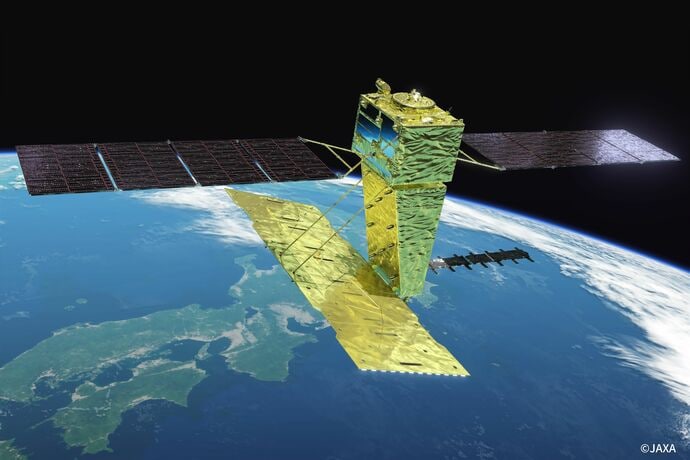ベンチャー投資家、京都大学経営管理大学院客員教授 山本康正氏(撮影:小宮和実)
ベンチャー投資家、京都大学経営管理大学院客員教授 山本康正氏(撮影:小宮和実)
近年、さまざま産業で生成AIが新たなイノベーションを生み出している。変わりゆく世界を前に日本企業のリーダーは何を学び、どのような視点を持ち、次なる戦略をどう講じるべきなのか。前編に続き、2024年7月に『2035年に生き残る企業、消える企業 世界最先端のテクノロジーを味方にする思考法』(PHPビジネス新書)を出版した京都大学経営大学院客員教授の山本康正氏に、生成AIの活用において国内外で注目すべき分野、そこから日本企業の経営者が学ぶべきことを聞いた。(後編/全2回)
■【前編】成長続く生成AI新勢力図「GOMA」、中でも際立つマイクロソフトの「抜け目ない戦略」
■【後編】生成AI時代を勝ち抜くヒント…最先端技術を使わない任天堂「ファミコン」が世界的にヒットしたシンプルな理由(今回)
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
生成AIのユースケースは「一つ一つ試すしかない」
――前編では、生成AI開発をリードする各社の動向について聞きました。著書『2035年に生き残る企業、消える企業』では、さまざまな産業での生成AIの活用例を紹介していますが、特に注目しているのはどのような分野でしょうか。
 山本 康正/ベンチャー投資家、京都大学経営管理大学院客員教授
山本 康正/ベンチャー投資家、京都大学経営管理大学院客員教授東京大学で修士号取得後、NYの金融機関に就職。ハーバード大学大学院で理学修士号を取得し、グーグルに入社。フィンテックやAI(人工知能)などで日本企業のデジタル活用を推進し、テクノロジーの知見を身につける。日米のリーダー間にネットワークを構築するプログラム「US-Japan Leadership Program」諮問機関委員。京都大学経営管理大学院客員教授。日本経済新聞電子版でコラムを連載。著書に、『シリコンバレーのVCは何を見ているのか』(東洋経済新報社)、『世界最高峰の研究者たちが予測する未来』(SBクリエイティブ)、『アフターChatGPT』(PHP研究所)、『テックジャイアントと地政学』(日本経済新聞出版)など。
山本康正氏(以下敬称略) 1つは「ヒト型ロボット」です。
ロボットの実用性に向けた最も大きなハードルは「頭脳」です。関節の動きといった身体能力の開発はある程度進んできましたが、「何が起きたときに、どのように動くのか」という状況判断をする頭脳部分の開発が非常に難しいのです。
しかし、生成AIの進化に伴い頭脳の部分が格段に進化し、人間のような状況判断の実現が近づいています。
2024年に行われた米グーグルの年次開発者会議「Google I/O(アイオー)」では、カメラを搭載したヒト型ロボットがオフィス空間の状況を把握し、判断しながら歩き回る様子が発表されました。オフィスに植木の鉢があれば「植木があるから、水をやらないといけない」とロボット自身が判断するようになるのです。
こうしたロボットが我々の日常にどこまで浸透するかは未知数です。ビジネスとして成立するためには利用者自身が「金銭を支払った分だけの便益」を感じなければなりませんし、需要と供給のバランスが取れるかどうか分かりません。しかし、人々の働き方や生活様式が変わりゆく今、突如変化が生じてもおかしくありません。
テクノロジーの進化を振り返ると、インターネットが出てきたころの用途は「メール」「チャット」といったコミュニケーションが主なものでした。その後にはeコマースの利便性が人々に受け入れられ、スマートフォンの普及や社会環境の変化も相まって爆発的に広がりました。しかし、当初から「インターネットをeコマースに使おう」と考えていた人は極めて少数でしょう。つまり、ユースケースはどこにあるか分からない、ということです。
ロボットに関しても同じ構図になると考えています。どのユースケースが世の中のニーズとマッチするのか、まだ確定していません。だからこそ、一つ一つ試し続けて確認していくしかありません。