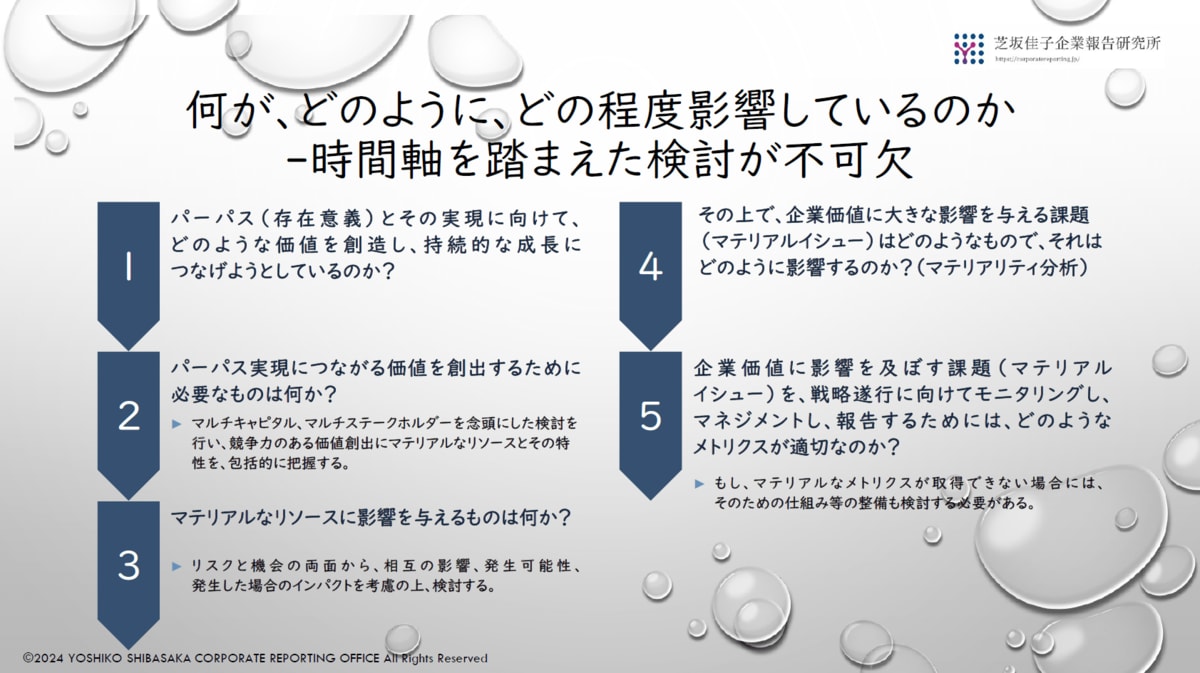芝坂佳子企業報告研究所代表の芝坂佳子氏 (撮影:宮崎訓幸)
芝坂佳子企業報告研究所代表の芝坂佳子氏 (撮影:宮崎訓幸)
企業価値の源泉が有形資産から無形資産にシフトし、見えざる財についての情報開示の要請が強まっている。その中で、企業は自社の価値や独自性を的確に捉え、目指す姿を描き、それらを世界のステークホルダーに伝えるために、今何をすべきか。中長期的な企業価値の向上をテーマに、企業報告に関わる調査研究や提言を25年以上行ってきた芝坂佳子企業報告研究所代表の芝坂佳子氏に聞いた。
日本企業の情報開示についての課題を指摘した前編に続き、後編となる今回は、ESG情報開示のベースとなるマテリアリティの捉え方、検討のためのマテリアリティ分析、その結果としてのマテリアルな課題の見極めと内容の説明、これらを用いたステークホルダーとの対話を通じたサステナビリティ経営の実現について解説する。
未来志向で価値創造を考えることが、魅力的なパーパスにつながる
――企業がサステナビリティ経営に取り組み、適切な情報開示をしていくためには何から着手すべきでしょうか。
 芝坂 佳子/芝坂佳子企業報告研究所代表
芝坂 佳子/芝坂佳子企業報告研究所代表東京エレクトロンを経てアーサーアンダーセン(現あずさ監査法人)に入所、2023年6月退職。1995年頃より、組織におけるインタンジブルズの活用等への取り組みに関わり、グローバルおよび日本の関連プロジェクトのリーダーとして活動し、さまざまな官民の国際プロジェクトにも参画してきた。現在も、サステナブルな社会と長期的な企業価値の実現にむけた企業経営上の課題、特に企業報告に関わる調査研究、提言等を行っている。
芝坂佳子氏(以下、敬称略) 自社の経営を持続可能なものにしていくには、まず未来に向けてどんな会社でありたいか、社会にどう貢献していきたいか、経営の意思を明確化し、自分たちの言葉で言語化して発信することが第一歩です。これがいわゆる「パーパス(社会的存在意義)」と呼ばれるものです。
パーパスは、今後の企業価値を決定づける根幹となる要素であり、通常の財務情報からは得られない、投資家たちが最も知りたい情報を形づけるベースになります。またZ世代には、社会貢献や自己実現、人間としての成長など、金銭的な価値では測れないことに価値を見出す人たちが多いですよね。
「われわれはこうありたい。こんな社会を目指したい」と明言している企業は、こうした若い世代の目に魅力的に映るはずです。パーパスの明確化は、投資家に対する情報開示のためだけでなく、それに共感してくれる人材を惹きつけることにもつながります。
――自社の特徴を打ち出した魅力的なパーパスを作成するポイントは何でしょうか?
芝坂 少し先の未来、例えば30年先の未来社会を想像して、どんな会社でありたいかを考え、そこから逆算して自社のあるべき姿を考えることが大切だと思います。「バックキャスティング」と呼ばれる方法です。
一般に、中期の経営計画を立てる際など、現時点の事業内容や保有する設備、技術などの積み上げ式で先行きを考えがちです。しかし、この方法だとどうしても柔軟な思考や発想が生まれにくく、自分たちが本当にやりたいことは何なのか、自社の持続的な経営を支えてくれる一番の強みや武器は何なのかということに、なかなかたどり着けないものです。
「そんな未来のことなんか分からない」とおっしゃる方もいますが、実はそれほど難しいことではありません。たいていの場合、会社の中で、最も長期的な視点で物事を深く考えているのは経営者です。特にオーナー社長には、自社が社会で果たしていく役割とは何か、30年後にどんなことをしたいのか、日々考えを巡らせている方が多いはず。その考えをベースに社内でディスカッションして言語化していけばよいのです。
ただ社内の組織が階層化していて、経営者と一緒に自由にコミュニケーションする風土のない企業では難しいでしょう。その意味で、組織のフラット化を進めることも、魅力的なパーパスを作成するためには必要かもしれません。社長と若手社員が直接会話することで、大きな気付きが生まれることも多いので、ぜひ取り組んでほしいと思います。