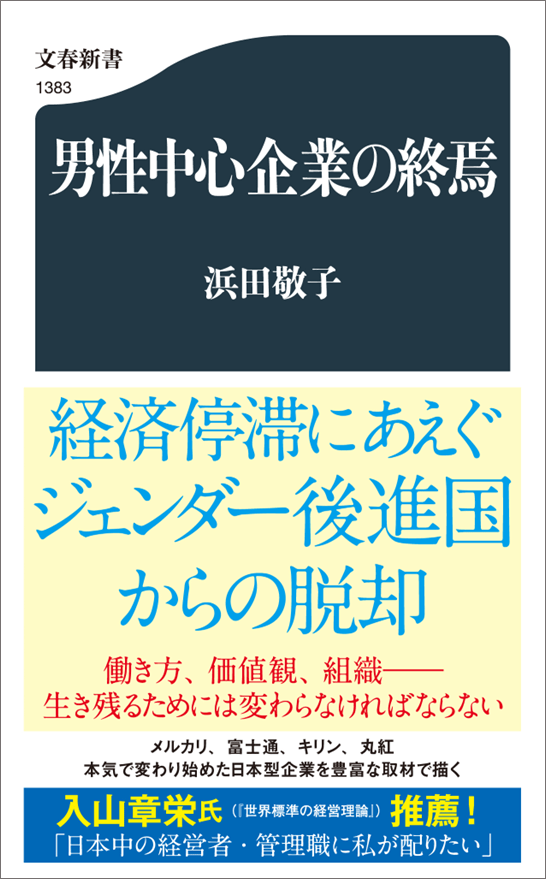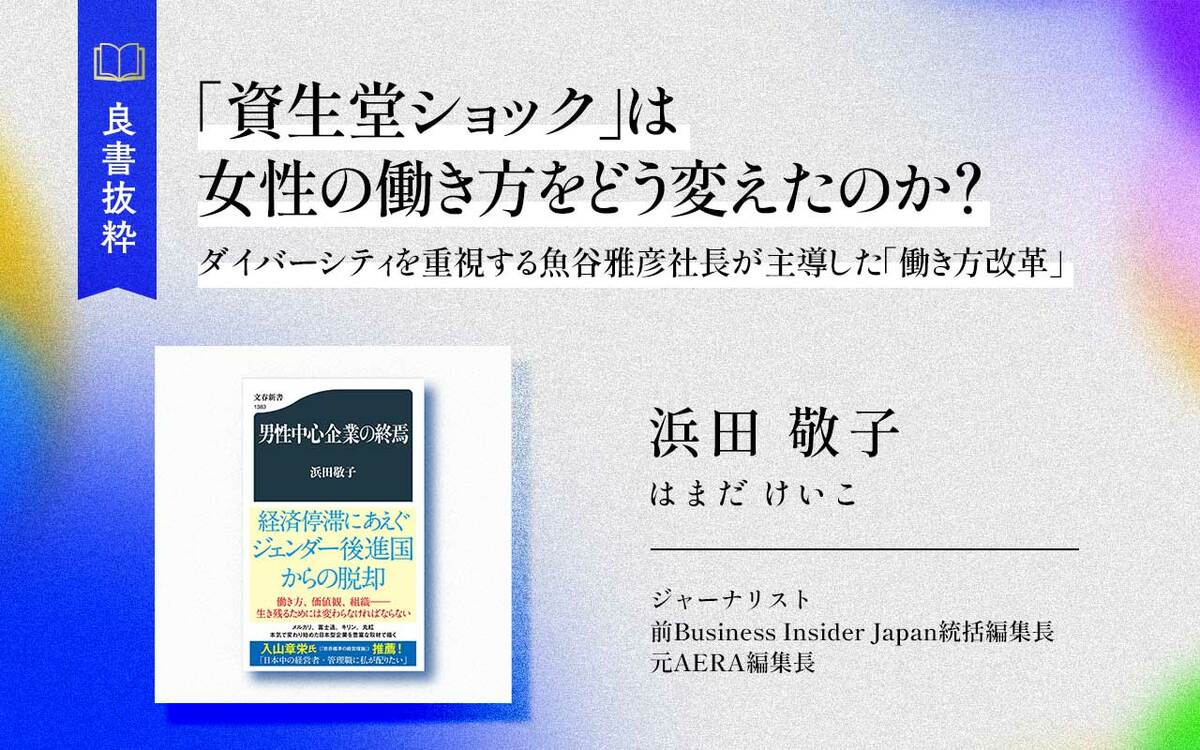
東証プライム市場に上場する企業の女性役員の比率を「2030年までに30%以上にする」という目標を政府が掲げたものの、日本のジェンダーギャップ指数は、先進国の中で最低水準。多様な人材の活躍の場を作り、ビジネスの成長機会を生み出し、社会を活性化させることは、企業こそ担える役割ではないだろうか。
本連載では、『AERA』編集長、Business Insider Japan統括編集長を歴任し、ダイバーシティや働き方をテーマにした講演を数多く行う著者が、積水ハウス、丸井グループなど先進企業の変革の取り組みを豊富な取材で描き出す。第2回は、魚谷雅彦社長(当時)が主導し、社員の多くを占める女性が、育児・介護をしながらキャリアアップを目指せるようにした資生堂の働き方改革について紹介する。
(*)当連載は『男性中心企業の終焉』(浜田 敬子著/文藝春秋)から一部を抜粋・再編集したものです。
<連載ラインアップ>
■第1回 ジェンダーギャップ指数121位で先進国最低水準、時代遅れの日本の実態とは?
■第2回 「資生堂ショック」は女性の働き方をどう変えたのか?(本稿)
■第3回 イクメン休業に女性イキイキ指数、積水ハウスと丸井は男性育休をどう進めたか
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
資生堂ショックが提起した問題
女性に本当に「活躍」してほしいなら、男性の働き方にこそメスを入れるべきという議論は、法整備と同時に、先進企業では「働き方改革」という形で進んだ。
その一方で、女性の働き方自体に関しても、2010年半ばに新たな議論が起きていた。女性を「保護」「配慮」の対象から「戦力」としてどう活かしていくのか、という議論だ。大きな転換点となったのが、「資生堂ショック」と呼ばれた資生堂の美容部員の働き方改革だった。
2014年、資生堂では育児のために時短勤務をする美容部員(ビューティーコンサルタント、BC)約1200人に対してそれまで免除されていた夕方以降の遅番や週末のシフトに、入れる人は入る形に見直した。
当時資生堂の女性社員比率は約8割。多くは美容部員だが、総合職の約半数も女性が占めてきた。2004年にはより女性に活躍してもらうために、女性活躍推進を経営戦略に掲げるなど、この分野においては日本で最も早くから取り組みを始めた企業の一つと言える。
それでも2000年代前半までは出産を機に退職する女性が多かったという。「子どもができたら退社」という第1ステージから、「育児をしながら仕事を継続」の第2ステージへの移行を目指して、企業内保育所や短時間勤務制度など両立支援制度の拡充を進めてきた。
その結果、2014年には育児休業者が年間1300〜1500人、時短勤務(育児時間)を取得しながら働く社員が2000人弱にまでなっていた。それに伴って深刻な問題になっていたのが、BCと呼ばれる社員たちの働き方だった。
時短勤務者たちの勤務時間が平日昼間に集中したため、平日夕方以降や週末はフルタイムで働く社員たちがいつもシフトに入るというようなことが起きていた。夕方以降の人手不足をカバーするカンガルースタッフ制度も導入した。
これは当時、様々な職場で問題になっていたことだった。両立支援制度が充実すると、子育て社員たちは「辞めずに済む」ようになるが、短時間勤務社員たちが早く帰宅した後に、そのサポートをするのはフルタイムで働く社員だ。
当時のAERAでも編集部員の3分の1を占めるワーキングマザー社員たちが、急な出張や夜の取材に行けない分を未婚女性や男性がカバーしていた。
支え、支えられる関係は1回や2回では終わらない。常にその状態が続くと、支える側には不満が溜まってくる。一方の「支えられる側」も「いつも早く帰ってごめんなさい」という罪悪感を抱き、肩身の狭い思いをするという構造が固定化する。資生堂だけの問題ではなかった。