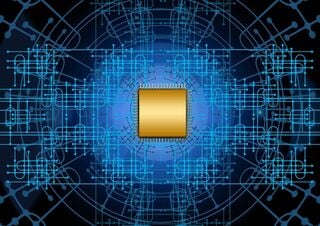こんにゃく。弾力ある歯ざわりが好まれ、田楽白和えやおでんなどに用いられる。
こんにゃく。弾力ある歯ざわりが好まれ、田楽白和えやおでんなどに用いられる。
「食感」がとりわけ特徴的な食材がある。口に入れたときの歯ざわりと噛みごたえ、そして舌が受ける感触。食感が独特であればあるほど、その食材はほかの食材と一線を画し、孤高さを感じさせるようになる。
「こんにゃく」は、そんな食材の代表格と言えるのではないか。例えば、おでん。がんも、きんちゃく、大根、ちくわ、はんぺん、卵と面子が揃う中で、こんにゃくは灰色の体で異彩を放っている。食べれば、歯ざわりでぷるぷる感を覚え、舌であの独特な風味を覚える。こんにゃくを食べるときだけは、ちょっとだけ「ちょっと違う具を食べる」といった意識を持つ人もいるのではないか。
こんにゃくはいまが旬と言える。11月は、こんにゃくの原料であるこんにゃく芋の収穫時期。消費量も11月から12月にかけてが毎年ピークとなっている(総務省統計局調べ)。
そこで、今回は「こんにゃく」をテーマに、日本人との関わりあいの歴史を追うとともに、こんにゃくに加えられている現代の科学技術をお伝えしよう。
前篇では、こんにゃくがどのように日本人の食材として定着していったのか、その変遷をたどってみる。後篇では、こんにゃくの成分に着目し、新たなこんにゃく加工品の開発に取り組んでいる未来食品研究所(群馬県)の滝口強氏に、今後のこんにゃく産業の活路を聞くことにする。