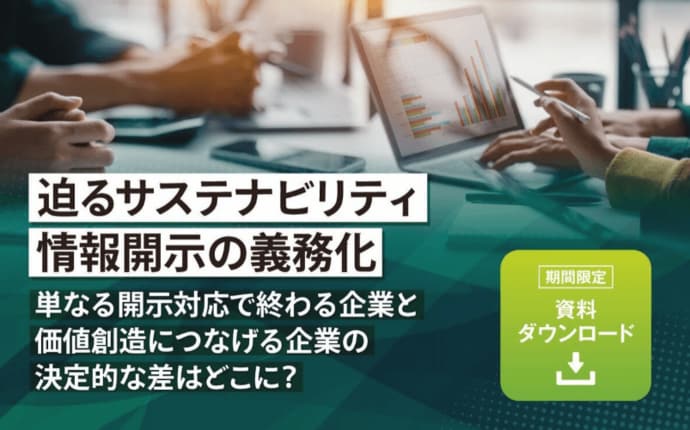富士通 代表取締役社長CEOの時田隆仁氏
富士通 代表取締役社長CEOの時田隆仁氏写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
プロダクト企業からDX企業へ転換すべく、全社変革プロジェクトに取り組む富士通。JTC(Japanese Traditional Company:日本の伝統的企業)である同社は、いかに時代の変化を成長の機会と捉え、生まれ変わろうとしているのか。本稿では、『CROの流儀 人・サービス・売り方を変え 提供価値と収益を最大化する』(大西俊介著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。CRO(最高収益責任者)が企業変革で果たすべき役割と、その舞台裏に迫る。
「売り上げ未達分の約1割を積み上げる」を目標に、社長直轄の緊急営業活動として実施された「TIGERプロジェクト」。そのリーダーとなった大西副社長は、何から着手したのか。
役員の直接商談を前提に対象顧客を選定
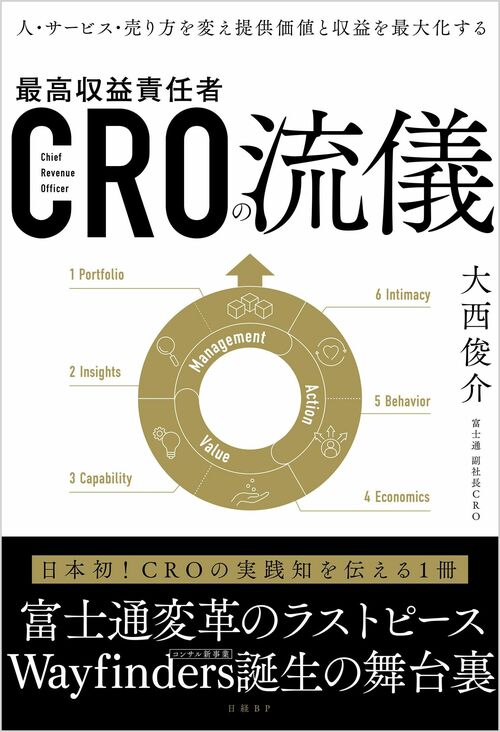 『CROの流儀』(日経BP)
『CROの流儀』(日経BP)
時間がなかったこともあり、役員合宿のすぐ後からプロジェクトの準備を始めました。期間は約1カ月。その段階でプロジェクトの大枠は固めてありました。
プロジェクトを運営するステアリングコミッティーのメンバー、海外拠点との連携窓口を含むPMOのスタッフ構成などです。また今回は気合いと根性ではなく、デジタルマーケティングの力を使うことと、OneCRMから上がってくるデータの分析をフル活用することを最初から考えていたので、デジタルマーケティングとデータ分析の担当者をそれぞれ最初から手当しました。
最初に手掛けたのはプロジェクトの対象にする顧客企業と、その顧客にアプローチするプロジェクト担当者の選定です。
まずは私が統括していたGCSBG(グローバル・カスタマー・サクセス・ビジネスグループ)部門の製造分野の顧客から3月末までに約50社、担当者候補45人を選び出しました。これを骨格にして、海外拠点や日本からも候補企業や担当者候補を募り、最終的には約100社を対象に、国内70人、海外14人の計84人をプロジェクト担当者に任命しました。対象の社数と担当者数が合わないのは1人で複数の顧客を担当したケースもあるからです。
対象の顧客選びは少し工夫しました。得意先の企業をあえて外したのです。投資力があり、大型案件の見込みと潜在能力のある顧客企業を選ぶのはもちろんなのですが、現状で富士通とはあまり仕事ができていない、「これだけの規模なのに、これしか取引がない」といった顧客企業を積極的にリストアップしました。