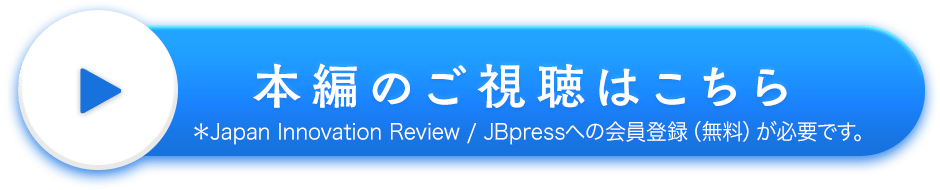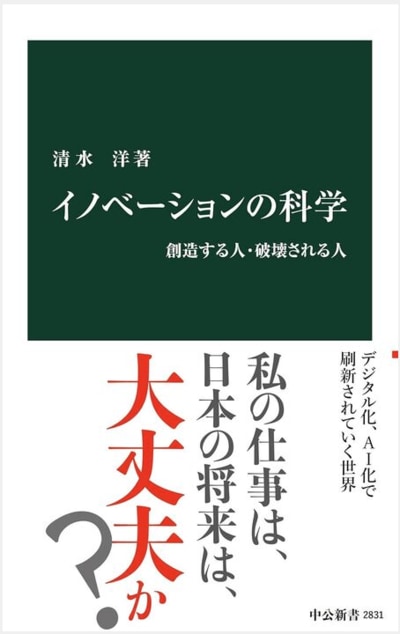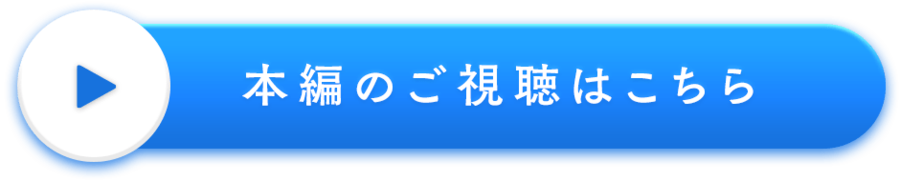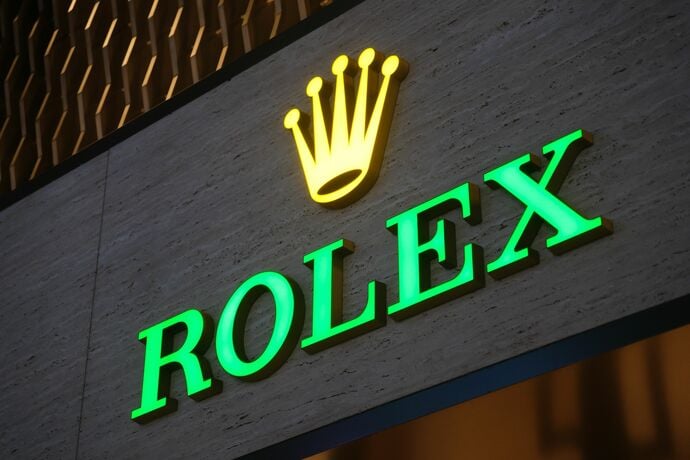以下はサマリー動画です。本編動画(22分49秒)はコチラから。
経済成長を促す起爆剤として、世界中のビジネスの現場で求められているイノベーション。一方で、イノベーションによって従来のスキルや生活が一変する経済プロセスを「創造的破壊」と言うように、「イノベーションを創造する者」がいれば「イノベーションによって破壊される者」も存在する。
この「創造的側面」と「破壊的側面」の両面からイノベーションについて考え、日本が目指すべきイノベーション戦略について提言しているのが早稲田大学商学学術院教授の清水洋氏だ。同氏は、2024年11月に著書『イノベーションの科学 創造する人・破壊される人』(中央公論新社)を上梓。「イノベーションは、人を幸せにするのか?」という、素朴かつ本質的な問いを学生から受けたことが執筆のきっかけになったという。
これまでイノベーションを創出するためには、リスクを恐れずに挑戦することができる人材が必要だと言われてきた。しかしながら、清水氏は「ビジネスパーソンがリスクを感じているとするならば、それはトップマネジメントの責任だ」と指摘。その上で、企業には「リスク・シェア」という仕組みが必要だと語る。イノベーションを創出する人だけでなく、イノベーションによって破壊される人においても必要な仕組みだという「リスク・シェア」の考え方とは。
 清水 洋/早稲田大学商学学術院 教授
清水 洋/早稲田大学商学学術院 教授
また、海外事例と比較しながら日本企業が目指すべきイノベーションの形についても解説。清水氏は、社会制度やビジネス環境の違いを適切に理解することが重要だと語る。例えば、コダックと富士フイルムの事例は日本においてイノベーションの成功事例として取り上げられるが、必ずしもコダックが「破壊された側」とは言えないという。フィルム事業が主力事業ではなくなる時代がそう遠くないことはコダックのエンジニアも分かっていたといい、むしろヘルスケアへの参入はコダックのエンジニアの方が早かったそうだ。では、なぜイノベーションの文脈においてコダックは「破壊された側」として解説されることが多いのか。そこには、日米間のビジネス創出の違いが大きく関係していた。
本動画インタビューでは、「イノベーションへの抵抗が生まれるか、否か」を分ける大きな2つの要因についても解説。日本企業のビジネスリーダーは、イノベーションをどのように位置づけ、向き合っていくべきなのか。著者であるイノベーション研究の世界的第一人者・清水氏へのインタビューで解き明かす。
【動画インタビュー視聴方法】
●ご視聴にはJapan Innovation Review / JBpressへの会員登録(無料)が必要です。
●既に無料会員にご登録済みの方は、 改めて登録する必要はございません。
<動画インタビュー内容>
- 本書を執筆したきっかけ
- 創造する人と破壊される人に必要な「リスク・シェア」とは?
- 大企業の中で「リスク・シェア」の考え方は必要か?
- 「創造する人」いわゆるハイパフォーマーの特徴
- 「包摂する社会」をつくる 企業の役割
- コダックは「破壊された側」なのか 日米の事業転換と社会制度の違い
- 日本企業が目指すべきイノベーションの形
- 「イノベーションへの抵抗」が生まれるか否かを分ける要因
- 今後、ビジネスパーソンはイノベーションにどう向き合っていくべきか?
 (撮影:木賣美紀)
(撮影:木賣美紀)
【動画インタビュー視聴方法】
●ご視聴にはJapan Innovation Review / JBpressへの会員登録(無料)が必要です。
●既に無料会員にご登録済みの方は、 改めて登録する必要はございません。