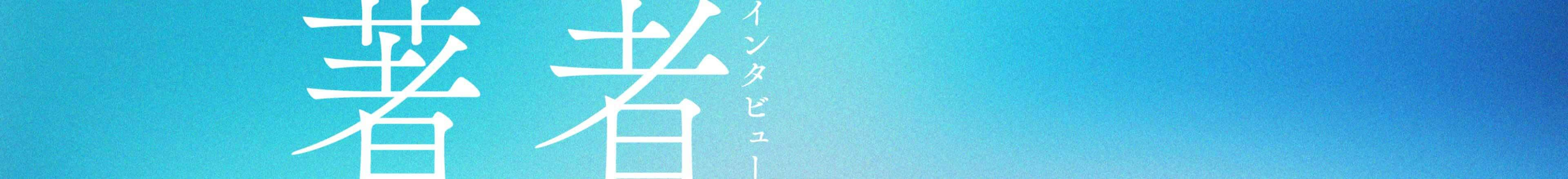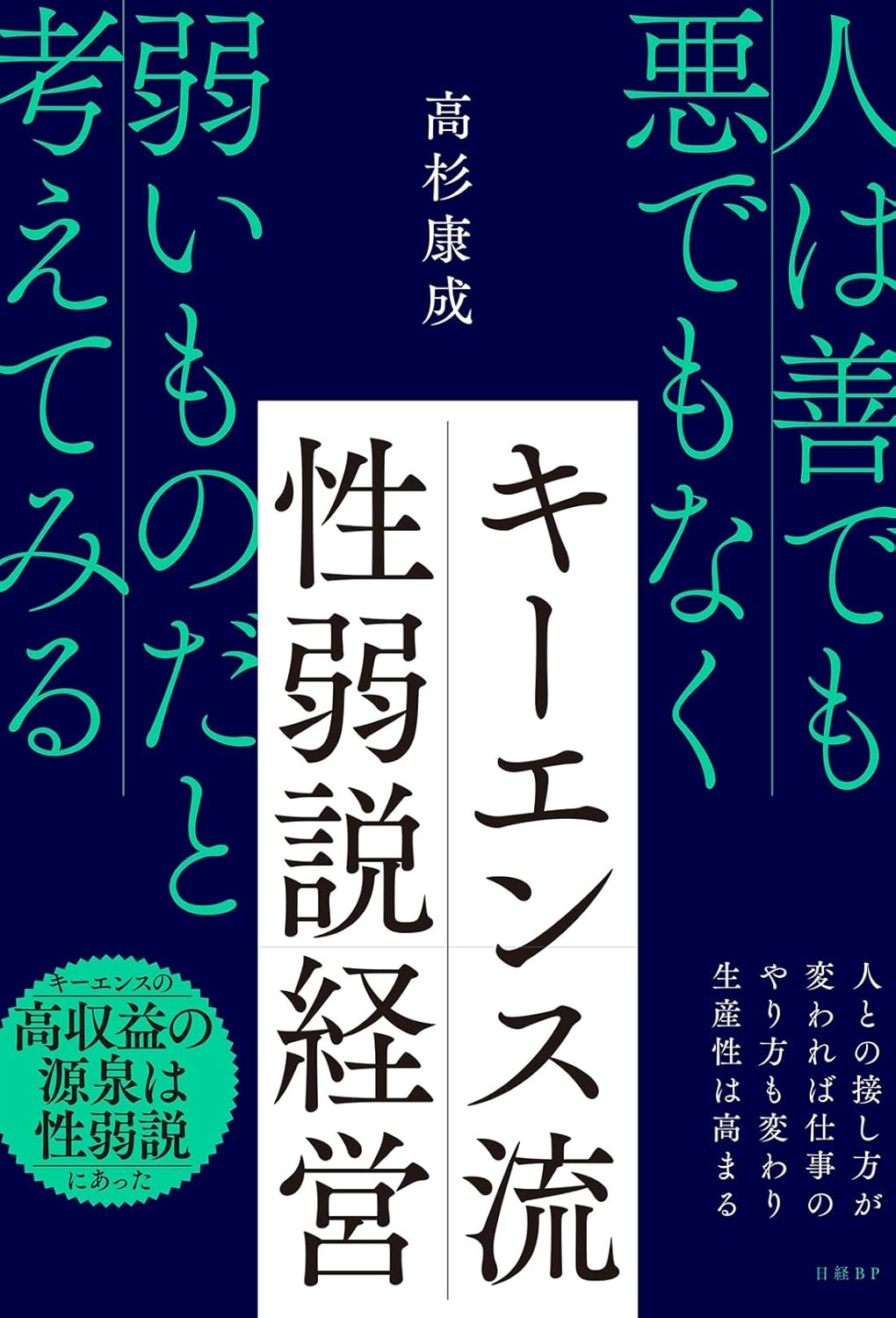出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
売上高が約1兆円、営業利益率50%超という超高収益企業のキーエンス。同社の高収益は、どのような経営手法によって実現されているのか──。その秘訣(ひけつ)について、かつてキーエンスで新商品・新規事業企画担当を務め、現在はコンサルティングファーム、コンセプト・シナジーの代表を務める高杉康成氏は、「性弱説」という考えを基にひもといている。2024年12月に書籍『キーエンス流 性弱説経営』(日経BP 日本経済新聞出版)を出版した同氏に、高収益を生み出すキーエンスの商品開発やマネジメントの手法について聞いた。
「仕様の見切り」がファブレスの経営持続性を高める
──著書『キーエンス流 性弱説経営』では、ファブレスというビジネスモデルの競争力について「性弱説」という視点からひもといています。キーエンスは50年前の創業期から自社で生産設備を持たないファブレスを採用していますが、いかにして競争力を高めてきたのでしょうか。
高杉康成氏(以下敬称略) 前提として、本書で述べている性弱説とは「人は本来弱い生き物である」という考えを指します。キーエンスでは、顧客や部下とコミュニケーションしたり、社内の仕組みを構築したりする際など、あらゆる場面で性弱説の考え方が生かされています。
ファブレスを効果的に機能させる上でも性弱説の視点を生かしており、長らく製造委託先との共存共栄を実現してきました。
自社で生産設備を持たないファブレス企業にとって、製造委託先の企業は重要なパートナーです。コストを抑えるために安く発注しようと交渉する企業も多いようですが、パートナー企業に無理難題を押し付けるような交渉をすれば、中長期的には自社のビジネスモデルを崩壊させることにつながりかねません。
そこでキーエンスがパートナー企業との共存共栄のために講じる策の一つが「仕様の見切り」です。例えば、A社が「最新機能を搭載し、サイズも小さくして、可能な限り安くしてください」とパートナー企業に依頼したとします。高価な最新部品を使い、サイズも小さくすると組み立てが難しく、手間もかかるため製造コストが高くなります。それにもかかわらず「安くしてほしい」と依頼したことになります。
こうした場合、キーエンスは「最新機能を搭載してください。サイズは現行品と同じで構わないので、コストについては可能な範囲で安くしてください」と依頼します。サイズが現行品と同じならばパートナー企業は効率的に製品を組み立てることができ、不良品の発生も抑制できます。そして、自社の利益を確保しながらA社の案件よりも安い価格をキーエンスに提示できるでしょう。
なぜ、キーエンスは「サイズは現行品と同じで構わない」と明言できるのでしょうか。それは、企画立案の段階で「サイズは現行品と同じでも売れる」という見込みが立っているからです。