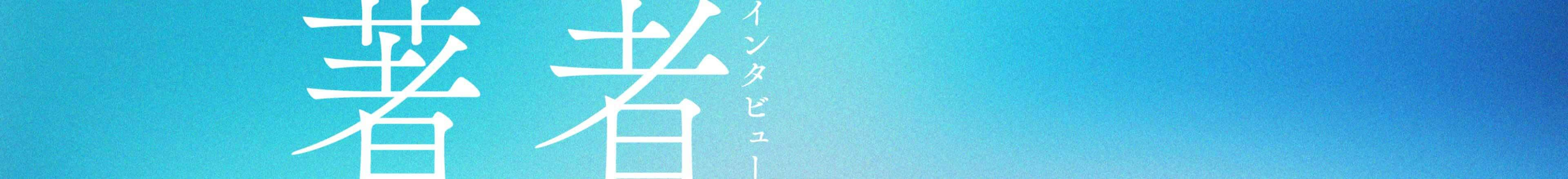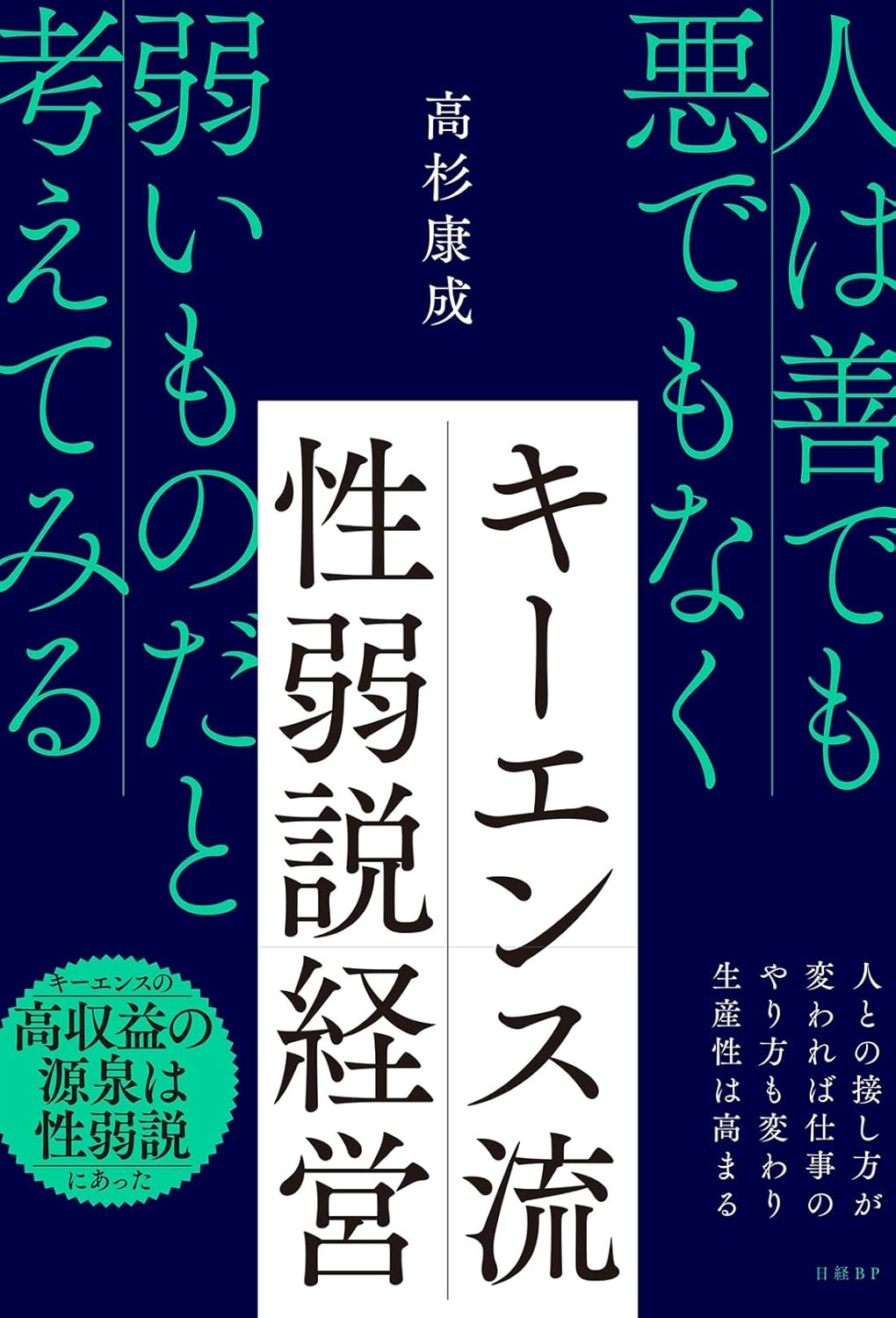営業利益率50%超という高収益企業として知られるキーエンス。同社と他の日本企業の「決定的な違い」は何だろうか──。この点について、2024年12月に書籍『キーエンス流 性弱説経営』(日経BP 日本経済新聞出版)を出版したコンセプト・シナジー代表の高杉康成氏は「キーエンスと他社の最大の違いは『性弱説の視点』の有無にある」と語る。「性弱説」とはどのような考え方を指し、どのようにして同社の高い収益力につながっているのか、話を聞いた。
人は本来弱い生き物だからこそ「性弱説」で考えるべき
──著書『キーエンス流 性弱説経営』では、キーエンスと他社との最大の違いとして「性弱説」を前提とした経営手法について解説しています。性弱説とは、どのような考え方を意味するのでしょうか。
高杉康成氏(以下敬称略) 「性善説」「性悪説」という考え方は古代中国の儒家の孟子と荀子の説に由来するものですが、これを私なりに再解釈したのが「性弱説」です。一言で言うと「想定通りに物事が進まないかもしれない」という状況に備える考え方です。
ビジネスにおける性善説とは、人はみな本来善人であることを前提とします。そこでは「マニュアルを作れば、みんなそれを守って動いてくれる」「仕事を正しく頼めば、適切に実行してくれる」「顧客にヒアリングすれば、求めている答えを返してくれる」といった思考になります。
しかしながら、実際には「思った通りには動いてくれない」ということも往々にしてあるのではないでしょうか。人は本来弱い生き物だからこそ、性弱説の考えを踏まえて「きちんとしたマニュアルを作っても、それを守って動いてくれないかもしれない」「仕事を正しく頼んでも、抜け漏れが出るかもしれない」「ヒアリングした内容は、事実ではなく顧客の主観かもしれない」と捉えることが大切です。
注意していただきたいのは、性善説が「相手を信頼している」、性弱説が「相手を信頼していない」という意味ではない点です。このような捉え方をしてしまうと「相手の能力を信頼できないから、全てトップダウンで管理してしまおう」というマネジメントに行き着いてしまいます。
「性弱説」とは「相手を信頼しているかどうか」とは無関係に「仕事の目的達成の確率を高めるためにどうすべきか」を優先し、適切なアプローチをする考え方のことなのです。キーエンスが高収益を出し続けている要因には、性弱説の考え方が組織に根付いていることが挙げられます。