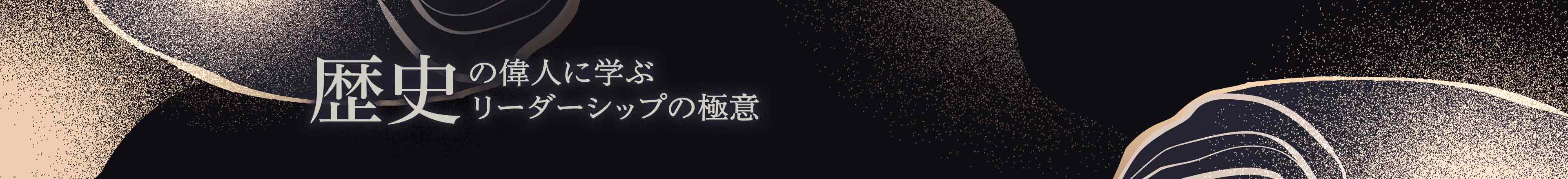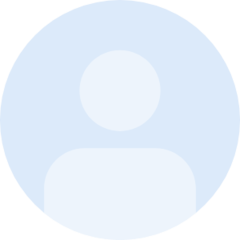京都御所 写真=hana_sanpo_michi/イメージマート
京都御所 写真=hana_sanpo_michi/イメージマート
歴史上には様々なリーダー(指導者)が登場してきました。その
若き日の道長はどんな人物だったのか?
2024年の大河ドラマは「光る君へ」で主人公は、平安時代中期の女性・紫式部です。ドラマでは、幼い頃からの式部の知人であり、熱愛相手として、藤原道長が重要な役どころとして登場しています。
道長と言えば「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の かけたることも なしと思へば」という「望月の歌」を権力の絶頂期に詠んだことを歴史教科書などで特筆されてきました。藤原氏摂関政治の最盛期を築いたことで道長は有名ですが、それではどのような公卿(政治家)だったのでしょうか。
道長は、康保3年(966)、藤原兼家の5男として生を受けます。母は兼家正室の時姫でした。道長の同母兄には、藤原道隆や道兼がいます。ちなみに、道長の父・兼家の生涯は波乱万丈でした。当初は兄・藤原兼通を追い越すほど出世(中納言→大納言)したものの、次第に追い抜かれ、遂には疎まれて左遷されることもありました。
しかし、兼通が亡くなると、兼家は復活。天元元年(978)8月には、娘の詮子を円融天皇に入内させることに成功します。その年には右大臣にまで昇進し、地歩を固めていくのです。詮子は、円融天皇の子・懐仁親王(後の一条天皇)を産むことになります(980年)。道長はその年(980年)に元服したと考えられています。
冒頭に記したように、道長は摂関政治の最盛期を築いたことから、出世が自明のことのように思われるかもしれませんが、決してそうではありません。道長には、道隆・道兼という実兄がいましたので、彼らが父の後継として家を盛り立てていくのが順当でした。
道長は永観元年(983)には侍従、その翌年には右兵衛権佐となりますが、格別の昇進だったわけではありません。では若き頃の道長は、どのような人物であったのか。平安時代後期の歴史物語『大鏡』には道長の性格を窺わせる挿話が幾つも載せられています。