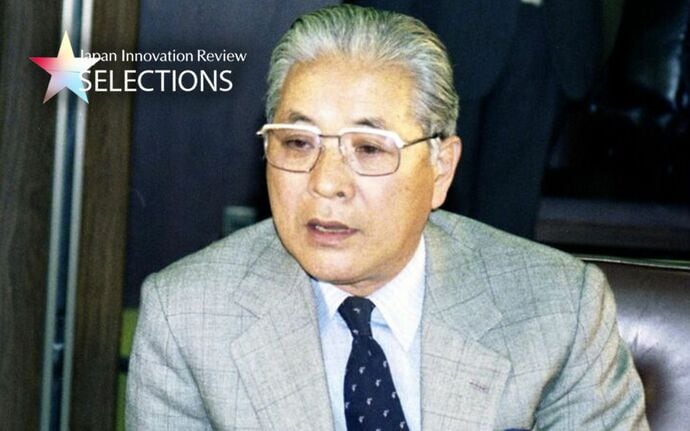モノづくり現場で使われる一切の商品「プロツール」を卸売する専門商社「トラスコ中山」の変革の舞台裏に迫っている。顧客の利便性を高めようとする思考は、独創的なサービスの発想につながる。今回は、モノづくり現場で使いたい時に資材や消耗品を「棚」から取り出せる、「富山の置き薬」のような発想で消耗品管理の概念を大きく変えた「MROストッカー」の事業化までと現在に迫る。
欲しい商品が「いま、ここ」にある
ここはモノづくりの現場。作業者が「棚」から作業に必要な資材や消耗品を手にとると、バーコードをスマートフォンで読みとる。そして手にした資材を使いはじめた……。
トラスコ中山のサービス「MROストッカー」の利用シーンだ。通常なら、作業者は必要となった資材や消耗品などを業者に発注し、届いてから使うことになるが、このサービスでは必要な商品を「棚」から取ればよいだけ。購買はバーコードの読みとりで成立する。「納期0秒」だ。
 モノづくりの現場に置かれた「MROストッカー」。MROは、Maintenance Repair and Operations。(写真提供:トラスコ中山)
モノづくりの現場に置かれた「MROストッカー」。MROは、Maintenance Repair and Operations。(写真提供:トラスコ中山)
「『富山の置き薬』方式をやったらどうや」
「MROストッカー」の発想のタネが生まれたのは2017年11月。トラスコ中山のボスコン(全国事業所長会議)で、あるチームが「営業拠点の近隣におられるモノづくり現場の方々がどんな商品を必要としているか把握し、支店や物流センターの在庫にその商品を置いておけば、すぐお届けできる」と提案した。
翌月、経営会議(取締役会)の場で同社社長の中山哲也氏が、この発想を昇華させる形で構想を打ち上げる。
「うちの拠点に商品を置くより、モノづくり現場であるユーザー様のところに当社の在庫を置かせていただき、使用した分だけ代金が発生する『富山の置き薬』方式をやったらどうや。そしたらもっと早くお客様に商品をお届けできるんじゃないか」
これで「MROストッカー」の原型が固まった。議事録には「ユーザー様にとっての在庫管理の手間がなくなる。得意先の発注の手間がなくなる。納期ゼロで手に入る」などと記されている。
同社では、中山氏の構想が言いっぱなしにならぬよう、どの部署が構想の具現化を担当するか決める。当初「MROストッカー」の導入・推進担当となった部署は、eビジネス営業部MROサプライ東京支店。うち、2008年に入社し、営業畑を走りつづけ、2017年より同支店で営業活動を行っていた上園宏一氏が、実務担当となった。