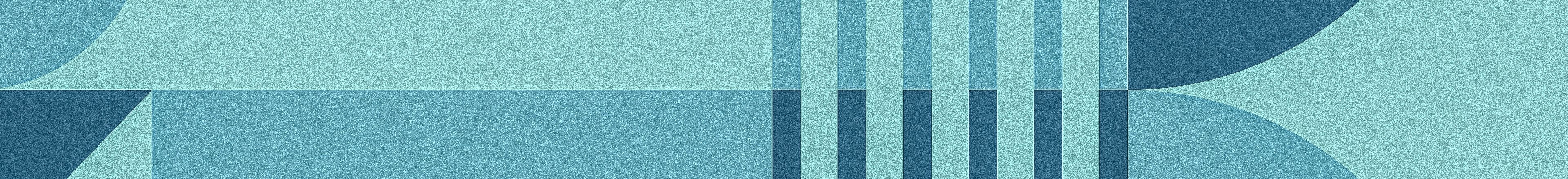2021年10月、くじらキャピタル株式会社(東京都/代表取締役社長:竹内真二氏)が、M&Aにより清酒酒造・販売の株式会社金井酒造店(神奈川県秦野市/代表取締役社長:佐野博之氏)の酒造事業を取得した。
それから1年。金井酒造はくじらキャピタルがもたらしたデジタル変革により、急速に業績を回復。年商は前年比1.2倍になり、赤字は半減、既に黒字化も視野に入っている。
老舗の酒蔵はDXにより、いかに業績回復を成し遂げたのか。M&Aに至るまでの葛藤から、V字回復を達成した現場の奮闘を追った。
※本記事は、2022年10月12日に、両社をマッチングしたM&Aマッチングサイト「M&Aサクシード」主催で行われた、くじらキャピタル竹内代表と、金井酒造店佐野代表との合同記者会見の内容をもとに構成しました。
 (左上)くじらキャピタル代表の竹内真二氏、(右上)M&Aサクシードの前田洋平氏、(下中央)金井酒造店代表の佐野博之氏
(左上)くじらキャピタル代表の竹内真二氏、(右上)M&Aサクシードの前田洋平氏、(下中央)金井酒造店代表の佐野博之氏
地方の酒蔵が突き付けられた現実
2020年。
金井酒造店の専務(当時。現在は社長兼6代目蔵元)を務める、佐野博之氏(以下、佐野)は岐路に立たされていた。
――150年続いた酒蔵を、私の代で終わらせるべきなのかもしれない――
そんなことはできるわけがない。いや、今やめればどれほど楽か。逡巡する毎日。
 左が佐野博之氏。自らも酒造りに従事しながら、社長兼6代目当主として経営も担ってきた
左が佐野博之氏。自らも酒造りに従事しながら、社長兼6代目当主として経営も担ってきた
金井酒造店は、明治元年創業、150年以上の歴史を持つ、神奈川県秦野市唯一の酒蔵だ。
名水で知られる丹沢山系の伏流水から造られる金井酒造の名酒「白笹鼓」は、同市内にある「白笹稲荷神社」(関東三大稲荷)に奉納されるほど、地元住民からも長く親しまれてきた。また、人気商品、「Mozart」は、麹にモーツァルトの曲を聴かせて造った酒だ。
日本酒になじみのある人なら、そのユニークな醸造方法を一度は耳にしたことがあるだろう。
 金井酒造店の代表作、「白笹鼓」は、大吟醸から純米酒まで幅広いラインアップ。地元を中心に、長らく親しまれているロングラン商品だ
金井酒造店の代表作、「白笹鼓」は、大吟醸から純米酒まで幅広いラインアップ。地元を中心に、長らく親しまれているロングラン商品だ
創業以来、真摯に酒造りに向き合ってきた。鑑評会では何度も入賞し、ヒット商品も、ロングランも多い。しかし、地方の小さな酒造メーカーは、時代から取り残されようとしていた。
佐野は、2010年ごろから徐々に経営に携わり、父親である先代から財務状況などの共有も受けた。しかし、既に経営状態は手の付けようがなく、銀行からの借入額を知った時は、足が震えた。
何をどうすれば、この借金を返していけるのか? 佐野には、全く見当もつかなかった。
近隣の同業者は縁戚関係にあることも多く、苦しい内情を相談する訳にはいかなかった。
同業者は自身の蔵の経営状況は順調と風呂敷を広げる一方、口をそろえて「日本酒業界に未来はない」と言った。どこそこも蔵を閉めた、どこそこは夜逃げした・・・、そんな話ばかりが耳に入り、次第にやる気を削がれていく。
実際、清酒製造業の数は、2000年から2016年の間に1977社から1405社にまで減っている。これは、1カ月に約3つの蔵が廃業している計算になり、酒蔵を存続させるのは、想像以上に困難な状況であると言える。
そして、佐野は、取引先銀行から、一つの提案を受けた。
「会社を残すのであれば、M&Aという方法もあるんですよ」
業界内でM&Aの話は昔から流れていたが、自分にその選択肢の話がまわってくるとは思わなかった。暖簾を降ろす以外の選択肢があることに初めて気付いたが、やはり最初は考え込んでしまった。
しかし、佐野は柔軟だった。先入観を捨て、M&Aに関する情報を集め始めた。この行動が、「M&Aサクシード」(東京都:M&Aのマッチングサイト)との出会いをもたらす。
そして、佐野と、150年の歴史を持つ酒造メーカーの運命を変えることになるのだ。
迎えた、2020年。新型コロナが追い打ちをかける。飲食店は、軒並み営業ができず、当然、金井酒造店も大幅な売上減に陥った。しかし、佐野は行動を続けた。
日本の酒造りの文化を途絶えさせてはいけない!
2021年2月末。
ある朝、くじらキャピタル代表の竹内真二氏(以下、竹内)は、一通のメールに目がくぎ付けになった。M&Aサクシードからの、譲渡案件の情報に関するメールだった。「酒蔵」「後継者不在」の文字が飛び込んでくる。竹内は急いでメールを開き、ある酒蔵の情報を確認した。その酒蔵こそ、「金井酒造店」だった。
メールを受け取った次の日にはM&Aサクシードを通じ、金井酒造店とのコンタクトを申し入れている(金井酒造店には、そのほかにも、物流、農業、輸出入、地方創生、ギフト、ECなどさまざまな業種の全国10社超からオファーがあった)。
竹内のこのスピード感こそが、企業再生のキーワードになることは間違いないが、それは徐々に語っていくことにしよう。
 くじらキャピタル代表取締役の竹内真二氏
くじらキャピタル代表取締役の竹内真二氏
くじらキャピタルは、「世界を素敵な会社で埋め尽くす」をミッションに、「DX×資本」により、中小企業の再生を手掛けるファンド会社だ。
実は、竹内は出資先の候補となる「酒蔵」を、2年もの間、探し続けていた。
日本酒の国内市場は、昭和40年代をピークに右肩下がり、出荷量はピーク時の7割減という非常に厳しい状況だ。しかし、海外の輸出量は順調に伸びていた。竹内はここに商機を見た。2年間、全国の蔵元を訪ね、中には、当主と具体的な話を進めたこともあった。
しかし、経営者の危機感の薄さ、変革への及び腰な態度に失望し契約には至らなかった。
「日本の伝統文化である、酒造りの技術を途絶えさせてはいけない。たとえ、国内の消費は先細りでも、一歩、海外に目を向ければ、マーケットは無限に広がっているのだから」
竹内は、ある別の視点から、酒造業界の未来に可能性を感じていた。
デジタル変革から取り残された、日本の伝統産業
竹内は、日本の中小企業におけるDXの遅れに、危機感を抱く一人である。
それは、かつて、4期連続最終赤字に陥っていた国内最大級の独立系デジタルマーケティング会社の株式会社アイ・エム・ジェイを、DXにより再建に成功した、実績と体験が大きい。
デジタルを導入すれば、旧態依然の無駄なアナログ作業を減らせ、その分、「人にしかできないクリエイティビティにもっと力を注げるはず!」と、自らの経験とともに、出資先企業にも、繰り返し伝えてきた。
「酒造り」は、まさに、クリエイティビティが求められるものでありながら、デジタル変革の波に取り残された産業の一つであり、だからこそ、事業再生の可能性を大きくはらんでいると、竹内は感じていた。
佐野は直接、竹内と会い、これまで自分がイメージしてきた「ファンド」とは大きく違う、くじらファンドの在り方に、絶大な信頼を寄せていく。互いに腹を割って、酒造業界の未来について本音で語り合った。何を守り、何を変えなくてはいけないのか。
対話を通じ、竹内は佐野の中に、「本気で酒造業界を変えたい!」と願う強い意志があることと、代々受け継がれている「ベンチャースピリット」が息づいているのを感じた。
金井酒造の創業は、明治元年だと先に述べたが、その時代を想像してほしい。
新政府が樹立し、西洋化への急激な転換により、市井の暮らしは大混乱。そんな時代のさなかに、金井酒造を立ち上げた初代当主は、酒造りの方法も全く知らない分家の一人の女性だったという。何もないところから、事業を起こし、時代の変革期、混乱の中の人々の日々の糧、笑顔のもとをつくり出そうとする。まさに、金井酒造は、150年前のベンチャー企業だったのだ。この創業ストーリーが、竹内が金井酒造に出資するかどうかを判断する際、大きく影響したことを付け加えておきたい。「金井酒造」という会社の中には、創業時から脈々と受け継がれた「起業家精神」が、確かに宿っていたからだ。
実際、佐野をはじめ、従業員は「新しいことや面白いことにチャレンジしよう!」という気概を持ち、商いを続けてきた。新商品の開発や、新規事業にも、何度、夢をはせたか分からない。しかし、資金がないがために、結局、着手ができない、従業員にもチャレンジさせてあげられないジレンマに、佐野は忸怩たる思いを抱えてきたのだった。
竹内と対話を重ねるたびに、佐野は自社に、そして酒造業界の未来に、希望を見いだす。
同業者や仲間内で愚痴をこぼすだけでは、見えてこなかった未来だ。
 佐野と竹内は、酒造業界の未来について、幾度も腹を割って話し合った。互いの「覚悟」を確認するプロセスは、スピード感を持ちつつも、確固たる信頼関係を築き上げた
佐野と竹内は、酒造業界の未来について、幾度も腹を割って話し合った。互いの「覚悟」を確認するプロセスは、スピード感を持ちつつも、確固たる信頼関係を築き上げた
大反対していた先代が、首を縦に振るまで
しかし、M&Aを成立させるためには、どうしても納得してもらわなければいけない相手がいた。先代であり、佐野の父親だ。
佐野の父親は70代。この世代は、やはり「ファンド」というものには、決して良いイメージを持っておらず、説得は難航した。
竹内にも直接会ってもらった。食事を共にし、人間性にも触れてもらった。
竹内の言葉には説得力があった。決して、人は辞めさせないこと。ブランドは守る、さらに、バリューアップさせること。金井酒造の歴史に敬意を払い、従業員さんと共に歩むこと。
なにより、佐野氏が、そのまま会社の代表を務めること――。
一つ一つ、丁寧に、誠実に伝えた。最後は、佐野自身が、極めて冷静に、父を説得した。普段であれば、感情的になりがちな親子関係であったが、暖簾を残す意味の重さと地元に根付いた商いの意味をとつとつと話し、全ての数字と業界内の話を腰を据えて語り合った。
父にも、やはり起業家の血は流れていた。もう一度、夢を見られるかもしれない。
孫やひ孫の時代には、全く新しい金井酒造の酒に出逢えるかもしれない――。
ようやく、父はうなずいた。2021年、夏のことだった。
佐野は、今、こう思う。
――会社を売ることは、決して恥ずかしいことではない――と。
何を、守るか、なのだ。何を大切にし、何を残すか、なのだ。
大切な従業員を守りたい。大切なブランドを残したい。何より、金井酒造のお酒を愛してくれるお客さまの笑顔を、この先もずっと見続けたい。それが叶うのならば、自身の小さなプライドや、同業者からの苦言や、ファンドに理解のない人からの心無い言葉も、取るに足らないことなのだ、と今なら思う。
しかし、当然ながら、M&Aの成立がゴールではない。本当の「再生」はここから始まる。
特に、本件は「人は変えずに、デジタルを導入する」ことを実現した、貴重な事例だ。デジタル機器にも不慣れな古参の従業員は、どのように変革を受け入れていったのだろうか。
シリーズ後編(11月8日配信)では、新体制となった金井酒造店が、どのようにDXを推進してきたか? その戦略と、現場の動きを追っていく。