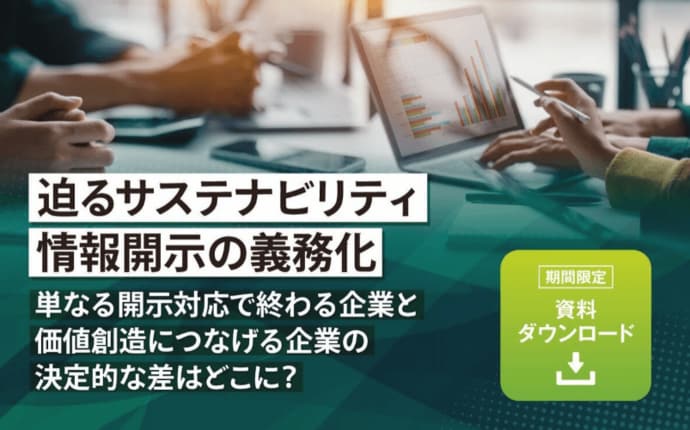写真提供:ロイター/共同通信イメージズ
写真提供:ロイター/共同通信イメージズ
2025年初頭、世界中で話題となった生成AI「ディープシーク(DeepSeek)」。チャットGPTと遜色ない性能で、しかも無料で使えるとあって、わずか1カ月で1億ダウンロードを達成した。しかし、この中国発AIの真の革新性は、ユーザー自身がデータを管理できる「分散型AI」の概念を取り入れていることにある。そう遠くない未来に、「誰もが自分のAIを持ち、使いこなす時代」がやって来るかもしれない――そのとき、私たちはAIとどう向き合うべきなのか。
ソフトバンクやアクセンチュアでAI エンジニアとして活躍してきた著者が、ディープシークの可能性と課題、そして生成AIの未来について記した『DeepSeek革命 オープンソースAIが世界を変える』(長野陸著/池田書店)から内容の一部を抜粋・再編集。今回は、ディープシークの優位性を捉えるための三つの視点を紹介する。
チャットGPTとディープシーク、二大AIの特徴と課題
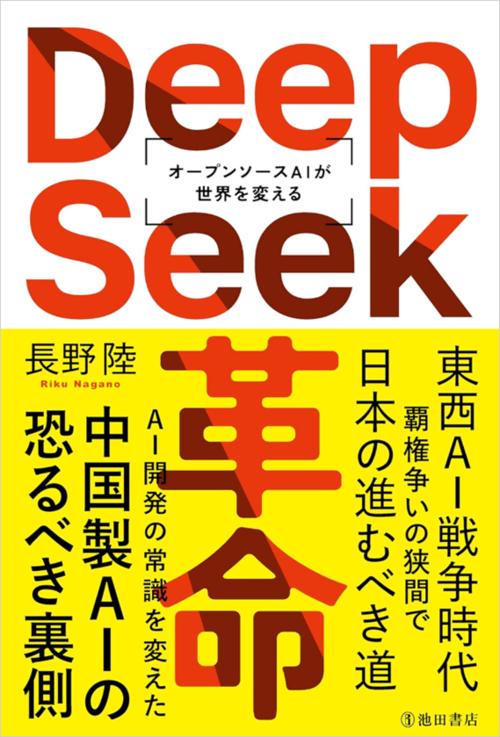 『DeepSeek革命』(池田書店)
『DeepSeek革命』(池田書店)
■ チャットGPTの抱える課題
チャットGPTがここまで爆発的に普及した理由は、その自然な会話能力と高い利便性にあります。これまで人間が行っていた知的作業の一部を代替できる存在として、多くの人々が日常的に活用するようになりました。
しかし、チャットGPTは高性能なAIである一方で、いくつか課題も抱えています。
その一つが「事実誤認(ハルシネーション)」を引き起こす可能性があることです。これは、AIがもっともらしい回答を生成するものの、必ずしも正確な情報とは限らないという現象です。
AIは学習データに基づいて確率的に単語を選んで文章を構築するため、事実に基づかない内容や誤った情報を含む回答を生成することがあります。特に専門性の高い分野や、正確性が求められる場面では、この問題は看過できません。
また、チャットGPTの学習データに偏りがある場合、その影響を受けた回答を生成する可能性も指摘されています。特定の見解や立場に偏った回答は、公平性が求められる判断において問題となり得ます。
こうした課題を認識した上で、チャットGPTを活用するためには、AIの生成した情報を適切に検証するプロセスや、人間による最終確認の仕組みを導入することが不可欠です。AIの特性を理解し、その長所を活かしつつ限界を補完する「人間とAIの協働」が今後の重要な要素となるでしょう。