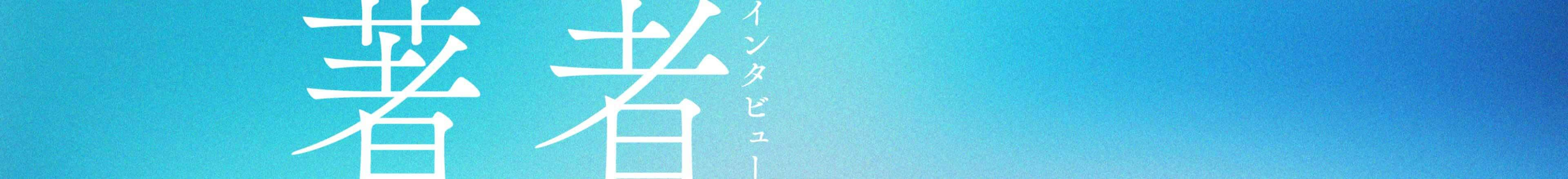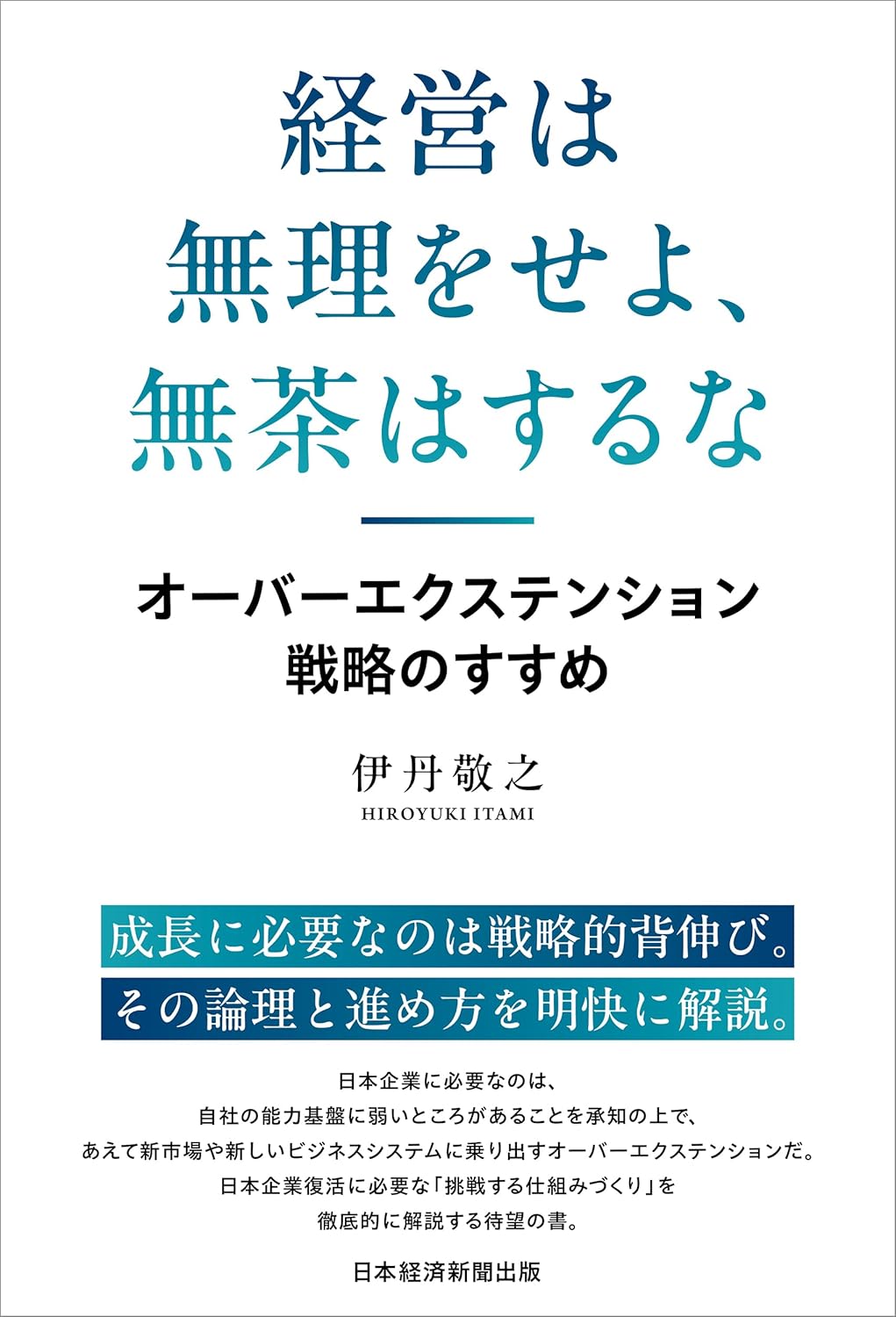写真提供:monticellllo - stock.adobe.com
写真提供:monticellllo - stock.adobe.com
自社に十分な実力がないことを承知の上で、あえて新しい事業活動に挑戦し、「戦略的背伸び」によって企業の能力基盤を拡大させる──。それが一橋大学名誉教授の伊丹敬之氏が提唱する「オーバーエクステンション戦略」だ。では、失敗リスクを伴う中で、いかにして戦略的背伸びを成功に導けばよいのか。2025年2月に『経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ』(日本経済新聞出版)を出版した同氏に、ユニクロや信越化学工業の事例を通じて、オーバーエクステンションの成否を分けるポイントについて聞いた。
2000年代にユニクロが直面した「無茶による失敗」
──著書『経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ』では、2000年初頭にユニクロが海外進出に失敗した例について解説しています。当時の経営判断を「無茶だった」と述べていますが、失敗の背景にはどのような原因があったのでしょうか。
伊丹敬之氏(以下敬称略) ユニクロを運営するファーストリテイリングの成長の歴史は、自ら厳しい状況を意図的につくり出すことで飛躍を図る「オーバーエクステンション」の連続でした。それが現在の快進撃につながっていることは確かです。
しかし、無理を飛び越えて「無茶」になってしまった挑戦もありました。その一つが、2000年初頭の海外進出です。2001年にロンドンへ出店し、その後の3年間でイギリス国内に50店舗出店という目標を掲げました。さらに、2002年には中国・上海に2店舗を出店しました。同時期には、生鮮農産物の栽培と販売にも乗り出しました。
こうした大胆な施策に打って出たものの、これら3つの試みは全て失敗に終わっています。イギリスでは赤字が続き、ロンドンの5店舗のみへと縮小しました。上海では店舗数の拡大こそ目指しませんでしたが、売れ行きは不振が続きました。そして、農産物事業では約30億円の赤字を出して撤退しています。
これらの失敗の原因については、代表の柳井正氏自身が「自分自身がバブル状態になっていたのではないかと思う」と語っています。日本で大成功していたという慢心があった、と言っても過言ではないでしょう。
また、これらの挑戦は市場から見ても魅力に乏しく、組織の能力基盤を整備するための計画も不十分だったと分析しています。