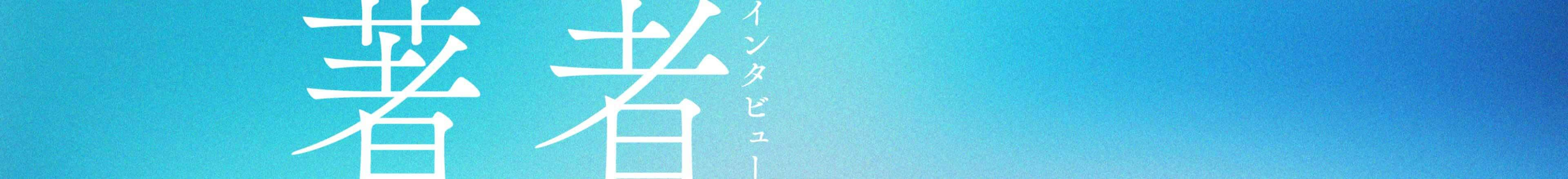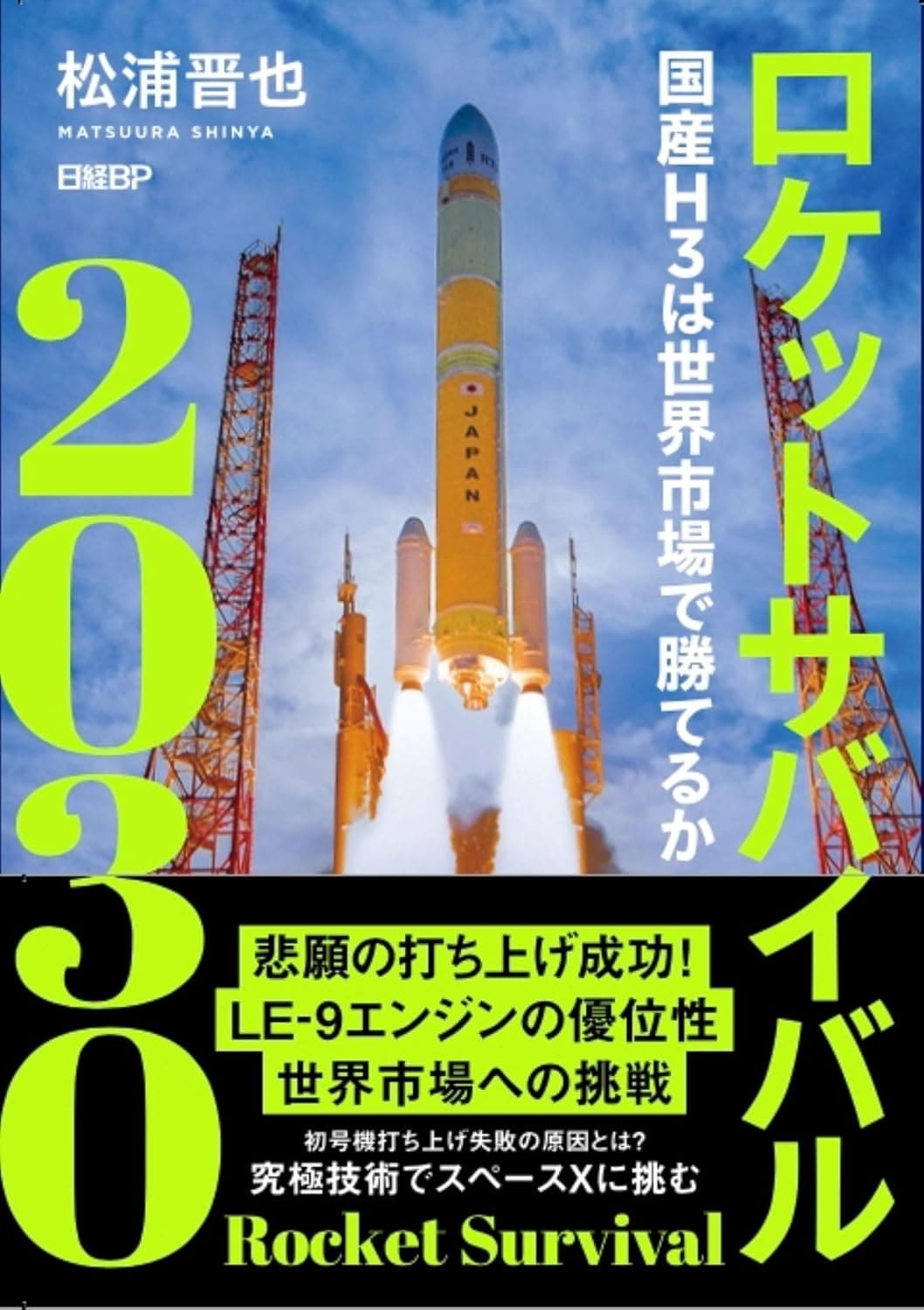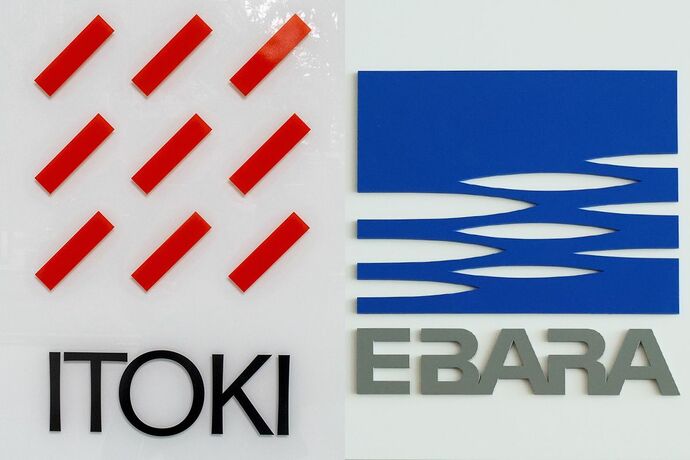出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
イーロン・マスク氏が設立したスペースX社のロケット「ファルコン9」は、それまでの世界の宇宙ビジネスを根底から変革した。一方、日本のJAXAと三菱重工が開発した「H3ロケット」は、それまでのロケットエンジン技術の通説を覆し、新たな可能性を生み出したという。ファルコン9が巻き起こした変革、そして、日本の技術を結集したH3ロケットの戦略とは──。2024年12月、著書『ロケットサバイバル2030 国産H3は世界市場で勝てるか』を出版したノンフィクション作家で科学技術ジャーナリストの松浦晋也氏に、ファルコン9の革新性や、日本が宇宙産業に見いだすべき「勝ち筋」について聞いた。
スペースXは「ロケットビジネスを根底から変えた」
――著書『ロケットサバイバル2030』では、イーロン・マスク氏が設立したスペースX社のファルコン9について触れています。ファルコン9はどのような点が画期的なのでしょうか。
松浦晋也氏(以下敬称略) ファルコン9の最大の特徴は、ロケットの第1段を「回収・再利用する」ことです。現在の人工衛星打ち上げ用ロケットは2~3段式の構成が主流となっていますが、そのうち第1段は最初に燃焼して機体を押し上げる重要なパートです。その第1段を回収・再利用することで、打ち上げコストの削減を狙っています。
それまでのロケットは、打ち上げた機体を宇宙空間などに投棄する「使い捨て型」が主流でした。しかし、ファルコン9はエンジンの逆噴射を活用し、最も大容量でコストの高い第1段ロケットを地上に軟着陸させて回収することに成功し、回収・再利用型を実現しました。
加えて、回収・再利用型のロケットには、もう1つの目的があります。それは、高頻度の打ち上げを可能にすることです。ロケットの第1段を回収・再利用することで、自社ロケットの生産能力を超えた高頻度の打ち上げが可能になるのです。
その結果、多数の小型人工衛星を何度も打ち上げる必要のある「衛星コンステレーション」を構築する需要に応えることができます。衛星コンステレーションとは、多数の小型人工衛星を同時に打ち上げ、それぞれを連携させ、一体として運用する衛星群を指します。
こうした需要の高まりに対応したことで、宇宙関連ビジネスの急速な発展につながりました。