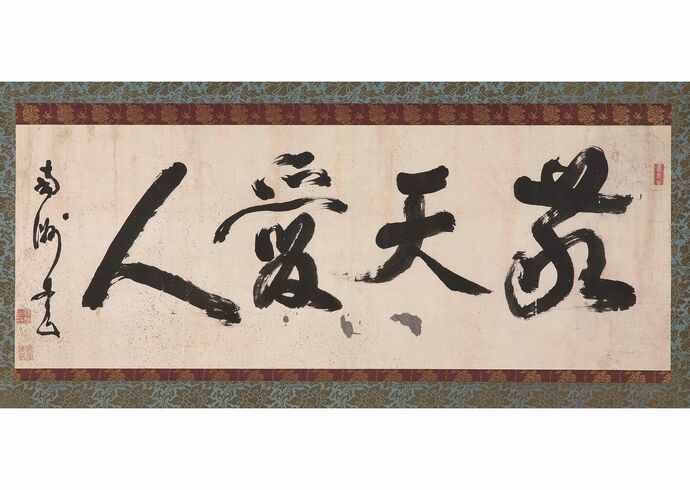ペンシルロケット発射実験の指揮をとる糸川英夫教授(写真提供:共同通信社)
ペンシルロケット発射実験の指揮をとる糸川英夫教授(写真提供:共同通信社)
「ものづくり大国」として生産方式に磨きをかけてきた結果、日本が苦手になってしまった「価値の創造」をどう強化していけばよいのか。本連載では、『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』の著者であり、故・糸川英夫博士から直に10年以上学んだ田中猪夫氏が、価値創造の仕組みと実践法について余すところなく解説する。
第2回では、飛行機設計において誕生した「チーフデザイナー制度」のルーツに迫る。
ゼロバリューだからこそ生まれた価値創造システム
東京帝国大学工学部航空学科(当時定員9名の超難関)を卒業し、中島飛行機で設計者になった糸川英夫博士は、一生を飛行機に捧げるつもりでいた。しかし、敗戦後のポツダム条約受諾による航空禁止令によって、「糸川英夫 = 飛行機」だった方程式の右辺が左辺に移動され「糸川英夫 - 飛行機 = 0」となり、価値のないゼロバリューの人間になったと『八十歳のアリア』(文藝春秋)に書いている。そして、糸川博士と同じ飛行機屋で立川飛行機の設計者だった長谷川龍雄氏もゼロバリューとなったのである。
1912年生まれの糸川博士は、真珠湾攻撃が始まる10日前の1941年11月26日に、29歳で東京大学第二工学部の助教授になっている。生きる目的を失いノイローゼとなって病院に通ううちに、医者から脳波記録装置や麻酔深度計の開発を頼まれることになり、その論文がシカゴ大学で認められ渡米することになった。
そこで出合ったのが『スペース・メディスン』(宇宙医学)という本だ。糸川博士はこの本に刺激され、ロケットの研究をスタートさせた。同じ頃、1916年生まれの長谷川氏は、敗戦の翌年1946年に30歳でトヨタ自動車工業(以下、トヨタ)に越境転職している。
2人とも航空禁止令という逆境で商売替えをせざるを得なくなった。異なる業界へ商売替えをすると誰でも経験することだが、前に勤めていた会社や業界固有の知識である固有技術(ファームスペシフィックスキル)がまったく役立たなくなる。従って、商売替えでは、業界や会社が変わっても使うことができるポータブルスキルを獲得・創造せざるを得なくなる。まさに、糸川博士の口癖「逆境は成長のルーツである」通り、ゼロバリューが価値を生み出す価値創造システムにつながったのである。
請負制度から職能専門家の集団化へ
日本経済新聞に連載された糸川博士の「私の履歴書」には、戦前の複葉機から単葉機に変わった時代の飛行機会社の設計部の様子が、次のように書かれている。
「設計室での大きな変化は、請負制度から職能専門家集団化の遷移点にあった。吉田孝雄、三竹忍、明川清、山本良平、松村健一などそうそうたる航空科の先輩は、いずれも一家を構えたボスよろしく、新しい設計の請負をその配下とともに引き受ける。この時代から建築のように、デザイン、構造、配管配線などの屋内装備に、専門が分かれはじめた。あるいは、私が勝手に、空力計算一手ひきうけ屋の看板をかかげ、ついで空力設計専門にひきうけますという看板をあげたことが、この傾向のトリガーになったのかもしれない。」
つまり、従来の飛行機設計は、A飛行機はボス・吉田孝雄配下の部下と共に丸ごと請け負う。B飛行機はボス・三竹忍配下の部下と共に丸ごと請け負うという請負制度だったのが、空力設計専門家、エンジン設計専門家、内装設計専門家と職能集団に分かれたというのだ。
そうなると、AやBという飛行機ごとにそれぞれの専門家を束ねる専門家が必要になってくる。これが飛行機設計におけるチーフデザイナー制度の始まりだ。
当時の中島飛行機は、三菱や川西、川崎を超える東洋最大の航空機メーカーだった。一方、立川飛行機は軍用機の生産が得意で、中島飛行機の戦闘機「隼」を転換生産する関係だった。1939年に糸川博士と同じ東京帝国大学工学部航空科を卒業した長谷川氏は、B29の迎撃機キ94の設計主務などを務めていたこともあり、中島飛行機で始まったチーフデザイナー制度は伝わっていたと思われる。