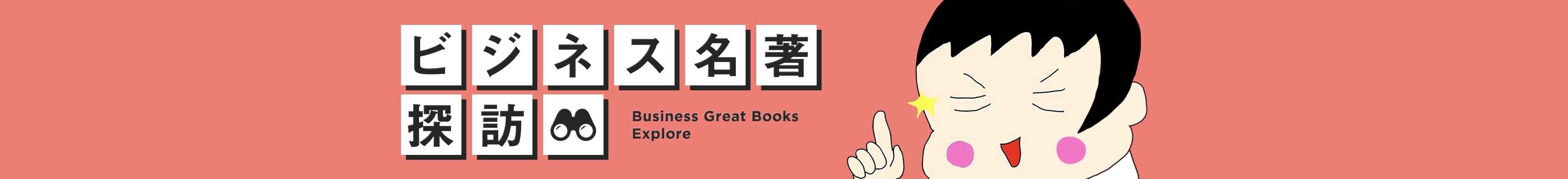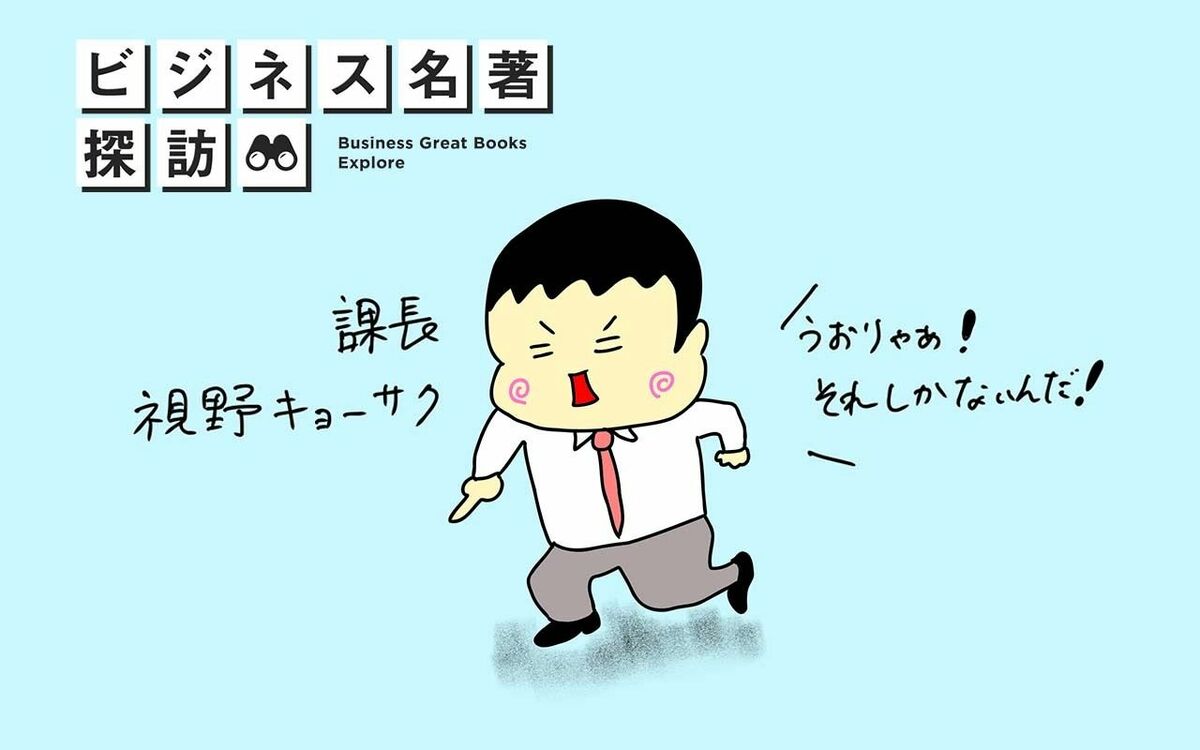
ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。
連載第11回は、「制約理論」を世に知らしめ、ジェフ・ベゾスもアマゾンの経営陣たちと読んだと言われる世界的ベストセラー『ザ・ゴール 企業の究極の目的とは何か』(エリヤフ・ゴールドラット著/三本木亮訳、ダイヤモンド社)を取り上げる。
「熱心な視野狭窄型」リーダーによって引き起こされる悲劇
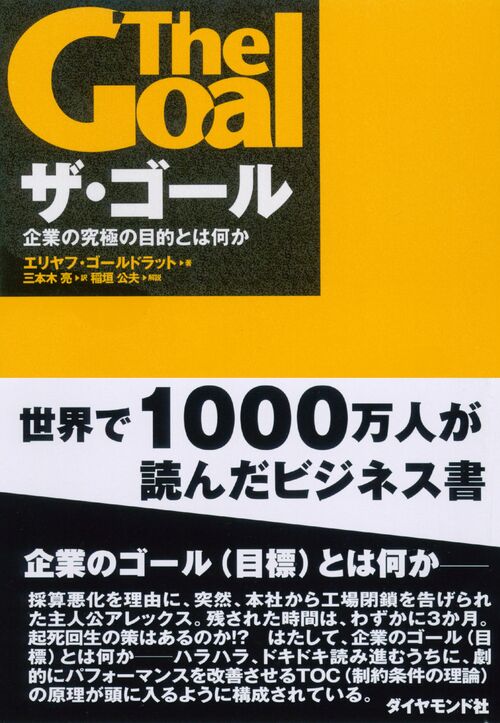 『ザ・ゴール』(エリヤフ・ゴールドラット著/三本木亮訳/稲垣公夫解説、ダイヤモンド社)
『ザ・ゴール』(エリヤフ・ゴールドラット著/三本木亮訳/稲垣公夫解説、ダイヤモンド社)
私は立場上、アドバイザーなど第三者的な立場で企業の新規事業や新たなプロジェクトに関わることが多い。
その経験を経て、プロジェクトリーダーには、一つの大事な要件があることを理解した。それは「視野の広さ」だ。全体最適を考えられるか、という言葉にも言い換えられるだろう。
これは別に目新しいキーワードではない。しかし、その重要性は、想像している以上に大きいというのが実感値だ。
それは、視野の狭いプロジェクトリーダーほど危険な存在はないからだ。視野の狭さに「熱心さ」が組み合わさると、やや大げさだが、経営を脅かす手に負えない存在になる可能性がある。今までそのような「熱心な視野狭窄型」リーダーによって引き起こされた悲劇を何度か見てきたからだ。
では「熱心な視野狭窄」はどんな意味で危険なのだろうか? それは、自分がコミットした目的達成に必死になるがゆえに、自分たちの行為が関係する他組織にどのような影響を与えているかについて、一切気にかけることなく突っ走ってしまうことにある。結果的に、その行為が組織全体としてはマイナスになったとしても、猪突猛進にやり続けてしまう。これが怖いのだ。

例えば、マーケティング部隊が新規顧客獲得という目標を掲げていたとしよう。「熱心な視野狭窄型」は、「新規顧客数」という目標数値だけにとらわれて、顧客の質やステータスなどにはお構いなしで、顧客からの営業アポイント獲得だけに走ってしまう。
しかし、そのバトンを受け取った営業部隊は大変だ。営業対応が後手に回り、顧客のステータスにバラツキがあるために無駄足が多くなり、キャパシティーオーバーになる可能性がある。
当然ながら、営業がクロージングをしない限り、組織全体の売上は立たない。そのまま営業が機能不全状態では、マーケティング部隊が頑張るほど売上は悪化する可能性がある。しかし、熱心な視野狭窄型は、そこに目が向かない。悪気なく、脇目も振らず「顧客からのリード獲得件数」を上積みしていってしまうのだ。
このように、「熱心な視野狭窄型」がいる組織では、その部署の生産性が高まったように見えて、一方で組織全体の生産性は低下する、ということがよく起こる。そして、「熱心な視野狭窄型」リーダーの部署だけが奮闘しているように見えるから、そのリーダーの発言力は高まり、似たようなタイプがはびこり始める。こうして組織全体が停滞していくのだ。もちろん、実際はこんな単純ではないが、デフォルメするとこのようなパターンに陥ることが多い。