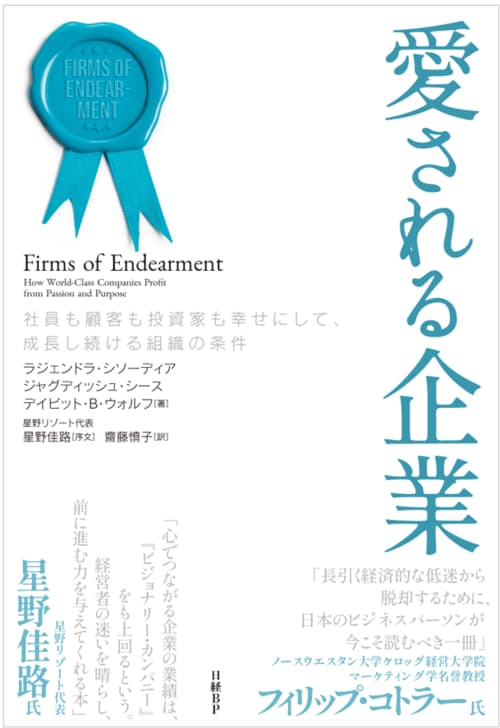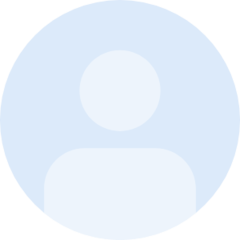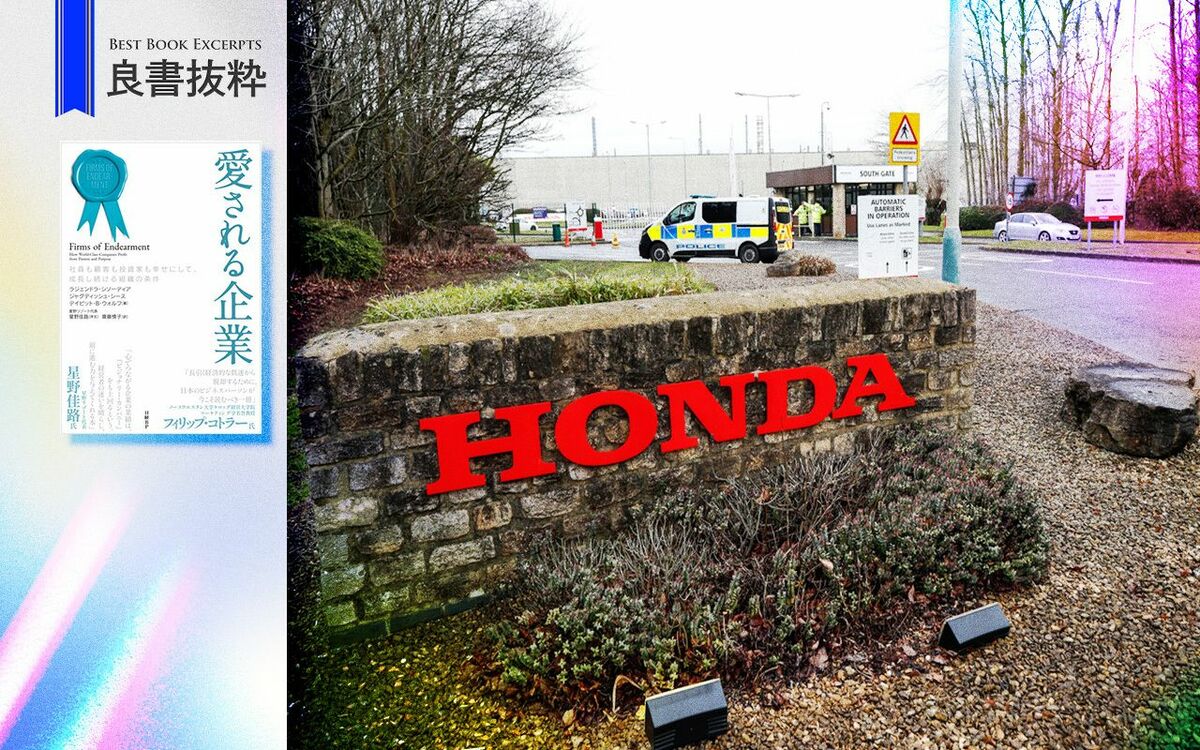 写真提供:ロイター/共同通信イメージズ
写真提供:ロイター/共同通信イメージズ
時代を超えて輝き続ける18社を研究した『ビジョナリー・カンパニー』(1994年発行)は現在も経営者の必読書と言える名著だが、それをさらに進化させた本『愛される企業 社員も顧客も投資家も幸せにして、成長し続ける組織の条件』(ラジェンドラ・シソーディア、ジャグディッシュ・シース、デイビット・B・ウォルフ著/齋藤慎子訳/日経BP発行)が話題を呼んでいる。キーワードは「愛」。企業経営にはおよそ似つかわしくない言葉だが、顧客や投資家のみならず関係するあらゆる人・組織に愛されることこそが経営の本質だと説く。抽出された72社はビジョナリーカンパニー以上の実績を上げており、そこには共通して7つの特徴があるという。本連載では、同書から内容の一部を抜粋・再編集、愛される企業の条件を事例を交えて紹介する。
第5回は、世界的に知られるホンダの「ベストパートナープログラム」を例に、サプライヤーとの関係性と質が収益に強く結びつく理由について解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 ホンダ、コストコ、グーグル――「愛される企業」に共通する特徴とは
■第2回 コストコの福利厚生は手厚過ぎる? 成長し続ける企業の「意外な条件」とは
■第3回 GEのジェットエンジン工場では、なぜ工場長がいなくても欠陥品が出ないのか?
■第4回 イケアやトヨタ、サウスウエスト航空は、なぜ「低価格、気高い魂」を重視するのか
■第5回 ホンダの成功のエンジン、「ベストパートナープログラム」はなぜうまくいくのか?(本稿)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
■協力するほうが搾取するより得策
愛される企業は、自社と関わることがステークホルダーの得になるよう心を砕く。サプライヤーのさらなる繁栄を手助けすることもそうだ。
長年、大手小売業者の多くがサプライヤーに毎年のように値下げを要求している。サプライヤーの収益性や存続が危うくなっても、それはサプライヤーの問題、というわけだ。愛される企業ならわかっているが、こうした冷淡なやり方で価格をコントロールするのは近視眼的で、サプライチェーンの健全性を害している。もっと悪いのは、サプライヤー同士に熾烈な価格競争をさせることにつながり、パートナーシップの恩恵が得られなくなることだ。
サプライヤーに毎年のように値下げを要求するのは持続可能な戦略ではない、という認識が高まりつつある。IBMがそれを認識し始めたのは、外部委託が急に増えた1990年代だ。ノースカロライナ州ローリーでIBMの調達サービスを担当しているビル・シェーファー部長が次のように述べている。
「長年、調達に関わっていますが、これまでの調達には、サプライヤーを信頼のおけないどうでもいい相手として扱うイメージがあります。それは良くないし、持続可能でもない調達のモデルだとわたしたちは考えています。IBMとサプライヤーのあいだに、緊密なチームワーク、信頼、分かち合いがなければ、うまくいかないのです」
ホンダがサプライチェーン管理で世界をリードしていることは広く知られている。サプライヤーとの長期にわたる、価値主導型の関係性の構築・維持に重点を置くことで、順調に成果をあげている。
ホンダは、製造会社というより組立会社に近い。たとえ新車であっても、そのパーツのほとんどをホンダは製造していない。米ホンダでは、車づくりに必要なパーツの約80パーセントを外部サプライヤーから調達している。だからこそ、サプライヤーを使い捨てにするのではなく、パートナーとして扱うのが賢明な判断なのだ。サプライヤーが重圧に苦しんだり、どんどん人が辞めていったりするようでは、品質が大きく損なわれて製造コストが膨らんでしまいかねない。
そこで、協力が重要になる。ホンダからの押しつけは一切なく、あらゆることが交渉で決められる。協力とは当然、双方向のものだからだ。ホンダは、サプライヤーが生産性・品質・収益性をさらにアップできるよう支援しているほか、どうすれば自社の工程を改善できるか、サプライヤーから提案してもらうようにしている。サプライヤーから寄せられた多くの改善案のなかから、これはというものを取り入れた結果、アコードの製造コストを21.3パーセント削減できた例もある。