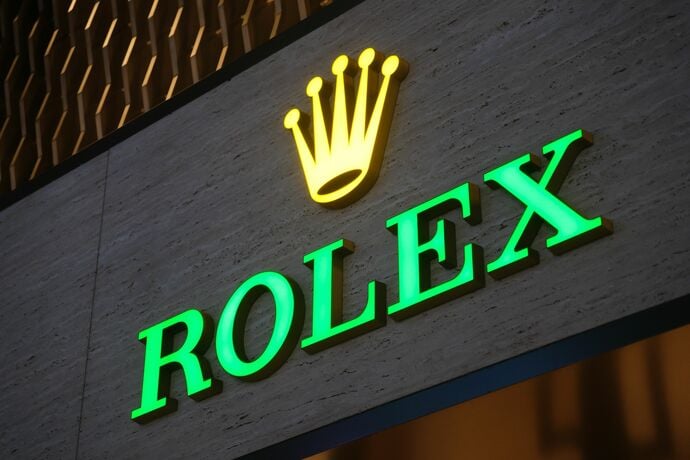同志社大学 学長の植木朝子氏(撮影:栗山主税)
同志社大学 学長の植木朝子氏(撮影:栗山主税)
政府は2023年6月に「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)」の原案を示し、2030年までに大企業の女性役員を30%以上にするという努力義務を掲げている。女性の管理職への登用は、企業の姿勢を示す指針の一つともいえるようになった。
では教育機関の場ではどうだろうか。学生たちの学習・研究環境、教職員の労働環境は多様化しているのだろうか。
同志社大学の植木朝子学長は、「ダイバーシティの推進は教育機関の使命」と語る。同志社大学が考える「ダイバーシティ」とはどのようなものか。男女問わず働きやすくなるための環境づくりに必要なこととは何か。植木学長に話を聞いた。
ダイバーシティの推進は教育機関としての指命
――同志社大学では、これまでもダイバーシティ推進に取り組まれてきましたが、2020年度に「ダイバーシティ推進宣言」を制定されました。どのような狙いで制定したのでしょうか。
 植木 朝子/同志社大学 学長
植木 朝子/同志社大学 学長博士(人文科学)。1990年3月お茶の水女子大学文教育学部卒業。1992年同大学大学院人文科学研究科修士課程修了。1995年同人間文化研究科博士課程を単位取得退学し、お茶の水女子大学助手に。1996年十文字学園女子短期大学文学科専任講師。同助教授、十文字学園女子大学社会情報学部助教授を経て、2005年同志社大学文学部国文学科助教授。2007年同教授、大学院文学研究科教授。同志社大学文学部長、同大学副学長、教育支援機構長を歴任し、2020年4月より現職。専門は中世歌謡。
植木朝子氏(以下敬称略) 本学の創立者である新島襄が「諸君ヨ、人一人ハ大切ナリ」という言葉を残しています。私たちはその言葉を大事にしていますし、もともと同志社という学校は、多様な人を受け入れて共存していくという今のダイバーシティ&インクルージョンという考え方が根付いている学校なのです。
しかし改めてそれを明確な形で学内外に発信したいという思いがあり、「ダイバーシティ推進宣言」を出しました。自分と異なる価値観をもっている人や、違う背景をもっている他者を理解して、共生共存していく中でその違いを新たな創造へ導く力をもった人を養成するという、教育機関としての使命を明確に示したものが「ダイバーシティ推進宣言」です。
――宣言を制定されたのは、植木学長が就任されて間もなくでした。なぜこのタイミングだったのでしょう。
植木 本学は特に障がい学生支援についてはかなり先進的に取り組んできました。しかしジェンダー・ギャップの問題や多様な性的指向、性自認に関しては、大学の施策の中心に据えて考えるということはなかったので、早く対応すべきと考えました。
これは私の個人的な体験になりますが、今から10年ほど前に出会った大学院生のことが心に残っています。その学生さんは真面目な人でしたが、ある時から大学に出て来なくなったのです。どうしたのと聞いてみると、その理由を泣きながら話してくれました。同性の友達に恋心を打ち明けたら、手ひどく拒絶されただけでなく、周囲の学生に言いふらされてしまったというのです。学生さんは結局退学してしまいましたが、私には慰めるだけで何もできなかったという後悔が残りました。
本学のダイバーシティ推進においては、「SOGI(性的指向・性自認)理解・啓発」を一つの柱にしています。周囲の学生の理解が進んでいたら、その学生さんは退学せずに済んだかもしれません。教育機関としては、直接の支援はもちろんのこと、教育や啓発が非常に大事なことだと思っています。自分と感情的には同調できない、共感できない人が何を考えているのかを理解しようとするのは、知的な作業であり、知識も必要なので、学生さんにはしっかりと学んでほしいです。