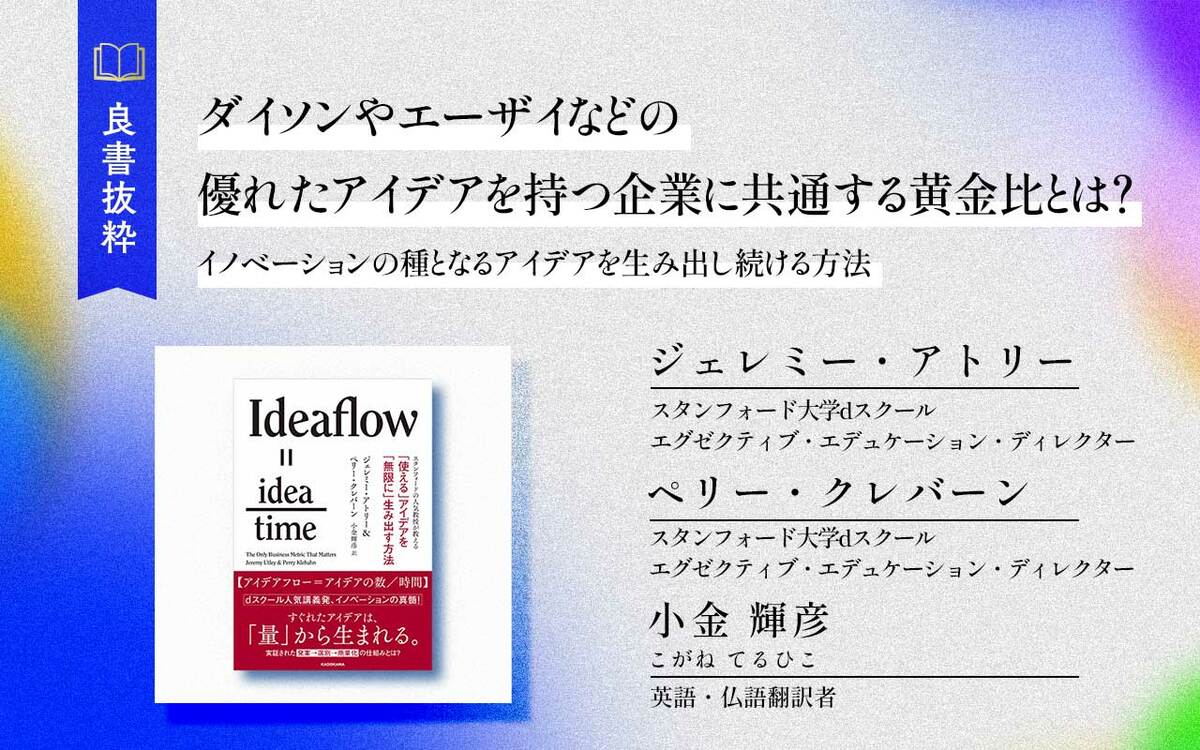
できることなら手間や時間をかけずに、質の高いアイデアを手に入れたいものだ。だが、世界の名だたる成功企業においては、イノベーションを生み出すために、あえてアイデアの質よりも重視している要素があるという。一体何なのか。
本連載では、デザイン思考のパイオニアであるスタンフォード大学d.schoolで、シリコンバレーの起業家やフォーチュン500企業の経営者らを指導してきた教授が、創造性を刺激し、無数のアイデアを生み出し、イノベーションを促す真髄を余すところなく解き明かす。第4回は、イギリスの家電大手ダイソンほか、成功企業がアイデアを生み出す際に共通する独特のパターンと、止めどなくアイデアをあふれ出させるテクニックを解説する。
(*)当連載は『スタンフォードの人気教授が教える 「使える」アイデアを「無限に」生み出す方法』(ジェレミー・アトリー、ペリー・クレバーン著、小金 輝彦訳/KADOKAWA)から一部を抜粋・再編集したものです。
<連載ラインアップ>
■第1回 パタゴニアが冒した大失敗、企業にとってなぜアイデアが死活問題なのか?
■第2回 アマゾンを成功に導いたのは、運でも才能でもなく「アイデアフロー」
■第3回 スタンフォードd.school教授が辿り着いた、究極のアイデア発想法とは
■第4回 ダイソンやエーザイなどの優れたアイデアを持つ企業に共通する黄金比とは?(本稿)
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
アイデア比率 「2000対1」の法則
一般的な意見に反し、成功を収めた創造者は、すばらしいアイデアを思いついた人ばかりではない。最も優秀な人が考えたどんなアイデアも、その部屋にいる誰かほかの人が考えたアイデアと、実現性や興味深さの点でさほど変わらないことが多い。心理学教授のディーン・キース・サイモントンが提唱した「イコール・オッズ(同率)の法則」は、誰かの創造的な成功の数は、創造物の総数と相関すると述べている(5)。
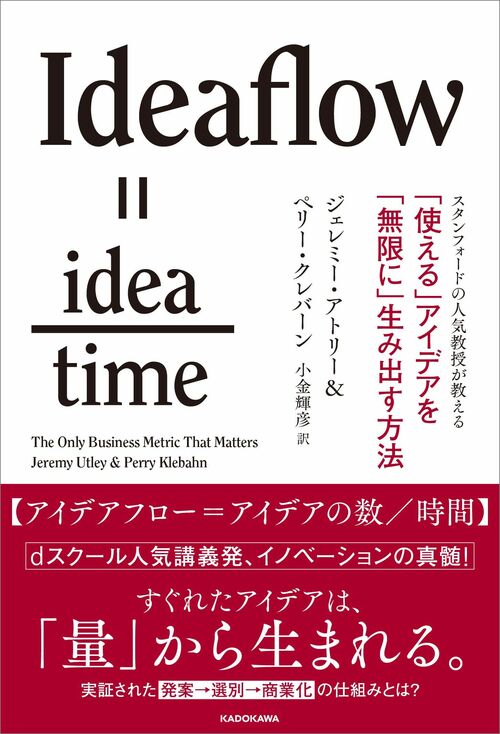 『スタンフォードの人気教授が教える 「使える」アイデアを「無限に」生み出す方法』(KADOKAWA)
『スタンフォードの人気教授が教える 「使える」アイデアを「無限に」生み出す方法』(KADOKAWA)拡大画像表示
5 Dean Keith Simonton, “Creative Productivity: A Predictive and Explanatory Model of Career Trajectories and Landmarks,” Psychological Review 104, no. 1 (1997): 66–89
交響曲が多く作曲されるほど、偉大な交響曲が多く生まれる。数学的定理の数が増えるほど、画期的な定理が増える。イコール・オッズの法則は、驚くほど幅広い分野にあてはまる。
サイモントンの研究や私たちの経験において、勝者を際立たせているのは「量」だ。世界に通用する創造者は、平均よりも多くの可能性を定期的に生み出している。よりよい結果を望むなら、それを達成するために、あなたのイノベーションの漏斗(ファネル)を大量のアイデアで満たさなければならない。同じくらい重要なのは、できるだけ幅広い可能性を網羅するようにアイデアを収集することだ。
では、どれだけあれば「十分」なのか? すぐれたアイデアに行きつくには、実際にいくつのアイデアが必要なのだろうか? 私たちの経験では、答えは約2000だ。そう、2にゼロが3つ、つまり2000対1の割合だ。私たちはこれを「アイデア比率」と呼んでいる。
誤解しないでほしい。私たちは、部屋に入ってその場で2000のアイデアを考えなさいといっているわけではない。創造性は反復的なものだ。2000対1の比率で解決策が生まれるというのは、イノベーションのパイプラインに沿った、すべての組み合わせやバリエーションや改良版を数に入れての話だ。
アイデア比率は、私たちの同僚であるボブ・サットンの功績といえる。ボブが最初にそのエビデンスを目にしたのは、デザインコンサルタント会社のIDEO(アイデオ)での仕事においてだった。ある玩具メーカーと一緒に働いてみて、この会社の開発者たちが4000もの製品のアイデアを検討したうえで、200の試作モデルに到達したことを知ったのだ(6)。
6 Robert I. Sutton, Weird Ideas That Work: 11½ Practices for Promoting, Managing, and Sustaining Innovation, illustrated ed. (New York: Free Press, 2002). (邦題は『なぜ、この人は次々と「いいアイデア」が出せるのか―〝儲け〞を生み出す12の〝アイデア工場〞!』ロバート・サットン著、三笠書房、2002年)
当然ながら、そのうち商品化されたのは1ダースかそこらで、まともに成功したのは2つか3つだった。そして、ひとたびこのパターンに気がつくと、創造者が着実に大きな成功を収めているところでは、必ずそれが目につくようになったのだ。








