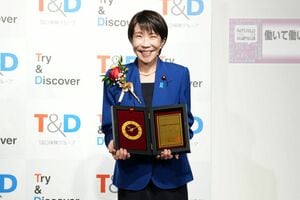大学設置基準の「大綱化」で、大学の一般教育はどのように変わったのか。
大学設置基準の「大綱化」で、大学の一般教育はどのように変わったのか。
(児美川 孝一郎:教育学者、法政大学キャリアデザイン学部教授)
前回の記事(http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56049)では、戦後日本の大学が、なぜ「教養課程」と「専門課程」を併せ持つ教育課程を採用することになったのか、その経緯を明らかにすると同時に、実際に各大学においてスタートした教養課程の教育(一般教育)が、その後、必ずしも所期の目的を達成したわけではなかったという実態とその原因について触れた。
それでは、その後、大学における一般教育(教養教育)は、どのような命運を辿ることになるのか。
設置基準の「大綱化」前夜
大きな変化が訪れるのは、1991年の大学設置基準の改訂(いわゆる「大綱化」)以降のことであるが、なぜ「大綱化」が実施されたのか。ここでは、その前段の動きから見ておきたい。
1984年に発足した臨時教育審議会(臨教審)は、明治初期、戦後改革期に続く「第三の教育改革」を標榜しつつ、日本の教育全体に改革のメスを入れることを目指していたが、そこでは当初から日本の高等教育を「個性化、多様化、高度化」し、「社会との連携、開放を進め」(「最終答申」1987年)ていく必要があるという課題意識が持たれていた。
教養課程の教育に関しても、「一般教育は・・・大学教育にとって重要な要素である」としつつも、「これまでの我が国の大学の一般教育は、理念においても、内容においても十分であるとはいえず、しばしば一般教育無用論さえ聞かれる」という認識を示し、「一般教育と専門教育を相対立するものとしてとらえる通念を打破し、両者を密接に結び付け、学部教育としての整合性を図る」(「第二次答申」1986年)必要があると主張していた。
おそらく、ここにあるような認識は、臨教審のみに突出したものではなく、当時の大学教育界の内外で共有されていたものであろう。結局、臨教審自体は、一般教育の改革を含む大学改革を進めていくためには、大学設置基準の改善が必要であると繰り返し主張はしたものの、その具体化の作業は、自らが創設を提言した「ユニバーシティ・カウンシル(大学審議会-仮称)」(「第二次答申」1986年)に委ねることになった。