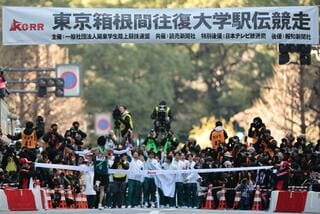日本における氷づくりの歴史と、その歴史の先端にある技術を前後篇にわたり取り上げている。
前篇では、明治時代までの電気の使われなかった時代、人びとがいかに“夏の氷”を珍重してきたか、その歴史をたどった。毎夏、氷は貴重な献上品の1つとして、地方の氷室から中央の権力者に運ばれてきたのだ。そんな氷が「お氷さま」と呼ばれる時代もあった。
現代に通じるような製氷技術が本格的に使われだしたのは、明治時代中期からだ。製氷機の導入により、技術的には“夏の氷”をどこででもつくれるようになった。
それから110年ほど。いまや日本の製氷技術は世界一と評価されるまで高まっているという。氷の質の高さとは、透明であることや、空気の含有量が少ないことなどが要素となる。実際、日本の製氷機にどのような技術開発がなされているのだろうか。
後篇では、茨城県水戸市で製氷機器を製造している今関靖将氏に話を聞こう。今関氏は「イマセキ氷技術研究室」という私立研究所を立ち上げ、氷の科学を氷づくりの技術に生かしている。
明治時代から「135キログラム」
製氷機でつくる角氷の重量は135キログラム。これは、日本全国の製氷業で通じる、いわば氷の標準的質量だ。
「明治時代に氷の技術が入ってきたとき、300ポンドの氷がつくられました。日本の単位では約36貫、つまり135キロ程。実は、この重さの基準が、ほぼ変わらずに続いてきたのです」
今関冷機製氷販売社長の今関靖将氏はそう説明してくれた。同社は茨城県水戸市で透明純氷装置などの製氷関連機器を製造し、氷メーカーなどに販売している。また、イマセキ氷技術研究室も立ち上げ、氷づくりの研究も行っている。