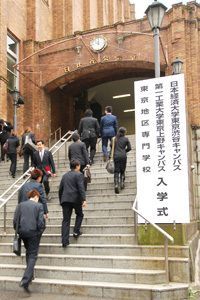東京大学駒場キャンパスの小ホール。観客が一人もいないのに義太夫節が静かに流れ、文楽の上演が始まった。演目は、仙台藩伊達家のお家騒動を題材とする伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)。忠義の乳母の政岡(まさおか)が、わが子を身代わりにしてまで幼い主君の鶴千代(つるちよ)を守る。気丈な政岡とはいえ、愛息を失った悲しみで心は千々に乱れる。「わが子の死骸抱き上げ、耐へ耐へし悲しさを一度にわつと溜涙」・・・。人形の演じる政岡が本物の涙を流すことはなくても、手や顔の動きそして全身から、母の嘆きが切なく伝わってくる。

主君身代わりの我が子悲しむ
極めて制約された動きの中で、なぜ文楽人形は人間そっくりの感情を表現できるのか。
文楽の舞台を観た人が必ず抱く疑問を、東大大学院総合文化研究科の植田一博准教授(認知科学)と慶応義塾大学理工学部機械工学科の森田寿郎専任講師(ロボット工学)が最先端科学に基づき、解き明かそうとしている。東大での「上演」はデータ収集の一環。吉田勘弥(よしだ・かんや)さんら文楽協会の人形遣い3人が、本物の舞台さながらの熱演で実験に協力した。
徳島県の人形作家に制作してもらった特製の人形は、肘や首など9カ所に磁気センサーを内蔵。動きを3次元で把握するから、正確な位置測定が可能だ。さらに3人の人形遣いに呼吸センサーを装着してもらい、人形の動きと呼吸のタイミングを計測。人形左手の動きを担当する「左遣い」には、目の動きを追尾するアイカメラを装着し、演技中の視線データを測る。
今後、数カ月かけてデータを解析し、文楽人形の動きの特徴や基本動作にこめられた感情のパラメーターを抽出するという。
「型」に凝縮する「人間らしさ」
「人間らしさ」とは何か。植田准教授と森田専任講師の共同研究の出発点はここにある。
数十年前のロボットは、立方体や長方体など単純な形の組み合わせで、「カクカク」とした単純な動きしかできなかった。その後、ロボットの体のバランスや見た目が人体に近づき、複雑な動きを身につけながら、「人間らしさ」を徐々に獲得してきた。
最近では人間の皮膚に色と感触がそっくりの素材や、関節を精巧に再現したパーツが開発され、「人間そっくりロボット」も登場している。しかし、こうしたアンドロイド(人造人間)に対しては、親しみより不気味さを感じる人が多いのではないだろうか。