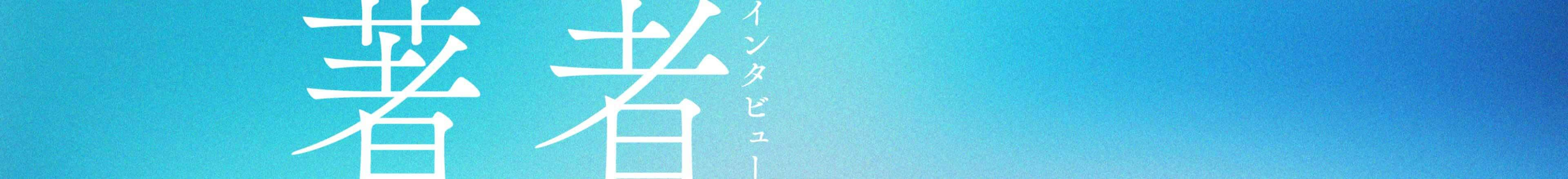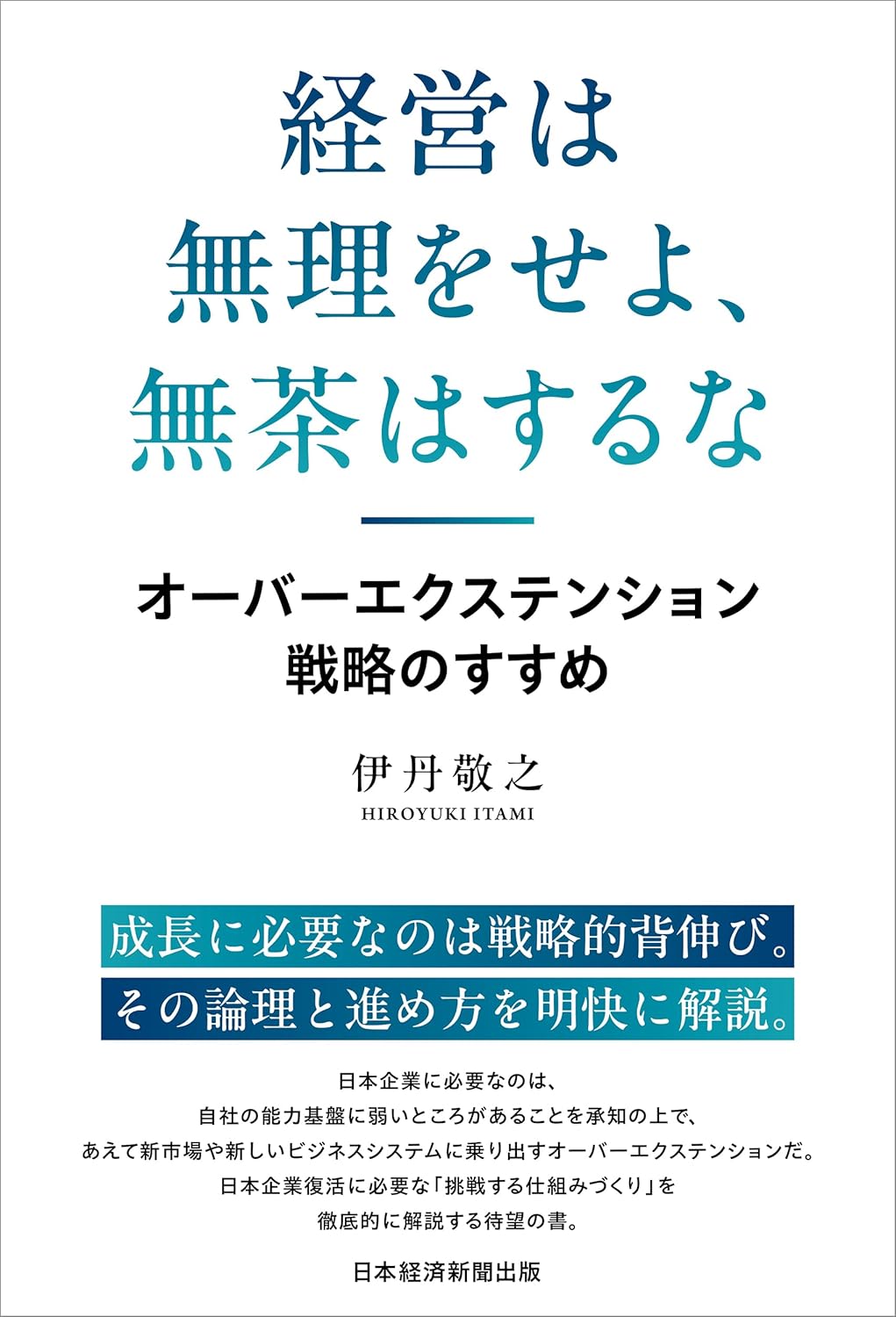出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
多くの日本企業は「失われた30年」の間に「無理」をしなくなってしまった──。そう語るのは、2025年2月に『経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ』(日本経済新聞出版)を出版した一橋大学名誉教授の伊丹敬之氏だ。伊丹氏は、過去50年以上にわたって日本企業を観察してきた経験を踏まえ、戦略的な背伸びによって企業の能力基盤の拡大を狙う「オーバーエクステンション」の必要性を力説する。成長の踊り場を迎えた日本企業に求められる戦略論、そして、オーバーエクステンション戦略によって欧米の競合を凌駕する競争力を手に入れたトヨタの事例について、同氏に聞いた。
多くの日本企業が無理をしなくなった理由
──著書『経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ』では、日本企業が「失われた30年」を脱するための戦略として、企業の成長の踊り場で自らをエクステンド(大きく拡張)する「オーバーエクステンション」を提唱しています。オーバーエクステンションとは、どのような概念なのでしょうか。
伊丹敬之氏(以下敬称略) オーバーエクステンションとは、自社に十分な能力基盤がないことを承知の上で、あえて新しい事業活動に挑戦することです。実力が不十分なまま挑むことになるため、当然ながら現場は大きな困難に直面します。しかし、その過程で試行錯誤を重ね、学習を続けることによって、最終的には自社の能力基盤を大きく高めることが狙いです。
人が困難を乗り越えて成長するように、企業もまた、自ら厳しい状況を意図的につくり出すことで飛躍を図ろうとします。「艱難汝(かんなんなんじ)を玉にす」ということわざを経営に採り入れる戦略、と考えると分かりやすいのではないでしょうか。
現代において、オーバーエクステンションに挑む企業がなくなったわけではありません。しかし、かつてと比べるとその数は明らかに減少しています。その最大の理由は、「バブル崩壊の後遺症」が今も残っていることです。バブル崩壊後、日本の金融システムは大混乱に陥り、日本経済は10年間ほど低迷しました。この時期に企業として無理をしないのは自然なことです。
しかし、金融システムが正常化しても、日本企業は昔のようにオーバーエクステンションすることはありませんでした。ここに日本企業が抱える課題の本質があります。