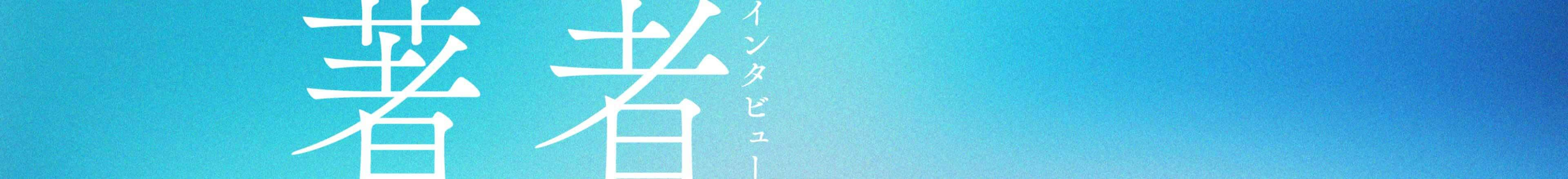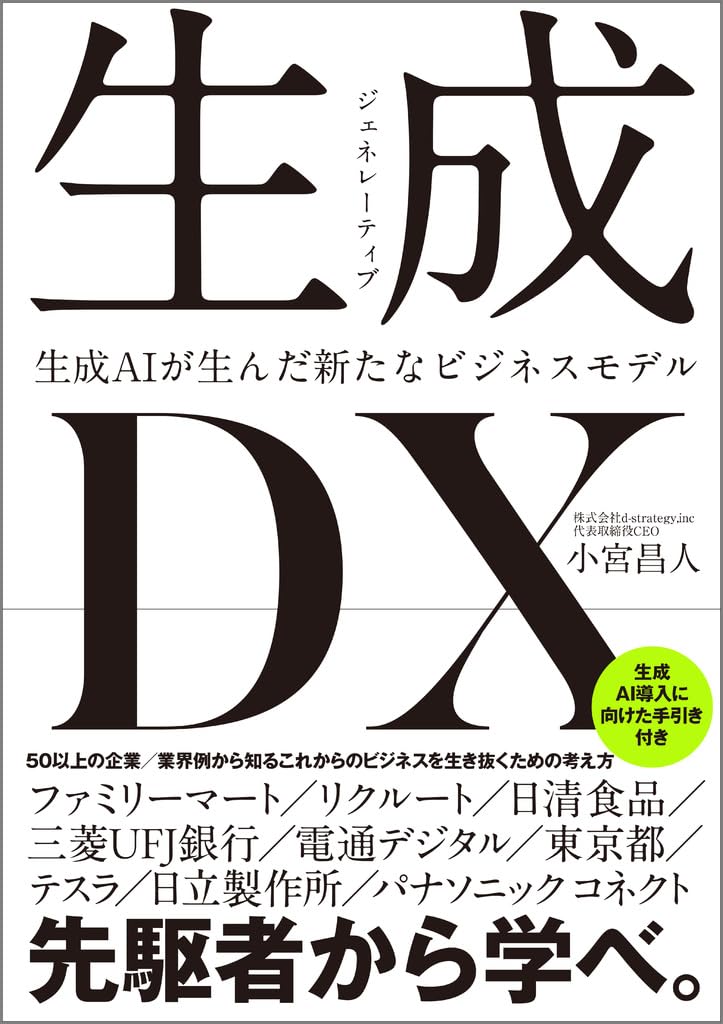出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
急速な進化を遂げる生成AIは、ものづくりの現場でも無視できない存在になりつつある。今後、製造業各社はいかにして生成AIをビジネスに採り入れるべきなのだろうか――。2024年11月に著書『生成<ジェネレーティブ>DX 生成AIが生んだ新たなビジネスモデル』(SBクリエイティブ)を出版した、企業のDX・ビジネス支援を手掛けるd-strategy,inc 代表取締役の小宮昌人氏に、製造業における生成AI活用の最新動向と、日本企業が進むべき方向性について話を聞いた。
独シーメンスが図る「製造ラインの革新」
――著書『生成<ジェネレーティブ>DX 生成AIが生んだ新たなビジネスモデル』では、ものづくりの分野における生成AI活用として、製造ラインの在り方を変えようとする独シーメンスの取り組みを解説しています。同社の取り組みについて、どのような点に注目すべきでしょうか。
小宮昌人氏(以下敬称略) 製造業を支えるデジタルソリューションを展開するシーメンスは「自律型生産工場」をコンセプトに、生成AIを活用してフレキシビリティ(柔軟性)を担保した仕組みづくりを提示しています。
従来型の製造業では、いくつかの設計パターンから顧客が求めるものに合わせて生産ラインを設計して高速生産する、というアプローチが一般的でした。そして、従来の産業用ロボットや機器は、同じ動作を高速で繰り返すことは得意とする一方で、状況に応じて動作を変えることは不得意でした。
しかし、生成AIとロボットや機器が融合することにより、小さなタスクモジュールを組み合わせ、状況に応じて最適な生産方式を切り替えることが可能になります。これにより、高度な現場力を持ち合わせていなくても、生産ラインの段取り替えを柔軟に行えるようになり、多品種少量生産やマスカスタマイゼーションが実現しやすくなっています。
大きな工数がかかっていた製造ラインの変更やカスタマイズが効率化されるようになったことで、ものづくりの在り方は今後大きく変わるでしょう。
このような、製造ラインのフレキシビリティ向上に加えて、もう1つ、製造業において注目されているのが、設計の自動化を意味する「ジェネレーティブデザイン(Generative Design)」です。