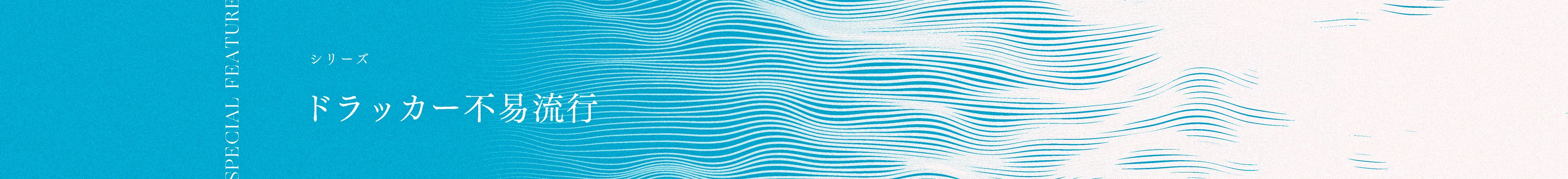野中郁次郎氏:撮影 木賣美紀(左)、写真提供:共同通信社(右)
野中郁次郎氏:撮影 木賣美紀(左)、写真提供:共同通信社(右)
『マネジメント』(ダイヤモンド社)をはじめ、2005年に亡くなるまでに、39冊に及ぶ本を著し、多くの日本の経営者に影響を与えた経営学の巨人ドラッカー。本連載ではドラッカー学会共同代表の井坂康志氏が、変化の早い時代にこそ大切にしたいドラッカーが説いた「不易」の思考を、将来の「イノベーション」につなげる視点で解説する。
今回は、累計100万部を突破したロングセラー『失敗の本質』と、ドラッカーのマネジメント論の共通点から、組織におけるフィードバックの重要性について考察する。
「読み込む」価値のある本
歴史家の半藤一利氏は、日本近代には「40年ごとのサイクル」があると指摘している。まず、開国(1865年)から日露戦争の勝利(1905年)までが40年。その後、敗戦(1945年)までがさらに40年である。
敗戦後、日本は占領期を経て、1952年にサンフランシスコ講和条約の発効により主権を回復し、戦後復興と高度経済成長を遂げ、約40年をかけて経済大国へと成長した。しかし、1992年のバブル崩壊をきっかけに再び低迷期に入り、現在はその40年周期の終盤にあると考えられる。
そして、2025年は敗戦からちょうど80年目にあたり、40年という周期を経て、再び節目に差しかかっていると言えるだろう。
敗戦によって再出発した日本は、高度経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国にまで登り詰めたが、1990年代以降の「失われた30年」を経て、今や経済力・技術力・国際的影響力において明らかな衰退過程にある。
『失敗の本質』(戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎著/中央公論新社)は、累計100万部を超え、多くの人が書棚に1冊は保蔵している名著だ。経営のためだけではない。あらゆる組織、あらゆる人間の営みにおいて、失敗と向き合い、そこから何を学びとるのかという、問いかけがそこにある。
2025年は、敗戦から80年という節目の年である。その年に『失敗の本質』の主著者の一人である野中郁次郎氏が逝去された。組織論の泰斗であり、「知識創造企業」で世界に知られた野中氏の渾身(こんしん)の問いに、今一度耳を傾けてみたい。
同氏の問いの中核を私なりに要約すれば次のようになる。
「われわれはフィールドと時代を変えて、またあの戦いをしているのではあるまいか」
今私たちはこの書を読み返さなければならない。これは過去の戦争についての本ではない。現代の日本を読み解くための手がかりである。