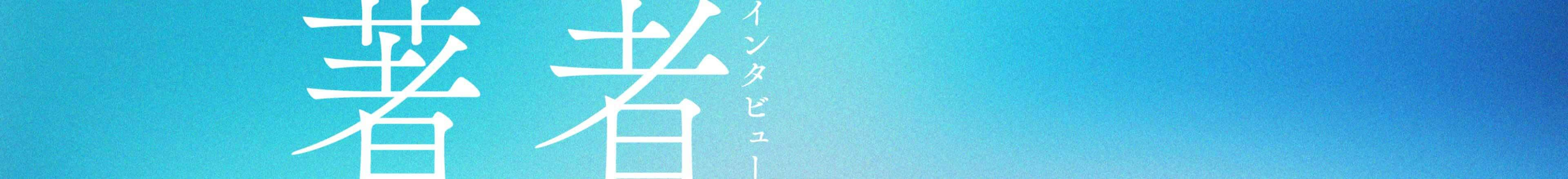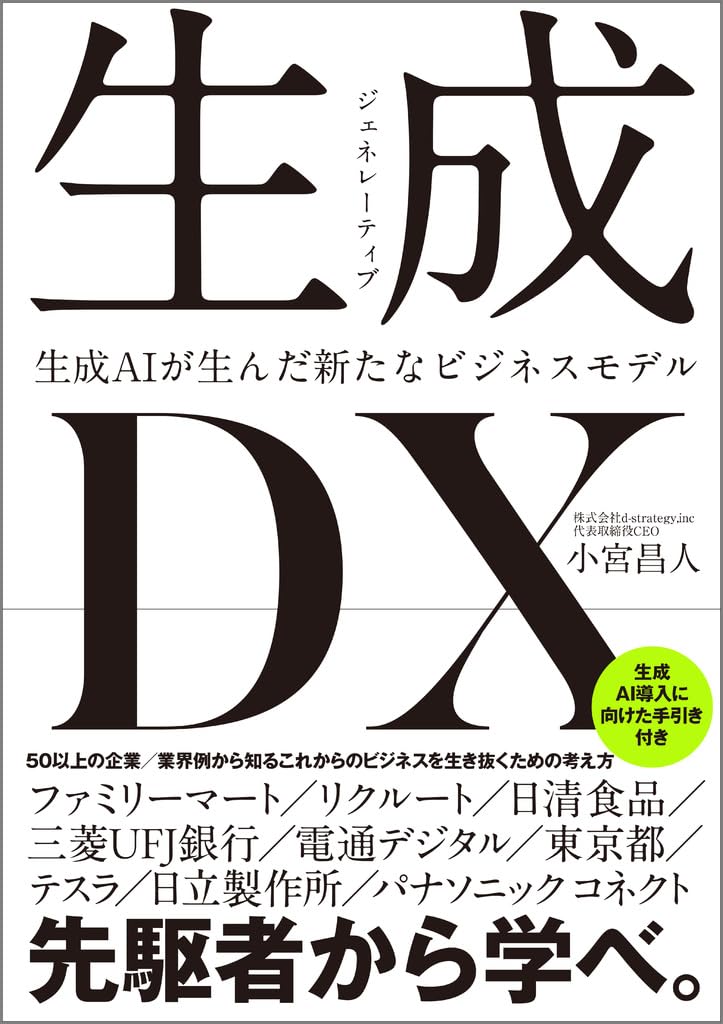出所:共同通信イメージズ
出所:共同通信イメージズ
ビジネスの現場で、文章や画像の生成にとどまらない幅広い活用方法が模索されている生成AI。その可能性を競争力へと転換させるには、どのような視点が必要だろうか――。こうした問いについて「生成AIの真価は、自社独自のデータやノウハウを組み合わせることで発揮される」と語るのは、企業のDX・ビジネス支援を手掛けるd-strategy,inc代表取締役の小宮昌人氏だ。2024年11月に著書『生成<ジェネレーティブ>DX 生成AIが生んだ新たなビジネスモデル』(SBクリエイティブ)を出版した小宮氏に、企業における生成AI活用の具体例について聞いた。
生成AI活用のかぎは「社内データの活用」
――著書『生成<ジェネレーティブ>DX 生成AIが生んだ新たなビジネスモデル』では、文章の要約やプログラミング、画像・動画生成といった用途にとどまらない「より踏み込んだ生成AI活用」の重要性を述べています。その1つが「自社や産業データの学習」とのことですが、具体的にどのようなアプローチがあるのでしょうか。
小宮昌人氏(以下敬称略) 生成AIの可能性を引き出すためのアプローチとしては、2つの方法があります。1つ目は「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」と呼ばれる手法です。RAGは、生成AIが元々備えている知識だけでなく、社内文書やマニュアル、報告書、IoTデータなど、自社のコアとなるノウハウが含まれたデータを参照させながら回答を生成する方法です。
2つ目は「ファインチューニング」という手法です。生成AIの中でも大規模言語モデル(LLM)は自然言語処理に特化した技術を指しますが、そのLLM自体を事後学習データでカスタマイズし、自社が求める目的に合わせて最適化する方法がファインチューニングです。
例えば、英語中心の学習データに日本語を追加学習したり、広範囲なデータを中心に扱うLLMに対して用途に応じてロボットの制御コードや、法務や財務といった特定分野の専門知識を追加学習させたり、という具合です。
そもそも、生成AIの活用には「3つの段階」があると定義しています。第一段階(生成AI活用1.0)は、OpenAIのChatGPTをはじめとする既存の生成AIを単独で活用する方法です。これらの生成AIは既に多くの知識を有しており、弁護士資格の司法試験や医師試験を突破できるといわれており、様々な用途に活用が拡がっています。
続いて、第二段階(生成AI活用2.0)では、現場のノウハウや熟練技能者の経験則といった「暗黙知」の体系化を含めた自社や産業のノウハウ、オペレーションと生成AIの組み合わせを通じたオペレーション変革を目指し、第三段階(生成AI活用3.0)は、生成AI活用による新規サービス・ソリューションの創出などビジネスモデルの変革や、社会・環境・顧客価値の創出を目指します。前述のRAGやファインチューニングは、主に生成AI活用2.0に踏み込む際に必須となるアプローチです。