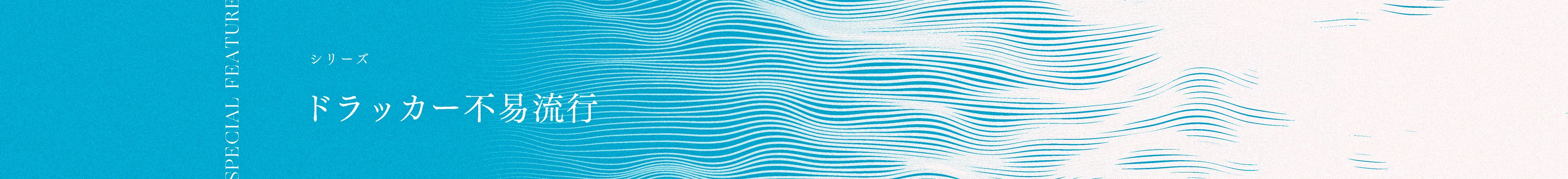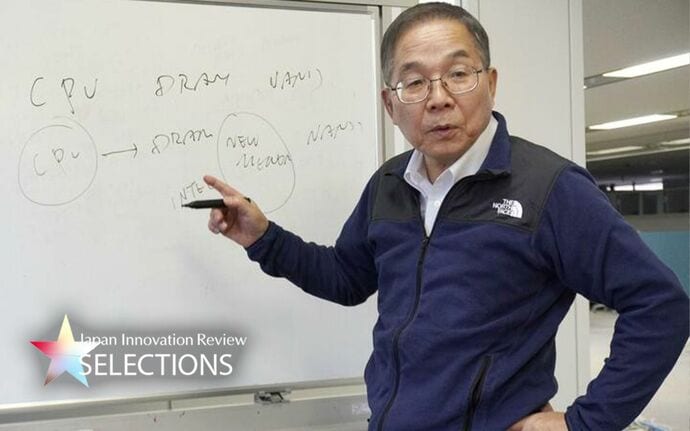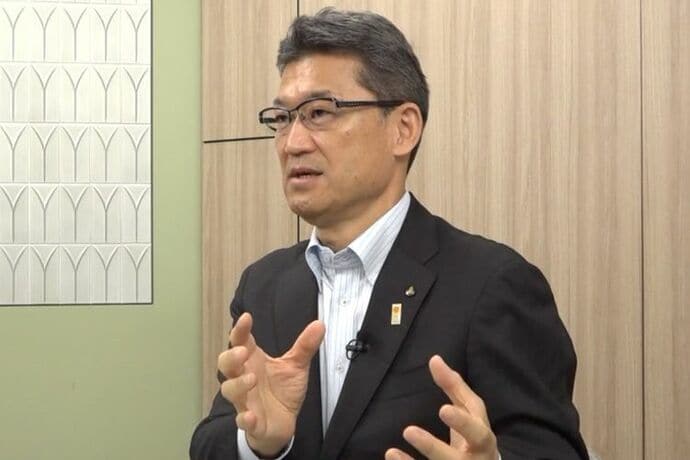ドラッカーの晩年の弟子ボブ・ビュフォードは、アメリカンフットボールの試合になぞらえ、「第二の人生」を「セカンドハーフ(後半戦)」と呼んだ。
ドラッカーの晩年の弟子ボブ・ビュフォードは、アメリカンフットボールの試合になぞらえ、「第二の人生」を「セカンドハーフ(後半戦)」と呼んだ。写真提供:Ross Harried/NurPhoto/共同通信イメージズ
『マネジメント』(ダイヤモンド社)をはじめ、2005年に亡くなるまでに、39冊に及ぶ本を著し、多くの日本の経営者に影響を与えた経営学の巨人ドラッカー。本連載ではドラッカー学会共同代表の井坂康志氏が、変化の早い時代にこそ大切にしたいドラッカーが説いた「不易」の思考を、将来の「イノベーション」につなげる視点で解説する。
連載第5回は、ドラッカーが最晩年まで強い関心を寄せた「人生」のイノベーションを取り上げる。
会社のために生まれてきた人はいない
イノベーションとは製品やサービス等、いわゆるビジネスのみに限定されるものではないし、そうすべきでもない。今回はやや視点を変えて、人間の一生に関わるイノベーションに触れておきたい。
「人生のイノベーション」はドラッカーが最晩年、つまり亡くなる直前まで強い関心を寄せていたテーマでもある。彼が『現代の経営』(ダイヤモンド社)で語った、「会社勤めをするために生まれてきた人間など一人もいない」という一文。何か胸に迫るものがないだろうか。
現代の企業社会においては、仕事と自己実現が一衣帯水になりがちな環境にある。多くが昇進や収入を追い求める。地位や給与が増すにつれて、自身の価値観や理想を犠牲にして、組織に迎合して生きてしまう。しかも大半の場合、自分が進んで特定の価値観の奴隷になっている事実に気付いてさえいない。
若いうちはいい。40歳くらいまでは、社会である程度確固たる地位を築くのに全てのエネルギーと時間を注がなければならない一時期だろう。
社会に出て、家族を持ち、地位を得ていく。人生が50年だった頃にはそれでよかったと思う。平均寿命が60年に達していなかった戦後間もなくは、終身雇用とは文字通りの「終身」だった。
だが、人生100年という言葉は、もはや非現実的な理想ではなくなった。現在の日本では100歳以上の方々が約10万人に上る。40歳、50歳の方々を見ても外見も考え方も若々しい。中には、一昔前の若者を思わせるほど元気な方もいる。平均寿命から見てもようやく半分を越えたばかりだ。
ドラッカーが人生のイノベーションについて語る内容は、実に素朴で率直だ。「人生は二つある」という考え方がそれである。これは案外知られていない。