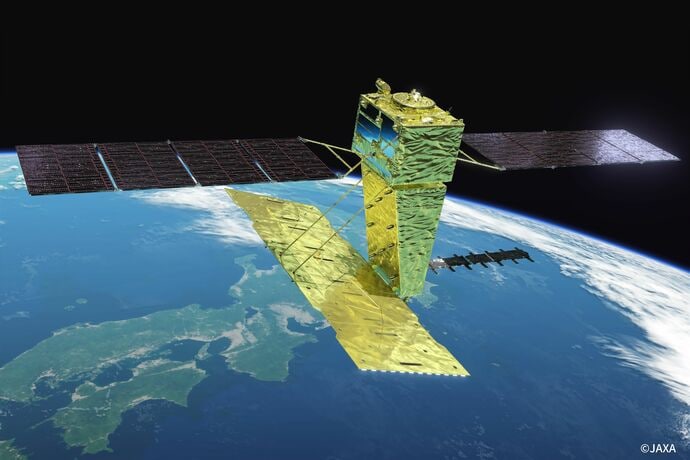2019年、「CRISPR-Cas9」を利用してゲノム編集した世界初のクローンサルが中国で誕生した。
2019年、「CRISPR-Cas9」を利用してゲノム編集した世界初のクローンサルが中国で誕生した。写真提供:新華社/共同通信イメージズ
大企業の経営幹部たちが学び始め、ビジネスパーソンの間で注目が高まるリベラルアーツ(教養)。グローバル化やデジタル化が進み、変化のスピードと複雑性が増す世界で起こるさまざまな事柄に対処するために、歴史や哲学なども踏まえた本質的な判断がリーダーに必要とされている。
本連載では、『世界のエリートが学んでいる教養書 必読100冊を1冊にまとめてみた』(KADOKAWA)の著書があるマーケティング戦略コンサルタント、ビジネス書作家の永井孝尚氏が、西洋哲学からエンジニアリングまで幅広い分野の教養について、日々のビジネスと関連付けて解説する。
第7回目は『ソクラテスの弁明』、最新遺伝子工学の世界を描いた『CRISPR』をテキストに、ゲノム編集、超人工知能など「神の領域のテクノロジー」に人類が向き合うために、なぜ教養が欠かせないかを考える。
教養の世界と最新テクノロジーの世界は、深くつながっている
テクノロジーの進化が加速している。人類は既に生物の遺伝子を自在に編集して生物を作り替える技術を手に入れている。人知を超える超人工知能(ASI)の登場間近と言われている。まさに「神の領域のテクノロジー」を手に入れつつある人類は、どうすべきなのか?
教養を学んでいくと、問題の本質が見えるようになる。第7回目は、その一例としてソクラテス哲学と最新テクノロジーを取り上げよう。『ソクラテスの弁明』(プラトン著、納富信留訳、光文社古典新訳文庫)と、最新遺伝子工学の世界を描いた『CRISPR』(ジェニファー・ダウドナ/サミュエル・スターンバーグ著、櫻井祐子訳、文藝春秋)をテキストに、このテーマを考えていく。
ソクラテス哲学は、第1回「ソクラテス哲学を学ぶと、なぜ『心理的安全性』が理解できるのか?」で簡単に紹介した。ここでは改めて簡単におさらいしよう(既に知っている人はここを読み飛ばして、次のページから読み進めてほしい)。
ソクラテスは、2400年前の古代ギリシャに生きた哲学者だ。そのソクラテス哲学のエッセンスが凝縮された古典的名著が『ソクラテスの弁明』である。
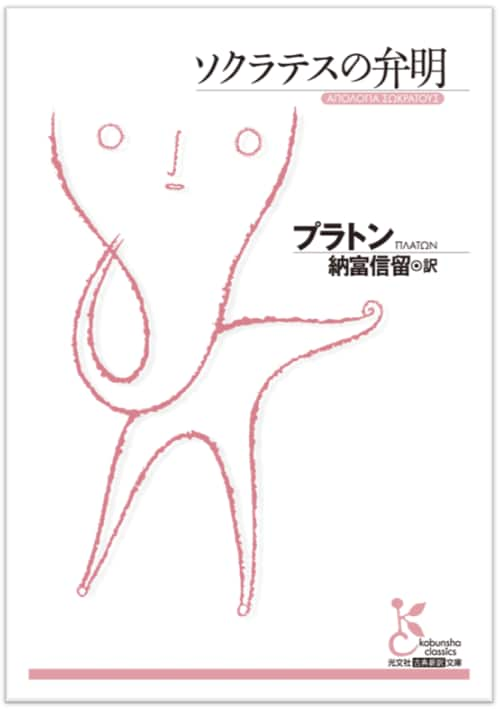 『ソクラテスの弁明』プラトン 納富信留:訳/光文社古典新訳文庫
『ソクラテスの弁明』プラトン 納富信留:訳/光文社古典新訳文庫
ある日、神殿で「神のお告げ」を担当する巫女(みこ)が「ソクラテスより知恵がある者は誰もいない」と言った。すると神を信じていたソクラテスは「俺に知恵なんてないぞ」と真剣に考え込んでしまった。ソクラテスは「本当に神が言う通りなのか」を検証するために、当時の知識人たちと対話を重ねていった。自分より知恵がある人物を見つければ「神が間違いだ」と分かるはず、と考えたのだ。
しかし知識人を自称し「自分はあらゆることを知っている」と公言する人たちは、ソクラテスの問いかけに誰一人まともに答えられなかった。彼らはソクラテスと問答を繰り返すうちに、話のつじつまが合わなくなったり、矛盾が生まれたりして答えに窮して、馬脚を現したのだ。こんな問答を知識人たちと繰り返して、ソクラテスは理解した。
「なるほど。俺は『知らない』と自覚するだけ彼らよりはマシだ。神は正しいのだな」
しかしソクラテスは、面目丸つぶれの知識人たちから逆恨みされ、裁判で訴えられた。その裁判記録が『ソクラテスの弁明』なのだ。
このソクラテスの考えの根本にあるのは「自分は知らない」という「不知の自覚」だ。ソクラテスは「不治の自覚」を出発点に、他者との対話を通じて本当に自分が知っているのかを謙虚に検証し続け、知の探究を行ったのだ。
ところで日本ではソクラテス哲学を「無知の知」と理解する人が多いが、プラトンの本には「無知の知」という言葉はない。「無知の知」は教科書にも掲載されている言葉だが、これは昭和初期にプラトンが流行した時に誤って紹介されたもので、実は間違いだ。「不知の自覚」は「自分が何も知らないことは、(その通り何も知らないと自分は)自覚しています」という意味である。