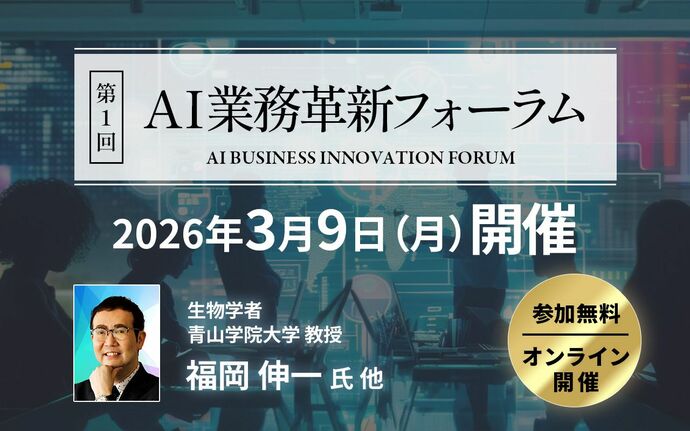写真提供:ZUMA Press/共同通信イメージズ
写真提供:ZUMA Press/共同通信イメージズ
大企業の経営幹部たちが学び始め、ビジネスパーソンの間で注目が高まるリベラルアーツ(教養)。グローバル化やデジタル化が進み、変化のスピードと複雑性が増す世界で起こるさまざまな事柄に対処するために、歴史や哲学なども踏まえた本質的な判断がリーダーに必要とされている。
本連載では、『世界のエリートが学んでいる教養書 必読100冊を1冊にまとめてみた』(KADOKAWA)の著書があるマーケティング戦略コンサルタント、ビジネス書作家の永井孝尚氏が、西洋哲学からエンジニアリングまで幅広い分野の教養について、日々のビジネスと関連付けて解説する。
ヘーゲルの弁証法の本来の意味を解説した前編に続き、後編となる今回は、実は弁証法の力を巧みに操る日本の特徴とエンゲルスがまとめた弁証法の3法則について紹介する。
人間社会は弁証法的に進化していく、と考えたヘーゲル
ヘーゲルが追求したのは、人類の大きな歴史の流れの中で、人間の理性が果たす役割だ。
ヘーゲルに半世紀先立って活躍した哲学者カントは、人間の理性を重視しつつ、人間の理性の限界も考え抜き、著書『純粋理性批判』を書いた。逆にヘーゲルは、人間の理性を絶対的に信頼した。前編で紹介したヘーゲルを中心に海外哲学者の翻訳も多く手がける長谷川宏氏は、著書でこう述べている。
「理性的な思考を働かせることで、わたしたちは現実の奥の奥まで認識することができる、とヘーゲルはいいたいのだ」。
ヘーゲルが生きた18世紀末〜19世紀初頭は、教会や貴族階級が権力を握る中世欧州の封建社会が崩壊して人々が「人間は自由だ」と気付き、神や主君は否定され、個人が「個」を主張し始めた時代だ。こんな時代を生きた彼らにとって自由は「与えられるモノ」でなく、「闘って獲得するモノ」だ。
だから真正面から向かい合って、話し合う。目的は一致点を見つけることではなく、双方の明確な対立と緊張を大前提に、意見の相違はあるものとして明確に違いを述べ、どちらが理にかない、真理に近いかを議論し、真理に一歩でも近づくこと。そして矛盾を叩きつけて決闘し、否定に否定を重ねる。これがヘーゲルの弁証法の背景にある。
このプロセスは、いわゆる「和を以て貴し」が身上の日本人は慣れていないし、結構つらい。日本人は意見の違いがあると、何とか双方の一致点を見つけて解決しようとする。「ヘーゲルの弁証法は正反合」という誤解も、「一致点を探す」という発想が心地よいが故の誤解かもしれない(ただ、この点は、後ほど「弁証法的に」改めて検証したい)。
ヘーゲルの弁証法は「一致点を探す」などという生ぬるい「和」の世界ではない。むしろ「つぼみは花によって否定される」というように、自分の存在が危うくなるほどの否定を重ねて真理を探求する、生死を懸けた決闘だ。このことは私自身、IBMの社員だった時代に欧米人との仕事で身に染みて実感した。
20代の頃、グローバルコミュニケーションを何も知らない私は、日本流に相手の立場を察して譲歩し、一方で相手からの配慮もひそかに期待した。これが実に甘かった。
こちらが価値を提供できなければ、譲歩しても奪われる一方。日本流に控えめな者は「ディールできない無能なやつ」、主張なき者は「真理追究に興味がない怠惰な人間」と思われるだけだった。
このことを身に染みて学んだ私は、海外との対話の場では、自分の人格を改造した。徹底的にロジックを磨き、論理立ててこちらの利害を主張する。優位に立った時点で、ほんの少し譲歩する。この方法は日本では「智に働けば、角が立つ」と言われて敬遠されるが、欧米社会ではむしろタフネゴシエーターとして評価される。いわば「智に働けば、一目置かれる」。
前出の長谷川氏も著書で、ヘーゲルが智の働きを重視していることを、こう述べている。
「ヘーゲルは、近代的な個の自由と自立を確立する上で、知の働きこそがもっとも基本的な要因をなすと考え、個の自由と自立をめざす『意識』の旅を自立した知への旅として描いてみせたのだ」
ただし、日本について別の見方もある。日本人が日頃気が付かない指摘なので、こちらも紹介しておこう。