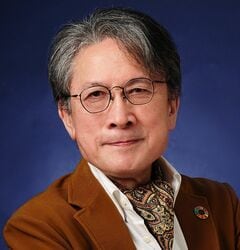写真提供: ZUMA Press/共同通信イメージズ
写真提供: ZUMA Press/共同通信イメージズ
物流と地球社会を持続可能にするために、今何が必要なのか。デジタル先端技術から経営戦略まで、世の誤解・曲解・珍解を物流ジャーナリスト・菊田一郎氏が妄想力で切りさばく連載企画。
第7回からは3回にわたり、物流の持続可能性を左右し、待ったなしの対策を迫られる人手不足の問題について考える。その①となる今回は、総人口と生産年齢人口の減少速度を比較しながら、この問題を乗り越えるための土台となる2つの視点を紹介する。
産業の基本構造を揺るがす「受給逆転」
佳境を迎えた「物流2024年問題」。荷主産業界がそこからくみ取るべき最大の教訓の1つは、「物流業者から<選ばれる荷主>にならなければ、事業が持続不可能になってしまう!」との現実認識だと、私は思う。
問題の発端は、1990年代の物流規制緩和策にある。参入障壁低下とバブル崩壊による需要低下があいまって、ドライバーとトラックの物流供給力が貨物輸配送の需要をはるかに上回り、「供給過多/需要不足」のレッドオーシャン化した市場は荒廃、持続不能の危機に陥った。それがようやく反転し、「供給不足/需要超過への歴史的転換点」を迎えようとしている。
この「受給逆転」には、産業の基本構造を揺るがすほどのインパクトがある。コロナ期から昨年度まで輸配送力の供給超過傾向がしぶとく続いてきたので、「逆転」をまだ実感していない業界も多いかと思うが、直近のNX総研・物流短観はマイナス圏に沈み続けていた需要が2024年度、3年ぶりに微増ながら反転すると予測している。その動きにかかわらずドライバー数が減り続けるなら、<運命の日>がいずれ訪れることは「ほぼ確定事項」と言ってよい。
ところが、不足する物流の担い手は、ドライバーだけではないのだ。筆者はフィジカル面に着目し、「これからは物流現場作業者も払底し大変な人手不足になる、準備を」とあちこちで警鐘を鳴らしてきた。それが今やフィジカルな現場作業の大半を担う非正規従業員だけでなく、オフィスの正規従業員も含めて不足感が強まっている。輸配送の物流需給が足踏みしている間に、人材全般の需給はすでに逆転し、人手不足時代に突入した模様である。
わけても中小企業の状況は厳しい。日本商工会議所がこの1月に全国の中小企業 6013社に聞いた調査結果では、人手が「不足している」と回答した企業は「65.6%」と3社に2社を占め、前年同時期(64.3%)から1.3ポイント増加。うち2024年問題が直撃する「建設業/運輸業」では、「78.9%/77.3%」と8割近く!に及んでいるのだ
( https://www.jcci.or.jp/news/research/2024/0214110000.html)。