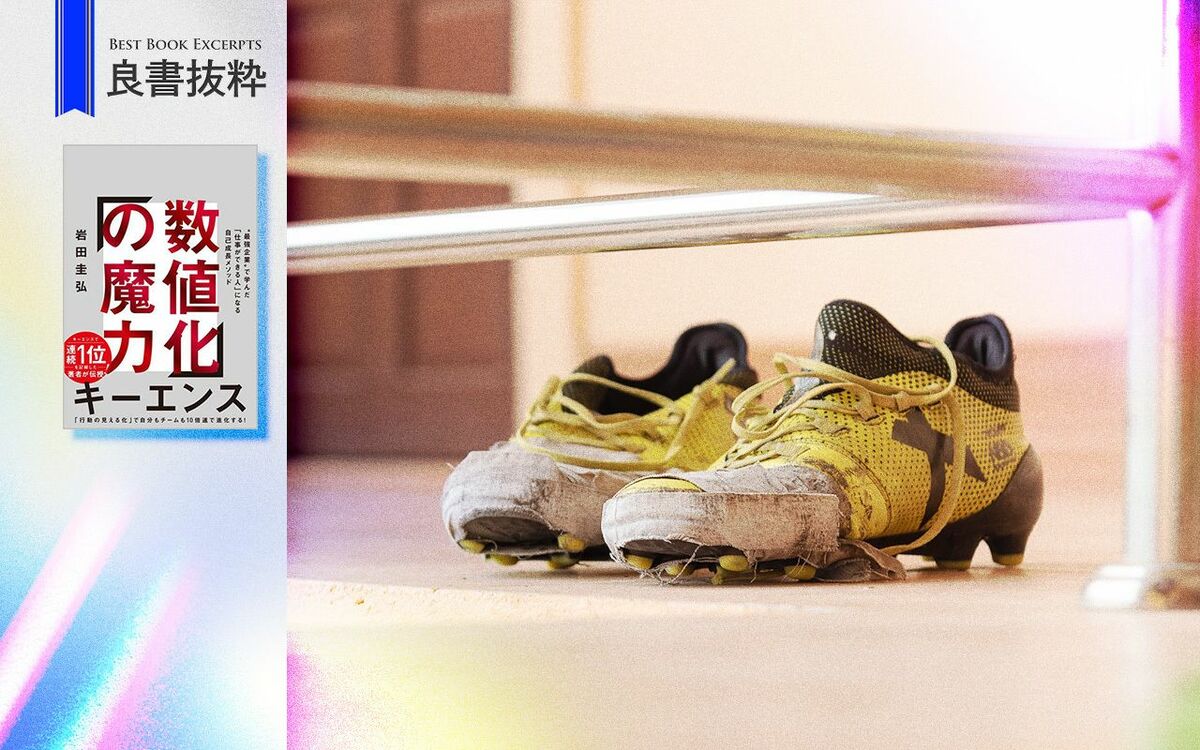 Noy Bounthavong/Shutterstock.com
Noy Bounthavong/Shutterstock.com「行動の量」を増やすことは成果を高める最短ルートになる。
プレゼンの質がどれだけ高くても、顧客に予算がなければ商談につながりにくい。「行動の質」はコントロールが難しい一方、「行動の量」を増やすことは成果を高める最短ルートになる。“キーエンスの数値化”を実践してきた岩田圭弘氏は「仕事の成果が低いのは、単純に量が足りていないケースがほとんど」という。本連載では、『数値化の魔力“"最強企業”で学んだ「仕事ができる人」になる自己成長メソッド』(岩田圭弘著/SBクリエイティブ)から内容の一部を抜粋・再編集し、最小の努力で成果を最大化する数値化の秘訣を紹介する。
第4回は、「行動の量」をコントロールすることについて解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 毎日の業務を数値化すると、なぜ“10倍速の成長”が可能になるのか
■第2回 “会社から与えられた目標”をゴールに設定すると、なぜ未達に終わるのか
■第3回 仕事の成果が低い時、「能力不足かも」と悩む前にすぐやるべきこととは?
■第4回 「行動の量」を増やすことが、“根性論”にならない理由とは?(本稿)
■第5回 「行動の量」を増やしても、残業が増えない発想とは?
■第6回 なぜ、「数値目標が設定しにくい業務」の数値化が重要なのか?
■第7回 部下を“茹でガエル”にするマネジャーの、典型的なチームの状態の捉え方とは
■第8回 数値化が苦手なマネジャーは、なぜ感情的に部下を叱るのか?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
■「行動の量」はコントロールしやすい
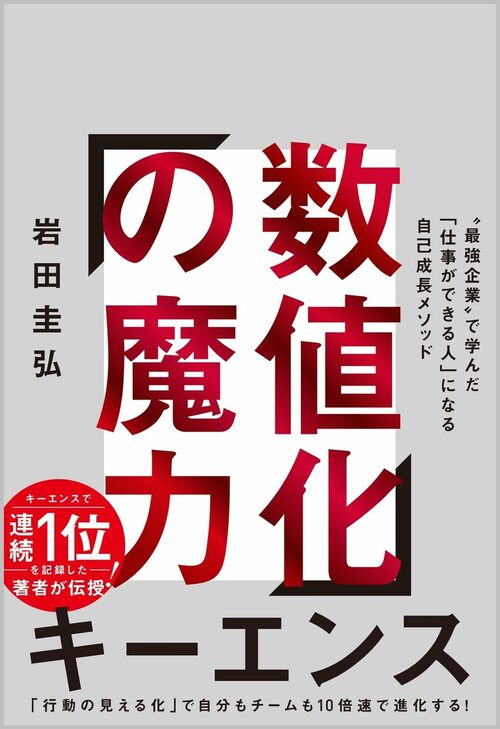 『数値化の魔力』(SBクリエイティブ)
『数値化の魔力』(SBクリエイティブ)
もう一つ、「行動の量」から着手するべき理由として、「行動の量」はコントロールがしやすいという点が挙げられます。
たとえば、営業でいう「商談化率」や人事でいう「入社率」などは、自分ではどうにもできない部分が残ります。
どんなにあなたが質の高いプレゼンをしても、顧客側の予算が足りないという理由で、商談化しない可能性もあります。
どんなにあなたが良い条件提示をしたとしても、応募者側の価値基準で別の会社を選ぶかもしれず、入社には至らないかもしれません。
「行動の質」を考える際、多くの場合で「相手」という不確実な存在がいるため、どうしても自分でコントロールできない部分が残るのです。
一方で、「行動の量」は自分次第で容易に増やすことができるケースがほとんどです。
営業であれば、「DM」や「電話」の数を増やせるかどうかは、自分が「DMを送る」「電話をする」という行動を起こすかどうかという、ただそれだけです。
人事であれば、「応募数」を増やすには、求人広告を増やすか、エージェントを増やすかどうかだけであり、比較的自分次第でどうにかなるケースがほとんどです。
特に若いビジネスパーソンでまだ経験もスキルも十分ではないという場合は、「行動の量」を増やすことが成果を出すための最短ルートとなります。
■「行動の量」は自分の精神面を守ってくれる
また、他にも「行動の量」から着手したほうがいい理由として、「自分の精神面のケア」に役立つという点が挙げられます。
そもそも、人は無意識のうちに「行動の質」に逃げがちです。
あなたも日々仕事をする中で、「自分の打診の仕方に問題があるのではないか」「自分の話し方に問題があるのではないか」と自分の能力や技術力、つまり「行動の質」ばかりに目が行くのではないでしょうか。
あるいはこれが行き過ぎると「自分に人間的魅力がないからいけないのではないか」といった考えに至ってしまう場合もあります。
いずれにせよ、最初から「行動の質」を考えてしまうと、自分を必要以上に責めてしまい、気分の浮き沈みが生まれてしまいます。
しかし、実は多くの場合、「単純に量が足りていない」ケースがほとんどだったりします。








