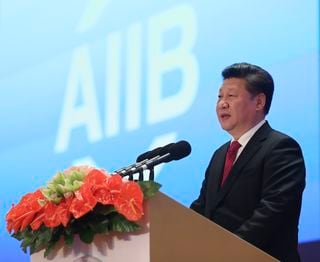自己啓発ツールとしての戦死
――本書は、(1)どういう戦死なら受け入れられるのか、(2)自己啓発ツールとして戦死(特攻の歴史)が使われている現状、(3)特攻×自己啓発という現象がもたらすものという3つのパートで構成されています。
戦死について考えることは、どんな立場の人でも心を揺さぶられると思いますが、特に(2)は衝撃的でした。特攻隊を題材にした小説や映画がヒットし、そのブームでの聖地巡礼や「泣けるパワースポット」として陸軍の特攻基地があった知覧を訪れる人が多いのだと思っていましたが、まさか非行生徒の更生、企業やスポーツ選手の研修の場となっているとは知りませんでした。戦死した特攻隊員の物語や遺書が、ダメになりかけている人や頑張ろうと思っている人に「活」を入れる自己啓発に使われている。
井上義和氏(以下、井上) 知覧を訪れ、戦死した特攻隊員の物語に触れることでポジティブな力を引き出す「活入れ」は、戦争の悲惨さや指導責任とは切り離して、何のために、誰のために自分の命を使うのかを考えるという、普遍的で純化された気持ちを呼び起こすものです。「お国のために命を投げ出す」自己犠牲ではなくて、「大切な人のために命を使う」こと、つまり「使命」を見出して、誰かのために自分のできることをひたむきにやるといった利他的な意識と行動が促されるのです。
 井上義和:1973年長野県松本市生まれ。ロボット工学の研究者を目指し京都大学工学部に進学するも、吉田寮で寝起きするうち人文社会系の学問に目覚め、「遅れてきた」思想青年として教育学部に転学部。博士後期課程を1年で退学し京都大学助手。その後関西国際大学を経て、帝京大学准教授。著書に『日本主義と東京大学』(柏書房)、『知識人とファシズム―近衛新体制と昭和研究会』(共訳・柏書房)、共著に佐藤卓己・河崎吉紀編『近代日本のメディア議員―〈政治のメディア化〉の歴史社会学(創元社)などがある。(撮影:URARA)
井上義和:1973年長野県松本市生まれ。ロボット工学の研究者を目指し京都大学工学部に進学するも、吉田寮で寝起きするうち人文社会系の学問に目覚め、「遅れてきた」思想青年として教育学部に転学部。博士後期課程を1年で退学し京都大学助手。その後関西国際大学を経て、帝京大学准教授。著書に『日本主義と東京大学』(柏書房)、『知識人とファシズム―近衛新体制と昭和研究会』(共訳・柏書房)、共著に佐藤卓己・河崎吉紀編『近代日本のメディア議員―〈政治のメディア化〉の歴史社会学(創元社)などがある。(撮影:URARA)特攻隊から「命のバトン」を受け取る
――「活入れ」には2タイプがあると紹介されています。1つは、「断絶・対照関係」で、「戦争の時代を思えば、平和な時代を生きている私たちは幸せ、平和な時代に感謝」「特攻隊員のことを思えば、自分の苦労など大したことはない」というタイプで、こちらはなんとなく理解できます。もう1つの「連続・継承関係」は、大切な人の幸せと祖国の未来のために命を使った特攻隊員に感謝し、彼らから受け取った命のバトンを次世代にリレーしていこうという「感謝・利他・継承」がセットになったタイプです。どうも私には、この「命のバトンリレー」そのものと、なぜ特攻隊員からバトンを受け取るのかが、腑に落ちないのですが。
井上 自分という存在はどこからきて、どこへ行くのかを突き詰めていくと、きっとバトンリレーの考え方に行きつくと思います。学校教育の中で命について教えようとすると「命あるものは大切にしましょう」とか、「親がいて、そのまた親である祖父母がいて・・・」という個々の命の大切さや家族のつながりを教える程度で終わってしまいがちです。
しかし、大人になり年老いていく間に、家族を持ち、子を生み育て、親を看取り、やがて自分も子や孫の世話になっていくであろうこと。企業で創業者の想いが受け継がれ、そのDNAを自分たちが守り、さらに良くして次の世代に渡すこと。いま便利に暮らしている国土が破壊の後につくられ、自分たちが維持・発展させて子や孫の時代にも不便な思いをさせないようにすることなど、まともな家庭人、まともな社会人であろうとすれば、必ず「命のバトンリレー」に思いが至ります。
つまり、これはどんな大人にも突き刺さる話なんです。私も40代になって、自分がバトンリレーの中継者であると強く思うようになりました。