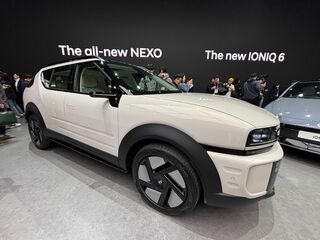マレーシア・クアラルンプールのミャンマー大使館前でロヒンギャ人の迫害に抗議する人々(2015年5月21日撮影)〔AFPBB News〕
残り5098文字
また、注目されたのは、自ら民族宗教、人種差別と戦ってきたノーベル平和賞受賞者のデスモンド・ツツ大司教やジョゼ・ラモス・ホルタ元東ティモール大統領などの出席だったが、そこには、同様に今回の当事国のミャンマーの民主化運動を指揮し、135もの少数民族がモザイクのように織り成すミャンマーの少数民族の権利擁護を最優先課題に掲げきたスーチー氏の姿はなかった。
29日のバンコクでの国際会議でも同様だ。これだけ、国際社会で大きな問題に発展し、アンダマン海で約3500人ほどのロヒンギャ族が木造の古びた船で数か月以上漂流を強いられている今でも、彼女はかたくなに沈黙を守っている。
南アフリカのアパルトヘイトと闘ってきたツツ大司教は「不当行為に中立ならば、あなたは迫害者であることを自ら選択したことになる」と国際社会に行動を促すよう呼びかけるとともに、反政府運動を展開してきた“同胞”のアウンサンスーチーを異例にも厳しく批判した。
インドに亡命し、今年の4月には日本を、現在はオーストラリアを歴訪中の“世界で最も著名な難民”とも言える、同じくノーベル平和賞受賞者のチベット仏教の最高指導者のダライ・ラマ14世も次のように苦言を呈した。
「とっても悲惨なことだ。スーチー氏とはこれまでロンドンとチェコで面会し、この問題に触れたが『非常に複雑な問題』と言っていた。ノーベル平和賞受賞者として彼女が行動を起すことを希望するし、彼女にできることはある」
ロヒンギャ族受難の歴史
仏教徒が9割を占めるミャンマーに居住する少数派イスラム系のロヒンギャ族の受難は、今回に始まったことではない。
1970年代、1990年代に軍事政権による財産没収、強制労働、さらには移動制限を強いられ、教育や商業活動にも制限を加える迫害を執拗に受け、バングラデシュ、タイ、マレーシアなどに数十万人が逃げ出している。
近年では、2012年、仏教徒の女性がロヒンギャ族の男性に殺害された事件をきっかけに暴動が勃発し、ロヒンギャ族を中心に 約200人が死亡、14万人が家を焼かれ失った。
ミャンマー政府はロヒンギャ族を難民キャンプに隔離するなど、「アジアのアパルトヘイト政策」を強いるだけでなく、半年後に迫った11月予定の総選挙と大統領選を見据え、今年4月には、ロヒンギャの暫定的な在留資格の「臨時身分証明証」も廃止し、“民族浄化”に拍車をかけている。