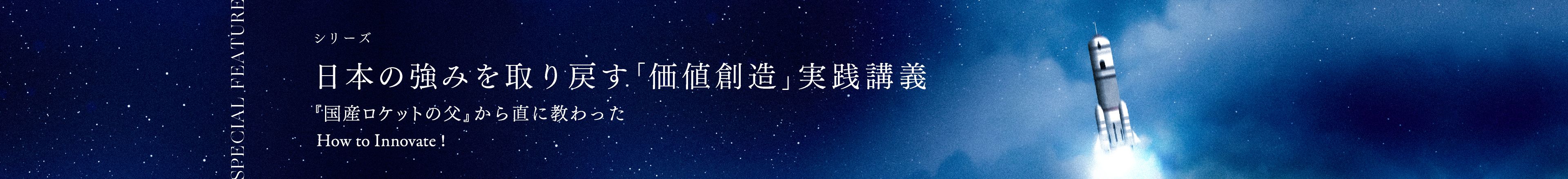東京・国分寺で全長23センチの鉛筆のようなロケットを発射台に取り付ける作業を見守る糸川英夫教授(写真提供:共同通信社)
東京・国分寺で全長23センチの鉛筆のようなロケットを発射台に取り付ける作業を見守る糸川英夫教授(写真提供:共同通信社)
「ものづくり大国」として生産方式に磨きをかけてきた結果、日本が苦手になってしまった「価値の創造」をどう強化していけばよいのか。本連載では、『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』(日経BP)の著者であり、故・糸川英夫博士から直に10年以上学んだ田中猪夫氏が、価値創造の仕組みと実践法について余すところなく解説する。
連載第1回となる今回は、「創造性組織工学」と「トヨタ製品開発システム」という日本独自の2つの価値創造システムを取り上げる。
<連載ラインアップ>
【Part1】価値創造システムのルーツ(本シリーズ)
【Part2】価値創造システムの組織のカタチ
【Part3】価値創造システムのPM論
【Part4】価値創造システムの2つのスキル
【Part5】価値創造システムのプロセス
【Part6】価値創造システムのオルタナティブ生成
【Part7】価値創造システムの組み合わせ
【Part8】価値創造システムの人材育成
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
価値創造システムとは何か
人が価値を創造する主役である。人はコストではなく資源である。人によって創造された価値が商品やサービスとなり、顧客を満足させ企業が収益を上げる。この極めて当たり前のことが忘れ去られてしまった歴史が日本にはある。このことを、次の3つの区分で簡単に振り返ってみよう。
1982年、IBMスパイ事件により、何でも欧米から学べばいいという時代は強制的に否定された。当時は創造性や独創性の必要性が強烈に叫ばれた。しばらくすると「地価は必ず上がり続ける」という土地神話から有形資産のバブルが起き、社員が価値を生み出す創造性の必要性はしぼんでしまった。
1992年、バブル崩壊後の失われた30年が始まるのと同時に、日本でERP(統合業務基幹システム)の導入が始まった。ベストプラクティスであったはずのERPに、膨大なカスタマイズを加えるためグローバルコンサルティングファームが大活躍する時代になる。さらに、2012年からのアベノミクスが有形資産の価値を押し上げ、人が価値を創造するイノベーションが忘れ去られた。
2024年、日本は生産労働人口が減少する中、労働参加率(女性、高齢者含む)がOECD諸国の中でも高い水準に達し、50歳以上の人が全人口の50%を超えるという超高齢化人口減少社会に突入する。働き方改革があらゆる業種で始まっている。⬅ 今ココ
このような歴史をたどった日本は「ものづくり」が強みと言われ、生産現場のカイゼン活動が注目されてきた。しかし、長年にわたってものづくりの現場を調査研究してきた経営学者の藤本隆宏氏は「生産=設計情報の転写、企画開発=設計情報の創造」と表現している。つまり、ものづくりの生産と企画開発を別物と表現しているのだ。
このことは本で考えると分かりやすい。世界40カ国1000万部以上のベストセラーとなった近藤麻理恵さんの『人生がときめく片づけの魔法』(サンマーク出版)は、本の企画立案をした編集者と著者がいて、世界中の印刷工場が原稿を1000万部以上転写した。つまり、「印刷=原稿の転写、企画執筆=原稿の創造」と表現できる。このように本の印刷と企画執筆は別物だ。さらに、Kindleになるとダウンロード=生産となり、価値を創造するのは企画執筆だけになる。
私たちが今までものづくり大国として議論してきたのは、生産のことばかりだった。IoTを駆使した生産技術はもちろん、MRP(資材所要量計画)、TPS(トヨタ生産方式)、TOC(制約条件の理論)といった生産方式が議論の中心だ。