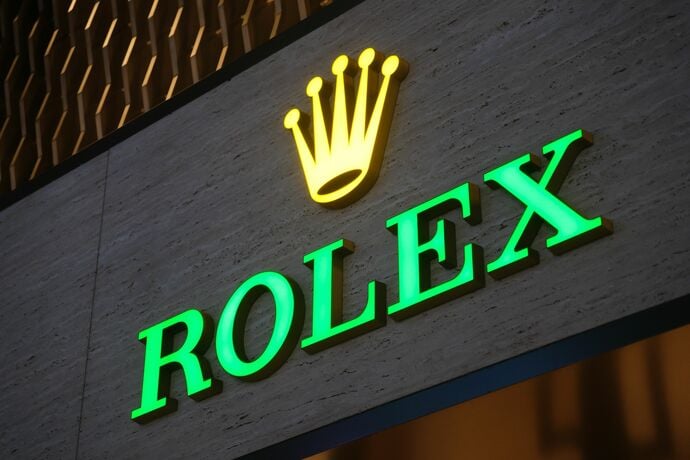testing/Shutterstock.com
testing/Shutterstock.com
デザインは、企業が⼤切にしている価値、それを実現しようとする意志を表現する営みである――2018年に経済産業省・特許庁が発表した「デザイン経営」宣言の一節だ。世界の有力企業はデザインをどのように経営戦略の中に位置づけ、ブランド価値の向上やイノベーションの実現を成し遂げてきたのか。本稿では、『デザイン経営 各国に学ぶ企業価値を高める戦略』(小山太郎著/中公新書)から内容の一部を抜粋・再編集。イタリア、アメリカ、中国、韓国、北欧、そして日本を代表する企業の事例を取り上げ、デザインをてこに競争力向上を図る経営の在り方を解説する。
大型家電市場で圧倒的な強さを誇る中国メーカー・ハイアール。同社のデザイン経営の特徴である「工学的設計」とは? 数々の先進的な取り組みから明らかにする。
マイクロ企業が牽引するデザイン経営 ハイアールの事例
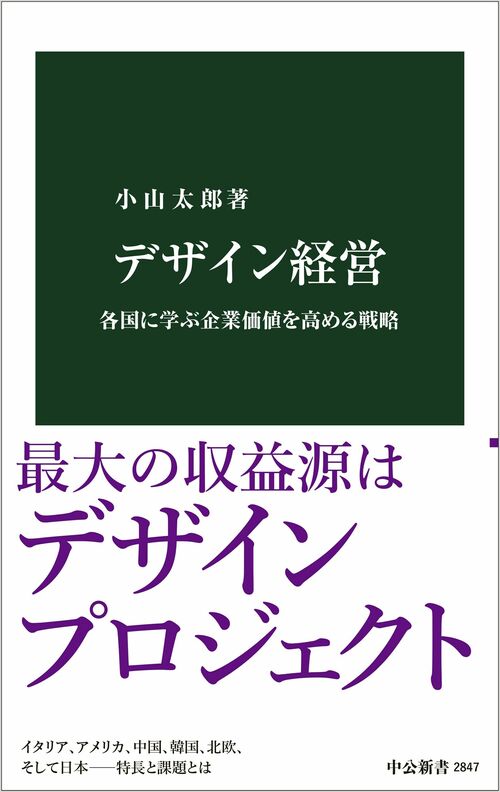 『デザイン経営 各国に学ぶ企業価値を高める戦略』(中央公論新社)
『デザイン経営 各国に学ぶ企業価値を高める戦略』(中央公論新社)
■ 人単合一と市場連鎖(SST)管理システム
1984年に、張瑞敏(チャンルエミン)氏は、ハイアール(海爾)の前身である青島(チンタオ)日用電器廠の社長に任命され、工場改革を開始した(5)。給与の遅配や悪臭がするといった職場環境の悪さなどから従業員の士気は低く、暖を取るため工場の窓枠の木が外されて燃やされる状況であった。
張氏は、6S(整理、整頓、清掃、清潔、躾、安全)の推進、アメリカ市場への進出、「人単合一」と市場連鎖(SST)管理システム、およびWin-Win付加価値計算の導入を推進して、2021年には、4.4兆円の売り上げを達成した。2023年時点で、大型家電の世界市場シェアは15年連続1位である。
2005年から導入された「人単合一」の人とは従業員(人材)、単はユーザー(市場)からの注文を意味し、従業員とユーザーとの間の距離をゼロにすることを目標とするものである。企業は従業員のものであるとする日本型企業システムとは異なり、ハイアールの場合は、企業はユーザーのものであり、ユーザーに付加価値をもたらすことが企業活動の目的であるとする。
これは、企業は株主のものとする欧米企業の株主資本主義とも異なる。ハイアールでは、ユーザーと最も接点の近い顧客対応を行う従業員が自主的な経営体――これは一種の戦略的事業単位(SBU)である――として、企業の職階ピラミッドのトップに位置づけられる。そして従業員は、前工程の作業者を仕入れ先、後工程の作業者を顧客、作業内容を商品とみなすことで、企業内部にいながらあたかも市場で取引を行う経営体へと転化する。
(5)本節は、Frynas et al.(2018)、Hamel et al.(2018)、Lu et al.(2020)pp.217-221、徐他(2016)pp.98-102、徐(2020)、 辛(2015)pp.59-66 およびpp.114-117、吉原他(2006)、娄他(2016)pp.92-98に基づく。